精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくるために 第17回:相談って難しい
2025/09/25
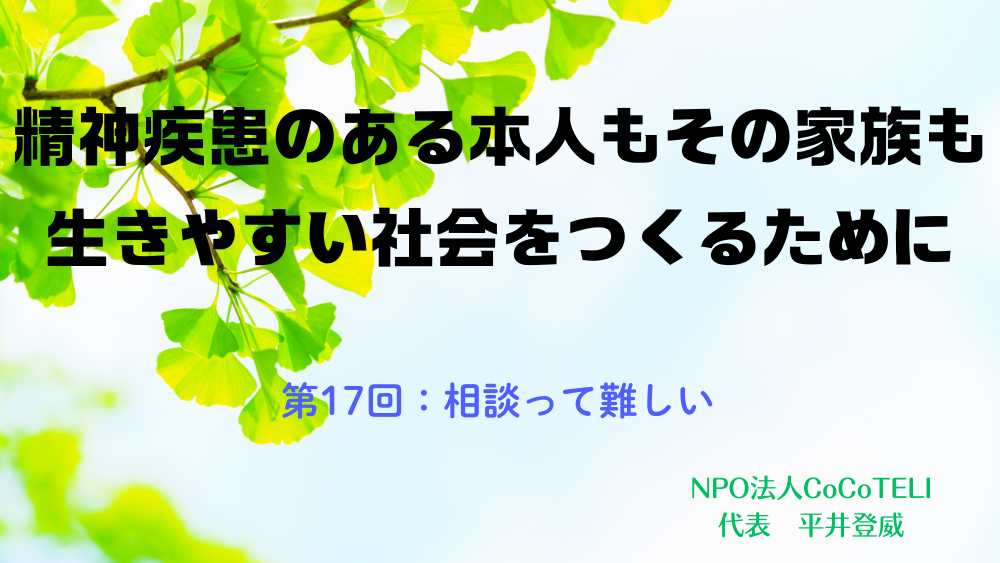
みなさん、こんにちは。2001年生まれの大学生で、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を行うNPO法人CoCoTELIの代表をしている平井登威(ひらい・とおい)です。
「精神疾患の親をもつ子ども」をテーマに連載を担当させていただいています。この連載では、n=1である僕自身の経験から、社会の課題としての精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻く困難、当事者の声や支援の現状、そしてこれからの課題についてお話ししていきます。
第13回から、CoCoTELIの活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いています。今回は、相談って難しいよなあということをテーマに書いていけたらと思います。
著者
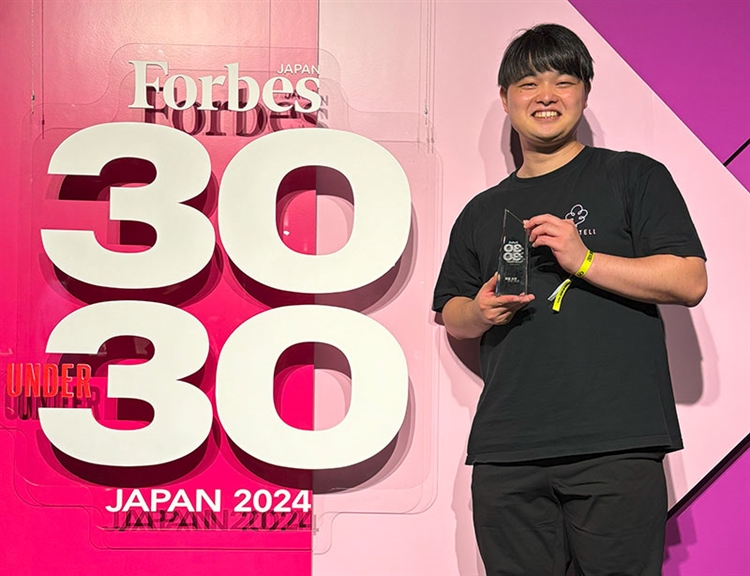
平井登威(ひらい・とおい)
2001年静岡県浜松市生まれ。幼稚園の年長時に父親がうつ病になり、虐待や情緒的ケアを経験。その経験から、精神疾患の親をもつ子ども・若者のサポートを行う学生団体CoCoTELI(ココテリ)を、仲間とともに2020年に立ち上げた。2023年5月、より本格的な活動を進めるため、NPO法人化。現在は代表を務めている。2024年、Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30人に選ばれる。
相談って難しい!
皆さんには、気軽に相談できる相手はいますか?
困ったことがあったとき、すぐに人に相談できますか?
「相談するのは難しい」と感じた経験がある人は、少なくないのではないでしょうか?
僕自身、精神疾患の親をもつ子どもや若者と出会うなかで、彼ら・彼女らにとって家庭の悩みを誰かに相談することのハードルの高さを強く感じています。
勇気を出して話しても、理解してもらえないかもしれない。怒られてしまうかもしれない。あるいは、相手は良かれと思ってアドバイスをしてくれるかもしれませんが、その言葉がかえって自分を傷つけることもあります。さらに、話した内容が周囲に広まってしまい、身近なコミュニティに知られてしまうかもしれない。精神疾患への偏見から、いわゆる「村八分」のような状況に置かれてしまう可能性もあります。
そんな「相手がどう反応するかわからない」という不安は、相談という行為を阻む大きな要因になっていると感じます。
相談とは、そうした数えきれない不安やリスクを乗り越えたうえで初めて成り立つ行為です。
そもそも相談の前提として必要となることが多いのは「自身の状況を自覚すること」「それを言葉にすること」「相談する勇気を出すこと」です。しかし、家庭という閉じた環境のなかでは自分の状況を客観的に捉えるのは非常に難しく、その時点で大きなハードルになっています。
さらに、親の病気について説明を受けていない子どもも多く、自分の困りごとや悩みに名前がつけられず、「どう説明したらいいのかわからない」と感じるケースも少なくありません。
加えて、精神疾患に対するスティグマ(偏見)も相談の大きな壁となります。
友達が精神疾患をもつ人を馬鹿にしていた、SNSで精神疾患に対する差別的な書き込みを見た、そのような場面を経験することで、「親が精神疾患であることを知られたら馬鹿にされるかもしれない」「大切な親を笑われるかもしれない」「笑われるだけでなく仲間はずれにされるかもしれない」という不安が浮かびます。その結果、相談すること自体のハードルはさらに高くなってしまいます。
僕たちは日々、スティグマが子どもたちにどれほど大きな影響を与えているかを強く感じています。
「相談しなくてもよい」も大切なのではないか?
そんな「相談のハードルが高い」社会のなかで、「相談しなくてもよい」という選択肢が実はとても大切だと思っています。
もちろん、相談はとても価値のあるアクションです。相談を通じて救われることも数えきれないほどあります。ただ、そのハードルがあまりにも高く、「相談しなければ何も始まらない」とされてしまうなら、相談以外にも一歩を踏み出せる選択肢があっていいのではないでしょうか。
僕自身を含め、多くの人が「困ったときは相談してね」「一人で抱え込まずに相談することが大事」と言います。確かにそれは正しいし、大切なことです。でも、先に触れたように相談という行為は想像以上に難しく、誰でも簡単にできることではありません。
だからこそ、結果が前向きに転ぶか悪い方向に転ぶかわからないなかで「相談してね」とだけ投げかけられる言葉は、ときにとても酷に響くことがあります。
そう考えたときに、もし「相談」という行為を100だとするなら、その100に至るまでに30や60といった中間地点が用意されていたらいいのにと思います。
「相談しなくても休める場所がある」
「相談しなくても自分を守れる仕組みがある」
「相談しなくてもつながれるコミュニティがある」
こうした“グラデーションのある”支援や選択肢が広がっていくことで、人は「相談する/しない」という二択から解放されていくのではないでしょうか。相談できない自分を責めるのではなく、「いまは相談しなくてもいい」「別の方法で安心を得られる」という感覚をもてることが、結果的に次の一歩につながることもあるはずです。
相談そのものを否定しているわけではありません。むしろ相談はとても尊い行為です。ただ同時に、「相談できない」という状況も否定されるべきではないと思うのです。
大事なのは、「相談するか/しないか」という二択だけではなく、「相談しなくてもいい」「相談しなくても支えられる」という多様な選択肢が存在すること。それこそが社会の豊かさであり、人が少しでも生きやすくなる道なのだと信じています。
いろんな選択肢が当たり前に広がっていくことを、僕は心から願っています。
そんなことを思いながら、CoCoTELIでは「相談しなくてもよい」ということを掲げ、Podcastやメディアを運営しています。
CoCoTELIのHPまできたけれど相談できない。そんな人もたくさんいるはずです。
相談しなくてもロールモデルと出会える、相談しなくても知るとためになる情報と出会える、そんな可能性を上げていきたいなと思っています。
本連載のなかでは描ききれていないことや当事者とのリアルな会話をお届けしています。関心のある方はぜひご覧ください。
▼感情を取り戻したことで感じたしんどさ。双極性障害とパニック障害を有する母親の元で育ったみすずさん(仮名、19歳)
▶ https://cocoteli.com/storys/misuzusan
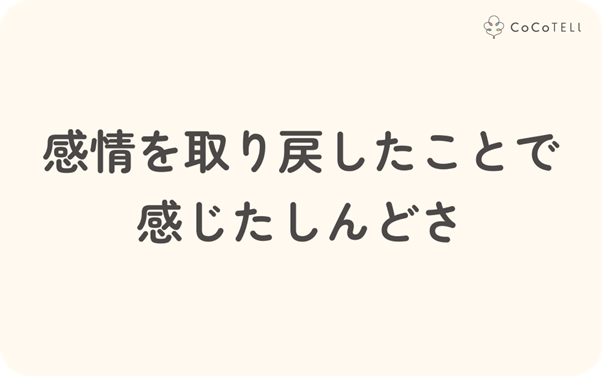
▼“子どもだから”と我慢しているあなたに知ってほしい”子どもの権利”
▶ https://cocoteli.com/facts/childrights

▼#11「親を許さなくても良い」ゲスト:桜井みよさん(株式会社Empathy4u ヤングケアラーピア相談員/理学療法士/精神保健福祉士)
▶ https://open.spotify.com/episode/0TSAHHrreOhf2rbei0scQY?si=yNz8T2w0RDmzYyvR3lBVFw
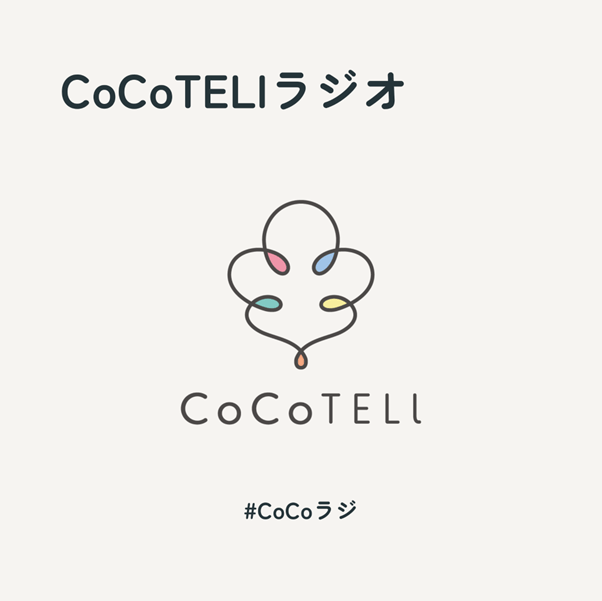
次回以降も日々の活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いていけたらと思います。
関連書籍
中央法規出版では,『精神疾患のある親をもつ子どもの支援』という書籍を発刊しました。参考にしていただければ幸いです。
