【vol.20】一つのお粥だけだと飽きてしまうかと思って | 私はミューズとゼウスのケアラーです
2026/01/21

韓国の介護現場で働く作家が送るケア文学
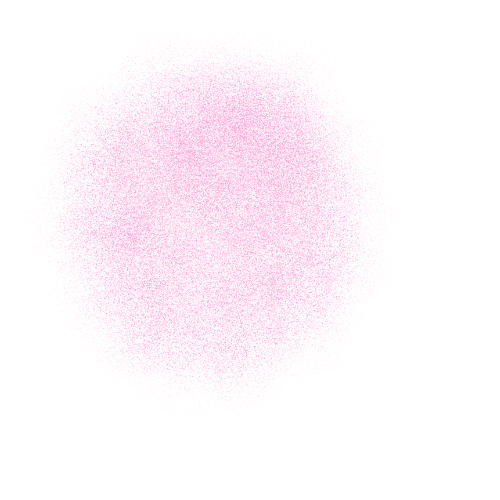 激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
-
そんなイ・ウンジュさんは韓国で、ケアについてのエッセイ三部作(『私は神々の療養保護士です』『こんなに泣いて疲れたでしょう』『東京因縁』)を出版して話題を集め、2023年には母親の在宅療養保護の経験を盛り込んだ『ケアの温度』を刊行しました。ケア三部作の『私は神々の療養保護士です』では、療養保護士として歩んだ療養院での日々から訪問介護に至るまでの道のりについて、『ケアの温度』では、誰かをケアする時の適切な距離感・温度感とレジリエンスについて、やさしい筆致で綴っています。この連載では、イさんの目に映った韓国の介護現場から、「ミューズとゼウス」のためのケアについて考えます。
月曜日の朝、孫を保育園に送り届けて、ドンシムビル103号の前に立って呼び鈴を押す。10時10分少し前、玄関のドアが開いた。残業を終えて帰ってきた四十代の男性――ミューズの息子である。
介護施設での勤務を辞めて3か月後、在宅訪問介護士として出会ったミューズについて、私が知っていることは少ない。軽度の認知症と筋無力症で寝たきりであり、ミューズの介護は同じく軽度の認知症を患う夫と、この息子が担っているということだけ。
三日月のように痩せたその男は、母親の部屋のほうへ目を向け、かすかな笑みを浮かべて、朝の挨拶の代わりに自分の部屋へと入っていった。夜勤を終えて、これから眠るのだろう。
部屋に入ると、ミューズの枕元に貼られた思い出の写真がまっ先に目に入ってくる。 満面の笑みを浮かべる二十代の息子の写真と、やはり満面の笑みを浮かべている夫婦の懐かしい写真が額縁に入っていたり、壁に直接貼られたりしている。
ミューズの部屋にはテレビがない。いや、家中のどこからもテレビの音がしない。夜勤から帰ってくる息子への配慮なのか、それとも以前からテレビのない生活を好んでいたのだろうか。おそらくそのようだ。静かな室内で響くのは、私が動くときの音だけだ。
横たわるミューズのところに行って、手を握りながら挨拶をする。ミューズもまた嬉しそうな顔で迎えてくれた。
「顔が明るくていいね」
「お元気でしたか?」
私もそう返しながら、エコバッグからバナナを取り出して差し上げる。
前回の訪問時、ミューズは昼食に出されたお粥を半分も食べられなかった。まるで、生きるか死ぬかを迷っているようなミューズの瞳。彼女の瞳をしっかりと捕らえていたかった――ちょうどそのとき、呼び鈴が鳴った。 同僚の介護士が到着したのだ。
朝の挨拶を済ませた私は、濡れたタオルでミューズの顔や手足を拭く。見知らぬ手が触れるたび、ミューズの体が緊張するのがわかる。次にローションを塗り、枯れ葉のように薄くなった枕を外して向きを変える。その途中、ミューズの夫が散歩から帰ってきた。
ドンシムビルの花壇で実ったイチジクの果実を摘んだらしく、皿に盛って「食べなさい」と差し出してくれる。
この家の男たちはどうしてこんなに目が綺麗なんだろう。先日入浴介助をしたとき、ミューズの息子は車いすに乗った母親に向かって、「ママ」と呼びかけながら笑った。その声とまなざしがあまりにも優しくて――朝、保育園に連れて行ったばかりの孫を思い出すほどだった。無条件の愛を受けている子供が発するような声で、四十代の男が母親を呼ぶ。
「ママ、そろそろお風呂に入るよ」
この声はどこかで聞いたような気がする。末っ子の甥が祖母を呼ぶ声にも似ている。あちこち痛む祖母を気の毒に思う、その末っ子の甥の声に滲む――限りなく切なく、愛情が込められた声。
ところが、今回はミューズの夫。認知症の初期とはいえ、自分もまた誰かの保護を必要とする高齢者が、妻を眺めるまなざしは息子と変わらない。
ちょうどおむつを替えている私たちの背後から、彼がうめき声に近い音を出す。
妻の臀部のあたりにできた赤い水ぶくれを見たのだ。お年寄りは声を殺して泣き伏せた。喉がかすれ、からからと鳥の鳴き声がする。
私も一緒に泣きたい気持ちだった。
幸いミューズは私たちに気づかず、壁に向かって横になっている。一日中おむつをしたまま同じ姿勢でいると、こうした水ぶくれができやすい。2009年から働いている同僚の介護士がおむつを開け(傷ついた部位には通気が一番)、右側へ体位変換をしてくれた。
私は準備してきたノートにメモを取る。残業明けの息子とコミュニケーションを取るには、やはりノートが必要だろうと思ったからだ。
<息子さまへ
伝達事項:
お母様の介護でお疲れのことと存じます。今後、伝達事項がございましたら、このノートに記入してください。
「デュパラック」をお持ちしました。この薬は、私の祖母が便秘で困っていた際に処方されたものです。効能についての説明書もご参照ください。お母様が錠剤を飲み込みづらいようでしたので、次回の処方時に薬局で粉砕してもらうようご相談されてはいかがでしょうか。
―介護士より>
メモを終え、部屋の掃除にかかる。昨夜飲み残された豆乳を捨て、水筒を拭き、床を雑巾で拭く。ベッドに散らばった抜け毛を拾い集める。体位変換で壁向きに寝ているミューズのそばで、介護士と私はミューズの足と背中を叩いたり揉んだりする。皮膚を刺激して、血行を促すためだ。
やがて昼食の時間。お粥の準備を始める。市販のお粥だ。毎回これを購入するのは出費がかさむだろう。実習生の立場ながら、空き時間に私が粥を作って差し上げられれば……と同僚に相談してみた。
「いい考えではあるけれど、最初はサービスを提供する側も、サービスを受ける側も、お互いに見極めることが必要なんです」とだけ、彼女は言った。
他の介護士にも助言を求めた。誰もが似たような生活の中で介護をしていて、おむつや治療費など出費が多いだろうに、食事まで買うのは負担になりすぎないか、と。その質問に、介護士はしばらく考え込んでから言った。
「人それぞれですからね。保護者が干渉だと感じるかもしれませんよ」
無知な私はその言葉に耳を貸さず、とうとうミューズの息子さんに聞いた。
「私がお粥を作ってさしあげるのは、どうでしょうか?」
返ってきた答えはこうだった。
「大丈夫ですよ。お粥が一種類だけだと、飽きるかと思って」
まさか、そんな深い意味があったなんて――なぜ私は気づかなかったのだろう! 考えが浅はかな自分に、限りなく恥ずかしくなった。
著者紹介
イ・ウンジュ 이은주

1969 年生、作家、翻訳家。日本に留学し、1998 年に日本大学芸術学部文芸学科を卒業。20 代から翻訳家になることを夢見て、家庭教師として働きながら翻訳した『ウラ読みドストエフスキー』(清水正)で夢をかなえる。その後も仁川国際空港の免税店で働きながら、休憩時 間は搭乗口 31 番ゲートで訳し、仁川への通勤電車でも訳し続け、『船に乗れ!』(藤谷治)、 『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(山極寿一)をはじめ、十数冊もの日本書籍を韓国に広める。おばあちゃんっ子だったイさんは祖母の逝去をきっかけに、高齢者施設でボランティア活動を始め、その後療養保護士の資格を取得。昨年からは認知症になった実母の介護を行う。「ケア」と「分かち合い」について、文学の一形態として追及してみたいという気持ちから、高齢者のケア現場についてのエッセイを三部作で発表し、韓国で共感を呼ぶ。現在、
