死をことほぐ社会へ向けて 第21回
2025/11/14
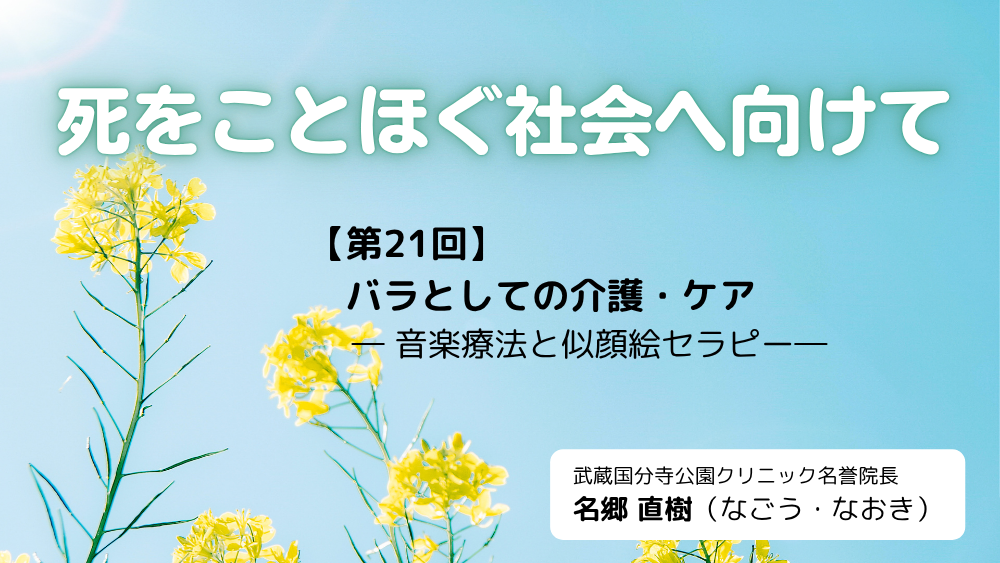
バラとしての介護・ケア ・・・音楽療法と似顔絵セラピー
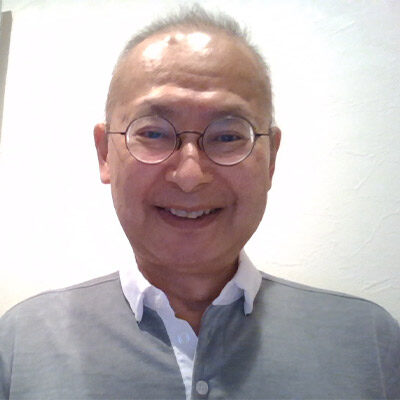
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
2025年7月に『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください!』(共著、日本医事新報社)が発売!
YouTube
X
認知症から老い全体へ
認知症に対して、予防や治療ができなくても、明日に向かって進んでいく老いと、死をコントロールできなくても、生きている限り、今の生活については介護・ケアが提供できるし、本人のみならず周囲への手助けもできる。さらに言えば、予防ができないからこそ、治療が限られているからこそ、コントロールできないからこそ、支援が必要だという側面もある。
これは一般的な老い全体にも敷衍できる。人は死に向かって老いていくほかない。老いに対して最新の医療でと言っても、あらゆる死亡率を下げたという最新の医療は、ある時点での死亡率を下げるだけで、その現実は死の先送りでしかない。そこでは、再び元気になるための上り坂の支援も重要だが、必ず必要になるのは下り坂の支援である。
下り坂の支援に「バラ」を追加する
この上り坂の支援と下り坂の支援には決定的な違いがある。前者は、再び上るために多くのものを犠牲にして回復を最優先する。例えば、入院すると食事介助が受けられなくなり、着替えも難しくなる。入浴はできなくなり、外出もできず、トイレもおむつに変わったりする。また、治療に伴う副作用や、医療費負担の増加といった心配もある。さらには、医療を受けたからと言って回復するという保証はない。それどころか、かえって悪化するということも珍しくない。老いが進み、介護が必要になるなかでの「医療を受けるかどうか」は、賭けの要素が大きい。
それに対して下り坂の支援では、賭けの要素はほとんどない。食事も着替えも、入浴も、くじに当たらなければ受けられないというものではない。介護・ケアを受けるということは現在に限ったことで、不確かな明日とは関係がない。また、介護保険を利用することで、誰でも受けられる。さらに、介護・ケアは、その他を犠牲にするというより、さらに生活に何か付け加えることができればという視点が重要になる。「人はパンのみに生くるにあらず」というわけである。「人は健康のためだけに生きる」という極端な医療化の対極にある。
そこで何を付け加えるか。生活の単なる支援でなく、そこに生活を彩るものを付け加えたい。それを「バラ」と呼ぼう。「バラ」を付け加えることができれば、そんなことを考え、訪問診療の現場でいろいろな取り組みをしている。そのいくつかをここでは紹介したい。
音楽療法士の同行
筆者が名誉院長を務めるクリニックでは、訪問診療の際に音楽療法士が同行し、訪問先で歌を歌ったり、楽器を演奏したりする。そのなかで印象的なエピソードを紹介したい。
神経疾患の進行で全身がマヒし、生活全般に対する介護を受けている方のこと。この方は身体を動かすことができないと、みんなが思っていた。しかし、音楽療法士が家族からこの方が好きだった歌を聴いてその歌を歌ったところ、歌に合わせて口が動いている。家族も訪問した医師や看護師もびっくりというか、衝撃である。腕を締め付けて血圧を測って、いる場合ではない。生活を維持するための介護・ケアだけで支援していると思うのも問題だ。下り坂こそ、「バラ」が重要だ。それをはっきり認識した瞬間であった。
似顔絵セラピーの提供
音楽療法士と同様に、病気の人を訪問して、いろいろ話を聞き、その人の人生を反映させた似顔絵を描いて患者にお渡しするという似顔絵セラピストとともに訪問し、診療終了後、希望がある患者に対して、似顔絵セラピーを提供するという取り組みも行っていた。
ある患者は、セラピーとして描いてもらった似顔絵を、次の訪問時に胸に抱いていた。家族が言うには、「前回描いてもらった絵を放そうとしないんですよ」とのことであった。
訪問診療の患者に対して、「安定していますね」と言って、血圧を測って帰ってくるというようなことは、「安定」という医療者側の解釈を押し付けて、何もしていない。しかし何もしていないのは、そこで医療ができることもないからだ。医者以外が、医療ではなく、その場の生活に何か付け加えることが、大きな希望につながったりする。安定した患者に必要なのは、医者による定期的な訪問でなく、医者以外による「バラ」の提供だということがここでも明確になった。
コストの問題とコストがかからない「バラ」の提供
その他では、園芸セラピー、アニマルセラピーなど様々な取り組みがある。しかし、これらすべてに共通するのは、介護保険の範囲外で、当事者が負担しなければいけないということである。ただでさえ少ない介護報酬のなかで、こうした取り組みを継続的に行うためには、コストの問題を解決しなければいけない。
そのコストの問題を現時点でクリアするのは、家族や介護・ケアに携わる方々のちょっとした一言であったり、冗談であったり、そこにも「バラ」を付け加えることはできる。筆者のクリニックでも、クリスマスの時にサンタクロースの仮装をして訪問したこともあるが、訪問先の子どもたちに喜んでもらえたこともある。筆者自身も、音楽療法士のように一曲歌ってみようかと思うこともあったが、実現しないままに訪問診療の現場を去ってしまった。ぜひ皆さんにもコストを無視してでも行える、ちょっとした「バラとしての介護・ケア」の実践に取り組んでもらいたい。
