独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.10 法的手続きと倫理・リスク管理
2025/11/07
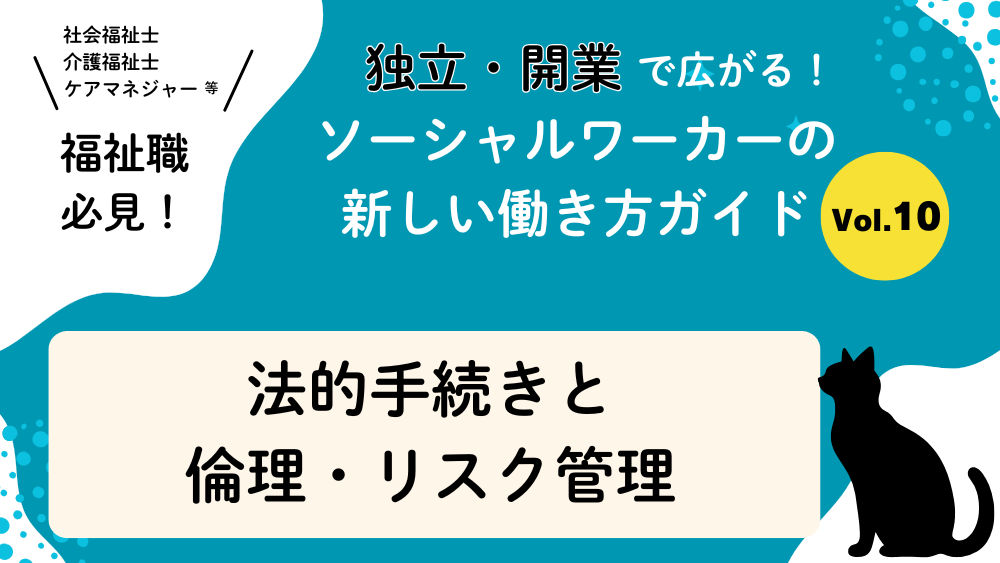
福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!
著者
小川 幸裕(弘前学院大学社会福祉学部教授)
横田一也(株式会社カラーサ・社会福祉士事務所カラーサ代表)
1. 事業の土台を築く「法的手続き」― パートナーとの連携で不安を乗り越える
「わからないことがわからない」という恐れとの向き合い方
法務局や市役所での手続きは、多くの人にとって未知の領域です。門田さんも当時の心境を「わからないことがわかっていないのではないかという恐怖もありました」と率直に語っています。
そのなかで門田さんが取ったのが、「最初から税理士と契約する」という決断でした。税務のような専門知識が求められる領域は、信頼できる専門家をパートナーにすることで、安心して事業の核心に集中できます。これは、一人で抱え込みがちな「経営責任の重圧」を乗り越えるための、非常に賢明な工夫といえるでしょう。
事業形態は「自分らしい船」を選ぶ
独立の形には、「個人事業主」と「法人」という選択肢があります。どちらを選ぶかは、これから始まる航海の「船」を選ぶような、大切な決断です。
自身が実現したい事業に法人格が必須かどうかを事前にリサーチし、自分のビジョンに合った形を選ぶことが大切です。自分のビジョンや活動内容に合わせて事務所の形態をじっくり考えることは、自分らしい働き方の実現につながります。
2. 自分らしくあり続けるために-信頼を育む倫理と事業を守るリスク管理
組織の看板をもたない独立・開業ソーシャルワーカーにとって、最大の財産は「あなた個人への信頼」です。その大切な信頼を育み、事業を長く続けていくために、倫理観のアップデートと、リスク管理について考えていきましょう。
倫理観を磨き続ける ― 外部の視点を取り入れる
一人での事業運営は、良くも悪くも他者のチェックが働きにくくなります。門田さんは「個人情報の取り扱いや倫理的課題への意識が薄くなりかけることもある」と、そのリスクを真摯に指摘しています。
この課題への対策として、門田さんは、専門職団体が開催する研修や勉強会に定期的に参加し、意識の再確認を続けています。こうした外部とのつながりは、孤立を防ぐだけでなく、専門性を維持・向上させるための生命線となります。
経済的な不安を乗り切る「羅針盤」をもつ
独立・開業後の収入は誰もが懸念する点です。門田さんも、事業が軌道に乗るまでの3年間は、以前の半分以下の報酬となり、貯金を切り崩して乗り越えたと語っています。
この荒波を乗り切るために作成したのが、ファイナンシャルプランナーの資格を活かした「5年間の収支シミュレーション」でした。この具体的な資金計画は、まさに航海の「羅針盤」です。未来を見通すことで、現在の経済的な困難にも冷静に対処できるのです。
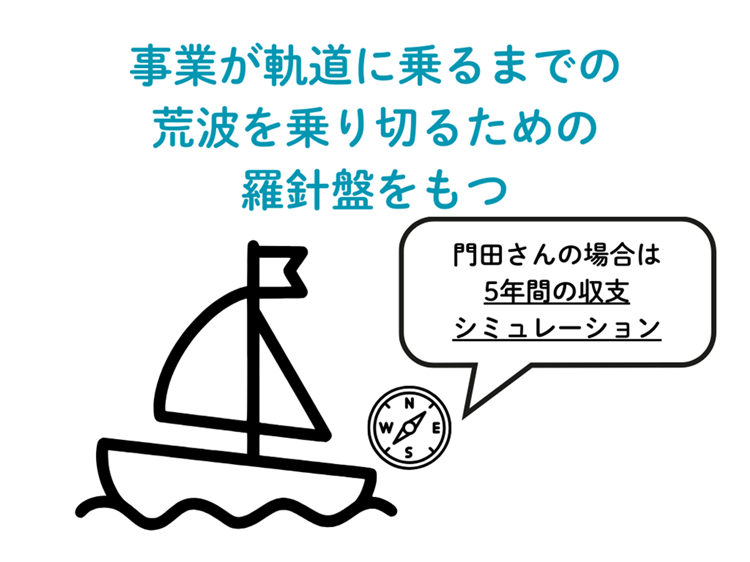
孤独感を力に変える「ネットワーク」
「最終的に自分が選択し、自らが決めて進めるしかないという強い孤独感が常にありました」。この言葉には、組織を離れ一人で進む覚悟が表れています。これは多くの独立経験者が直面する感情です。
しかし、門田さんは決して一人ではありませんでした。契約書の作成で困ったときなど、さまざまな人から支援をもらい、これまで築いてきたネットワークが、専門的な助言だけでなく、精神的な支えとしても大きな力になったと語っています。
Vol.6で解説された「ネットワーク構築力」は、専門的な手続きの場面だけでなく、心の支えという面でも、かけがえのない力になることがわかります。困難なときに支えてくれる人の存在こそが、孤独を乗り越え、前進するための最も価値ある資産なのかもしれません。
独立・開業は、自分らしい支援を形にできる、夢のある選択肢です。今回の門田さんの事例は、丁寧な準備と誠実な姿勢が、その夢をしっかりと支えてくれることを教えてくれます。
著者紹介
小川 幸裕(おがわ ゆきひろ)
弘前学院大学社会福祉学部 教授/社会福祉士。
独立・開業したソーシャルワーカーを対象とした調査に基づき、ソーシャルワーク実践の構造や要因を分析。研究活動の傍ら、地域の活動をとおして地域の社会福祉連携の推進に貢献し理論と実践の架け橋となる活動に取り組む。
横田 一也(よこた かずや)
株式会社カラーサ・社会福祉士事務所カラーサ 代表/認定社会福祉士(地域社会・多文化分野)・介護福祉士・介護支援専門員・大阪府人権擁護士等。
障害者・高齢者福祉分野を中心に支援経験を重ね、2012年に独立。ソーシャルワーカーとして子どもから障がい者・高齢者まで幅広い支援活動を行う。成年後見人等の受任のほか、スクールソーシャルワーカーや大学等講師を務める。訪問ケア・人材育成事業で地域に根ざした活動を展開。
