独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.9 【独立・開業を選んだ人④】門田博史さん(合同会社オフィスSora彩・そらいろ社会福祉士事務所)の場合
2025/10/31
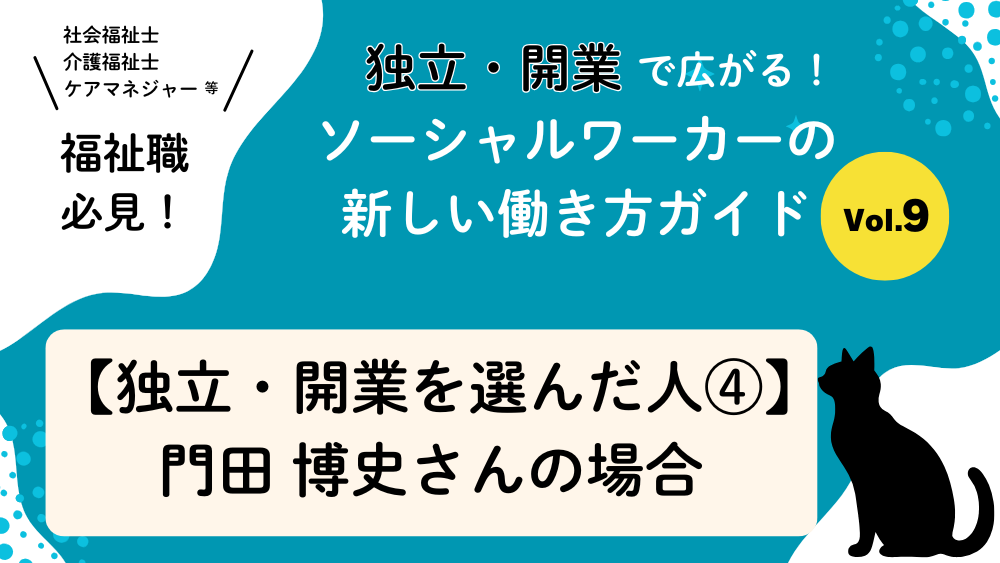
福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!
この連載は、介護や福祉の仕事に熱い想いをもち、これから資格取得を目指している方、あるいはすでに資格をもっていて、さらなるスキルアップを考えている方に向けてお届けします。 今回は、ケアマネジャーからソーシャルワーカーとしての独立・開業の道を選んだ門田さんへのQ&Aを通じて、独立・開業に必要な心構えや視点をお伝えします。
聞き手:松谷 恵子(まつたに社会福祉士事務所所長)
門田さんのプロフィール

合同会社オフィスSora彩・そらいろ社会福祉士事務所代表/社会福祉士、相談支援専門員、主任介護支援専門員、ワークサポートケアマネジャー、AFP認定ファイナンシャルプランナー2級。
障がい児・障がい者から介護を必要する高齢者などの総合的な相談支援活動を行うほか、成年後見等の受任、直近では「介護離職予防のための仕事と介護の両立支援」に関する企業や専門職、一般市民等への支援・研修・広報活動を行っている。
▶ 会社ホームページ
Q1 「独立・開業」の原動力となったものは?
高齢者福祉の仕事に飛び込んで20年、そのうち居宅介護支援事業所の管理者業務が約10年、副業も認めてくれる所属組織には感謝し、不満はありませんでした。
ただ、ケアマネジャーの立場では支えきれない複合的な課題を抱えるケースに何度も直面し、「介護保険サービスだけでは解決できない」「自分には足りない知識が多くある」と忸怩たる思いをすることが多々ありました。たとえば、利用者である高齢者に対する介護保険サービスの調整はできても、高齢者の年金に頼る家族の支援は難しく、家庭全体の経済的課題が解決できないケースなどです。こうした複合的な課題に直面するごとに、「もっと広い世界を知りたい」「もっと自由に仕事をしたい」「もっと自ら経験していきたい」という思いが強くなりました。
そうした思いを実現するには、組織に所属しているなかでは限界があると感じ、独立・開業への道へ進むこととなりました。
Q2 「独立・開業」までのプロセスは?
独立にあたってベースとなる収入が必要です。長らく居宅介護支援事業所の管理者を務めていましたので、まずは居宅介護支援事業所を立ち上げることを考えました。そのためには法人格を取得する必要があるのですが、自身が税務の素人で自らが税務処理を行うことはリスクが高いと考えました。そこで、法人格の取得を含め、最初から税理士と契約することにしました。
また、立ち上げを意識してからは、20年以上福祉分野で活動してきたネットワークをもとに、事業の立ち上げを経験した方、福祉以外の知見を持っている方、自分の選択肢を増やしてくれそうな方などに積極的に話を聞きに行きました。その結果、一層ネットワークが広がり、さまざまな方に支援していただくことができました。
Q3 独立・開業して良かったことは?
組織のルールに縛られるのではなく、すべて自らの意思決定でさまざまなことにチャレンジできることです。組織によるサービス調整に関する縛りもないため、専門職として利用者の最善の利益を追求することができます。
また、独立・開業後、高齢分野や障害分野など複数の分野で活動したため、多様な分野の知識を得て、知識をもとに分野横断的な実践することができました。さらに、会社運営の知見を得る機会に恵まれ、自分自身の物事に対する視野が広がりました。独立・開業したからこそ見える世界があり、その世界を知ることができたことが大きな成長です。
Q4 独立・開業して大変だったことは?
「すべて自らの意思決定でさまざまなことにチャレンジできる」ということは、裏を返せば、最終的に自分が選択し、自らが決めて進めるしかないという強い孤独感にもつながります。また、独立・開業にあたり法務局、年金事務所、市役所など初めて経験する事務手続きが続きました。
わからないことが多く、さらにはわからないことがわかっていないのではないかという恐怖もありました。契約書の作成の仕方、特に法令順守のために必要となる記載などは、一つひとつが初経験のためこれでいいのかととても不安でした。同僚もいないため社内で相談しながらということもできません。自分だけで作成したものが正しいのかわからないなか、つながりのあった専門家に契約書の内容を見てもらったり助言を頂いたりしたことは、心の面でも支えになりました。
経済面については、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、独立・開業後5年間の収支シミュレーションを数パターン作成しました。シミュレーションの結果、事業経営を軌道にのせるため、自らの報酬(給料)は事業所勤めをしていたときの半分以下でスタートしました。独立・開業後、3年間、預貯金を切り崩しながらしのいだので、家計はなかなか大変でした。現在も都度修正しながら、シミュレーションを行っています。
Q5 どんな人におすすめしたい?
独立することで「自由」を得ることが可能になってきます。しかしながら、それは同時に「強い責任」を負うことともなります。それでも「新しいことにチャレンジしたい」「もっと幅広い知識を得たい」という気持ちが強くなってきている方は、ぜひ独立・開業も一つの選択肢として検討されても良いかと思います。
Q6 独立・開業する際におさえて欲しいことは?
独立・開業には、個人事業主と法人の選択があるかと思います。やりたい事業によっては法人化が必須の場合がありますので、事前に調べておくことが必要です。また初めて独立される方は当然ながら独立・開業するうえでの知識が不足している状態にあると思います。書籍で調べたり、知人などに聞いたりしながら、自ら独立・開業の準備を進めるか、最初から専門家に依頼をするかは、リスクの面も考えながら十分な検討が必要です。
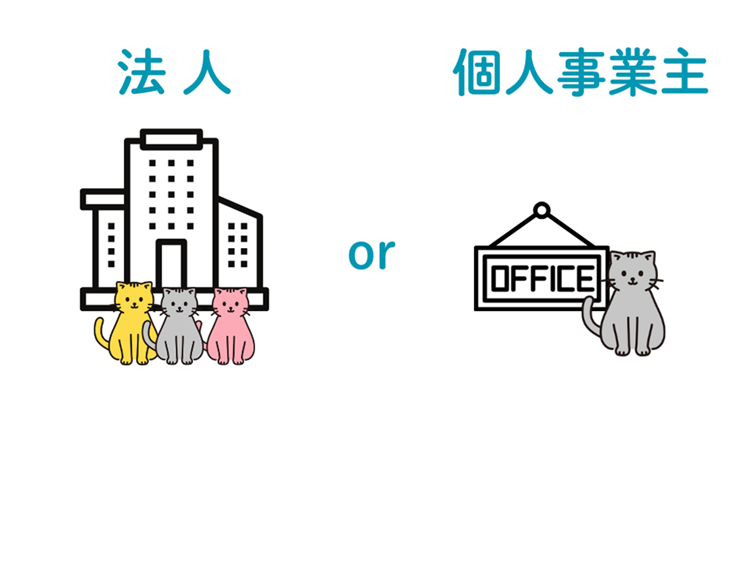
独立・開業後は、さまざまな複合的な課題への支援に関する問い合わせが増えました。そのなかで特に慎重に対応したことは、倫理的課題や利益相反の確認、個人情報の取り扱いです。
たとえば、利益相反においては、自分と縁の深い方や会社と取引のある方などはフラットで中立な立場での支援が難しくなる可能性を考え、公的機関の支援につなげたことがあります。また、個人事業の場合は、複数の社員で検討する機会がないがゆえに、他者チェックが効きにくく、個人情報の取り扱いや倫理的課題への意識が薄くなりかけることもあるかと思います。この辺りの意識を常にもち続けるために、専門職団体が開催する各種研修や勉強会などに定期的に参加し再確認を続けることが重要です。自身で自身を律するだけなく、研修や他者評価等の外部の力も活用しながらリスク管理を行っていく必要があると考えます。
