こどもの居場所部会
2025/09/01
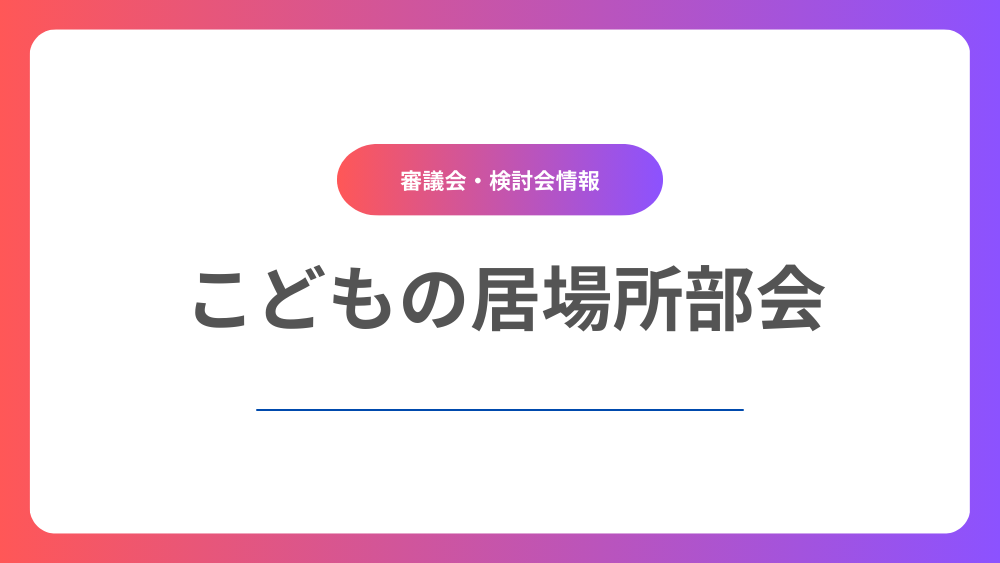
第18回こどもの居場所部会について紹介します。
第18回こどもの居場所部会
2025年8月27日に第18回「こどもの居場所部会」が開催されました。
こどもの居場所部会とは
「こどもの居場所部会」は、こども・若者が、その成長や発達の過程にかかわらず、安心して過ごせる居場所を見つけることができる環境整備を進めるため、具体的な施策について議論することを目的として、令和5年5月にこども家庭庁で第1回目が開催されました。部会での議論は、国が定める「こどもの居場所づくりに関する指針」にも反映されます。
第2期となる令和7年度は、特にコロナ禍を経て孤立しがちな大学生世代を含む、中高生以上のこども・若者への支援を中心に検討を進める方針です。また、議論にあたっては、自治体の「こども計画」への反映や、図書館・公民館など多様な既存資源の活用といった、自治体が実際に取り組みやすい施策であるかという視点が重視されています。
1.こどもの居場所部会(第2期)における議論の進め方
今回の部会では、第2期における議論の進め方について確認が行われました。
主な論点として、以下の3点が挙げられています。
・ユニバーサルな居場所の意義・役割等
ライフステージに応じた居場所の価値や特徴、特にコロナ禍を経て孤立しがちな大学生世代への支援などを検討します。
・切れ目のない支援の工夫
中高生や大学生世代の進学といった環境変化に応じた居場所づくりや、効果的に居場所へつなぐためのコーディネート機能、情報提供の在り方について議論されます。
・オンラインの居場所の意義・役割
オンラインの居場所の実態や特徴を捉え、その目的や対象を整理するとともに、プライバシー保護や情報管理についても検討事項とされています。
これらの議論は、自治体のこども計画への反映や、図書館・公民館といった多様な場の有効活用など、自治体が実施可能であるという視点に留意して進められます。
2.若者の居場所に関するヒアリング
若者の居場所についての実践や知見を深めるため、委員からのヒアリングが行われました。
松田委員からは、「子ども・若者支援と居場所~「非」専門的な場の価値~」をテーマに発表がありました。
その中で、家庭や学校・職場といった「1stプレイス」「2ndプレイス」に左右されない「3rdプレイス」としての居場所の重要性が示されました。居場所にいる大人は、正解を手放して子ども・若者と関わる「意味ある他者」としての役割が求められ、専門的なケアと地域(日常)をつなぐ存在となることが期待されると述べられました。そして、子どもの頃から慣れ親しんだ居場所や、そこでの思い出づくり自体が、孤独・孤立に悩む若者にとって最強の支援となりうると報告されました。
3.こどもの居場所づくりに関する調査研究
こどもの居場所づくりに関する調査研究について、3件の報告がありました。
こどもの居場所づくりの促進のための、他領域との連携を踏まえた
人材配置に関する調査研究
「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配置が各自治体で進んでいない現状が報告されました。この調査研究では、配置が進まない要因を明らかにするとともに、社会教育主事など他領域で既に活躍している人材との連携も視野に入れ、効果的な人材配置の方策を検討することを目的としています。
災害時のこどもの居場所支援に関する調査研究
災害時において、こどもの遊びの機会の確保や心の回復は重要な課題です。この調査研究では、「災害時のこどもの居場所づくり手引き」をもとに、研修等で活用できる分かりやすい資料や動画教材を作成し、児童館職員や自治体職員、災害支援に携わる人々が活用することで、被災したこどもたちの育ちと心の回復が支えられることを目指します。
こどもの居場所の現状を把握するための調査方法についての調査研究
自治体が「こども計画」を策定する際の基礎となる、「こどもの居場所」の実態把握を支援するものです。
多くの自治体では、地域にどのような居場所がどれくらいあるかを把握するための有効な調査手法が確立されていません。この研究では、先進的な自治体などで行われている調査方法を分析し、他の自治体が実情に応じて活用できる調査票やガイドなどを含む「調査パッケージ」を作成・提供することを目的としています。
まとめ
第18回こどもの居場所部会では、第2期における議論の方向性が示され、若者の居場所に関するヒアリングや、人材配置・災害時支援といったテーマでの調査研究の報告が行われました。
今後のスケジュールとしては、第19回(10月頃)、第20回(11月頃)で論点ごとの議論を深め、令和8年2月の第21回で報告書案・中間とりまとめが行われる予定です。
