当事者が教える 認知症の人へのかかわりでやってほしくないこと3選
2025/08/05
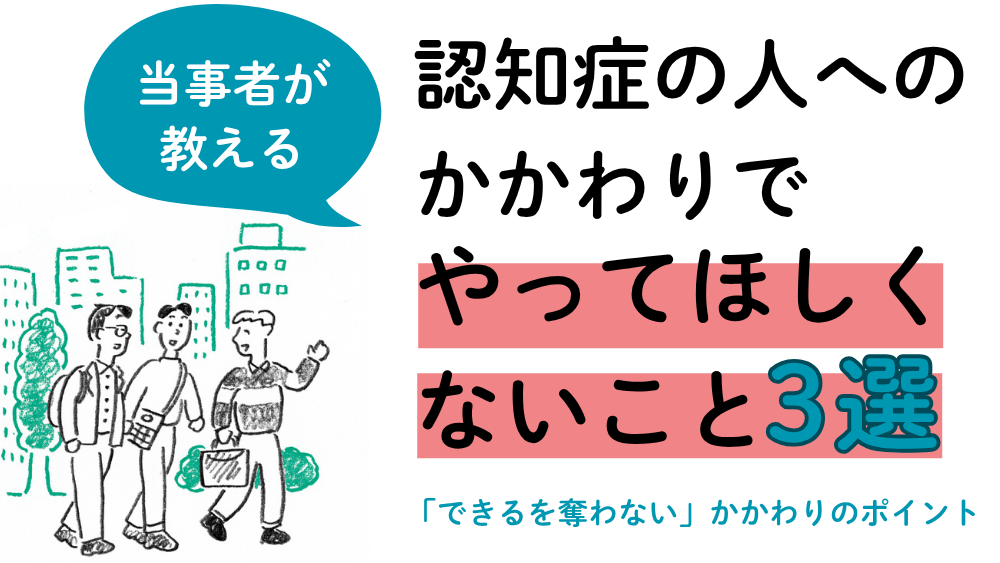
「できるを奪わない」かかわりのポイント
著者紹介
丹野智文(たんの ともふみ)
1974年宮城県生まれ。ネッツトヨタ仙台でトップセールスマンとして活躍中の2013年、若年性アルツハイマー型認知症と診断される。認知症の啓発活動を仕事として現在も同社に勤務。診断後支援としてのピアサポートや全国、海外での講演活動を積極的に行っている。
はじめに
この記事は、「認知症の当事者(本人)」である私が、実体験や800人以上の当事者への聞き取りを通じて痛感した「やってほしくないこと」を、厳選して3つお伝えします。
現場で頑張る専門職の皆さんや、認知症の当事者の家族の方にこそ、当事者の本音と、それぞれの「支援」や「言葉かけ」がどんな影響を与えているかを知ってもらい、ふだんのかかわりを見直してもらえたらと願っています。
1.「先回り」すること
認知症の人へのかかわりで、最も多い困りごとの1つが「先回り」です。
たとえば「外出先で失敗しないように」と財布や携帯電話を預かったり、「危ないから」と包丁を使わせずに何でも家族や介護職員がやってしまう。この“先回り”が、実は当事者の自信・やる気・自立心を大きく奪うことになります。
実際、診断直後から「できること」が急に減ることはほとんどありません。むしろ周囲の「心配」や「良かれと思って」が、本人に“何もできない自分”という刷り込みをしてしまうのです。
その結果、認知症の当事者は家族や支援者がいないと何も決められないという、「依存」の状態に―――。
依存が進むと、“何も決めたくない・動きたくない”状態になり、家族にも負担が増える「負の連鎖」が生じます。
「やってあげたほうが本人も楽」と思うかもしれませんが、時間がかかったり失敗したりしても「本人が自分でチャレンジできる」環境こそが力になります。“失敗することを奪わない”こと、そして「家族や支援者の安心」ではなく「本人のできる・やりたい」を中心にしてほしいのです。

2.当事者の力を信じないこと
多くの専門職が、「認知症の人は意思決定ができない」「何を考えているかわからない」と考えがちです。しかし、認知症当事者も、自分のことを自分で決めたい、という思いがあります。
ケアの現場では、意思決定の場に本人がいなかったり、サービス利用の話し合いでも「家族と支援者だけで決める」ケースが今も少なくありません。
「できること」に注目し、本人の力を信じてかかわることで、当事者に自信が生まれます。
実際、ピアサポートで本人同士が話すと、多くの方が本音や悩み・希望を語りだします。
関係性や信頼を築ければ、当事者は自分の言葉で“やりたいこと”や“不安”を自然と語れるのです。
当事者の「失敗する権利」を保障し、「困ったときに“助けて”と言える関係」を築きましょう。
認知症の症状によりできないことや難しいこともありますが、周囲が「できない」と決めつけたり、最初から何でもサポートする姿勢は、本人の自信を喪失させてしまいます。
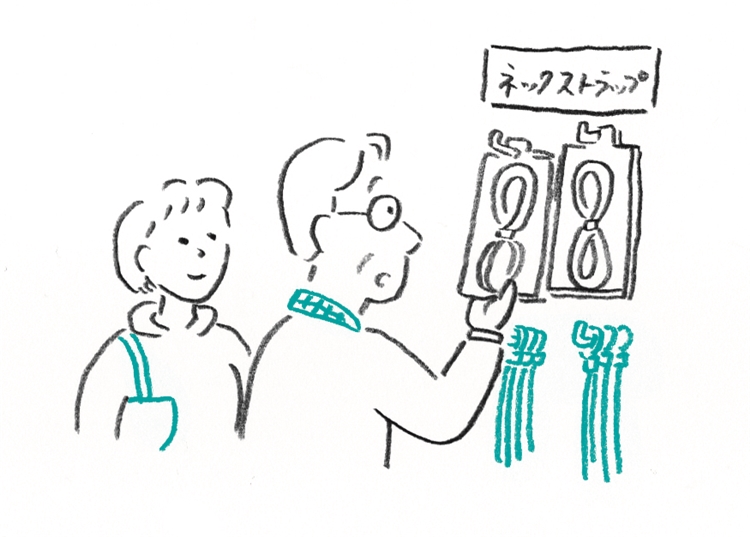
3.自分が認知症になったとき やってほしくないことをすること
最後に強調したいのは、「その支援やケアは、自分が認知症になったとき本当にやってほしいことか?」という視点です。
たとえば、デイサービスでも折り紙や塗り絵のレクリエーションが“当たり前”だったり、携帯が必需品の現代でも、「携帯持ち込み禁止・フリーWi-Fi なしの施設」など、本人目線とはギャップのあるケアの現場が多いのです。
さらに、「安心・安全」の名のもとに、GPS端末やQRコードを本人の意思と関係なく靴や服に付けられるなど、「家族や施設・地域の安心」ばかりが優先されていないか?と考えてほしいのです。
認知症になっても「やりたいこと」や「好きなこと」、「自分の行動を選ぶ権利」を変わらずもっています。
自分が認知症になって支援される立場になったとき、どんなふうにかかわってもらいたいかを、常に問い直してみてください。

最後に
「何かをやってあげる」よりも、「本人がやろうとするとき・失敗したとき・困ったとき、そっと応援し、必要なときにだけ手を貸す」――これこそが、認知症当事者が望む最大の支援です。
「本人の声を聴く」「一緒に考える」ことから、ぜひ始めてみてください。
もっと知りたい方に! おすすめ書籍
本記事の内容は、下記書籍の内容をもとに編集・作成しております。
