今さら人に聞けない! 「自立支援」ってなんだろう?
2025/05/02
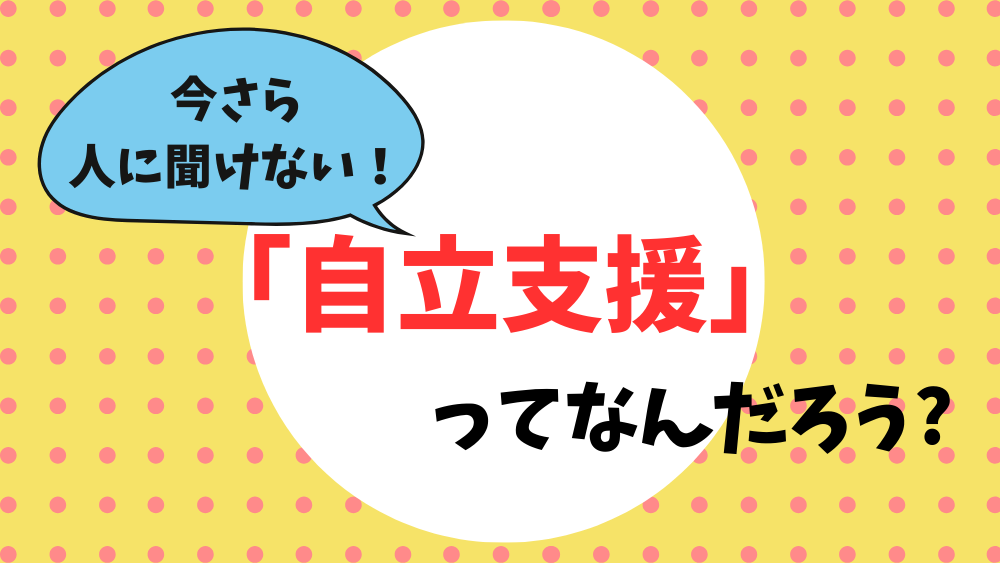
「自立支援」って当たり前に言うけど、そもそも自立支援って何!?
利用者が望む生活を実現するために、日々、「自立支援」に取り組んでいる介護職のみなさん。よかれと思って取り組んでいるのに、利用者の生活は、どんどん自立から遠ざかっていく…ということはありませんか? 心当たりがあれば、それは「思い込みの自立支援」かもしれません。
…というか、そもそも自立支援って何なのでしょう。当たり前すぎて、今さら人に聞きづらい「自立支援」について、事例をもとに考えてみましょう。
1.たとえばこんな「思い込み自立支援」~事例1~
Dさん(70歳代)は、軽度の認知症と下肢筋力の低下があります。自宅では、手すりを使ったり伝い歩きをしたりと、ゆっくりではあるものの腰を伸ばした姿勢で、ふらつくこともなく一人で歩くことができています。
しかし、今後への不安から、Dさんの家族は機能低下予防のため、週に3回、1日7時間の通所介護サービスの利用を申し込みました。介護事業所では、歩くことに重点を置き、Dさんの「有する能力」を維持するため、たくさん歩いてもらっています。ただ、介護事業所は伝い歩きができる環境ではなかったため、職員が Dさんの両手を引いて歩いています。
サービス開始から2か月ほどして、Dさんは自宅で手すりを使っているのにふらついたり、トイレ内で転倒したりすることが多くなり、介護事業所のトイレでも転倒することが増えてきました。そのため、介護事業所では下肢機能の低下と判断し、これまでの歩行練習から、マシーンを使った下肢筋力の強化を始めました。しかし、変化はほぼ見られませんでした。
◆ココを考える!
なぜ、介護サービスを使い始めてから、Dさんの生活に支障が出始めたのか
◆ヒント
手引き歩行
◆ほんとうの自立支援にするための見直しポイント
・手引き歩行をすると、上半身が前のめりになります。手引き歩行を続けることによって、Dさんは誤った姿勢で歩くことになります。その結果、バランスを取りながら歩くことが難しくなくなったのではないでしょうか。
・Dさんは、手引き歩行で、前方にしか歩いていません。しかし、方向転換やトイレ動作のときは、足を後ろに引いたり、振り返ったりする動作も必要です。
・介護職は、生活のなかでどのような動きをしているかをしっかり見直す必要があります。
2.たとえばこんな「思い込み自立支援」~事例2~
アルツハイマー型認知症のNさん(80歳代、要介護1)は、息子家族と同居しています。もともと家事が好きな人で、息子夫婦が留守の間も家事が自分でできていたため、息子夫婦は助かると喜んでいました。
息子夫婦は、認知症の進行予防のために介護事業所の利用をNさんに勧め、通所介護を利用することになりました。通所介護では、Nさんが好きな家事を中心に、できることをやってもらっています。家族との連絡帳で「○○を率先してやっていただけています。休憩も少なく毎回職員並みに動かれています」と報告をしていましたが、1か月しない頃から、家族から「母は本当に○○をしているのでしょうか。家では何もやらず、横になっていることが増えたのですが…」と言われるようになりました。
それからも、Nさんは通所介護ではいつもと変わらない生活をしていましたが、自宅ではほとんど寝ているようになり、昼夜が逆転して家族の負担は増え、疲弊しきっています。
◆ココを考える!
なぜ、Nさんは自宅では何もやらず、横になっていることが増えたのか
◆ヒント
「休憩も少なく毎回職員並みに動かれています」
◆ほんとうの自立支援にするための見直しポイント
・いくら好きな家事でも、休憩も少なく職員並みに動いていれば、当然疲れて家ではゆっくりしたいと思うのが普通ではないでしょうか
・Eさんには自宅に帰ってからの生活があります。「できるからやってもらう」ではなく、自宅に帰っても好きな家事ができるように支援することが大切です。
・家族の生活も踏まえたかかわりが大切です。家族が介護に疲れてしまうと、Nさんが自宅で生活を続けることが難しくなっていくことも考えられます。そうならないよう、適切な対応をしなければなりません。
3.たとえばこんな「思い込み自立支援」~事例3~
自分のタイミングでトイレに行くことができるKさん(90歳代)。排泄動作には問題がないと思われていますが、目が悪く眼鏡の度数も合っていないため、便器の淵が見えにくいらしく、周りに尿を飛ばしてしまうことが多々あります。そのため、次にトイレを使う人から文句を言われないように、職員はKさんがトイレから出てくると待ち構えていたかのように「清掃中」の札を出してトイレの確認、掃除を急いで行っています。
しばらくすると、Kさんはトイレに間に合わないことが増えてきました。よく観察してみると、自分からトイレに行く回数が減っています。そこで、職員は、Kさんが尿意を感じにくくなったのではないかと思い、Kさんにリハビリパンツとパットを使用してもらうようにしたところ、自分でトイレに行くことがなくなってしまいました。
◆ココを考える!
なぜ、Kさんは自分でトイレに行くことがなくなったのか
◆ヒント
トイレの確認・掃除、リハビリパンツとパット
◆ほんとうの自立支援にするための見直しポイント
・Kさんの次にトイレを使う人から文句を言われないように、Kさんがトイレから出てくるとすぐに掃除をしていますが、それを見たKさんはどう思うか考えてみましょう。
・「清掃中」の札は、Kさんがトイレを汚したと周囲にアピールしているようなものです。Kさん自身がトイレに行く回数を減らしている可能性もあります
・眼鏡のせいで便器の淵が見えないのがわかっていたのなら、眼鏡を調整をする、便器周辺の床の色を変えるなど、介護職としてやれることがあったのではないでしょうか。
4.「自立支援」のポイント
事例を読んで、違和感を覚えた人もいるかもしれません。自分たちのしていることが「自立支援」なのか気になったときは、次のポイントを参考に振り返ってみましょう。
◆自立支援のポイント
1.その人に合ったかかわり方をする
認知症、片麻痺、耳が聞こえにくい…など、身体の状態は人によって異なります。それなのに、かかわり方はみんな一律で同じ、っていうのはおかしいですよね。その人に合ったかかわり方をしましょう。
2.利用者の力を適切に発揮できるようなかかわり方をする
力を「適切に」発揮することが大切です。「最大限に発揮する」と考える人もいるのですが、力を最大限に発揮しつづけるのは、誰だって大変です。「力を最大限に発揮して、毎日30回階段の上り下りをする」という目標を立てられたらどうしますか? 膝を痛める未来しか見えません…
3.必ずしも本人の意向を尊重することがベストではない
毎日利用者と接していれば、利用者の意向は尊重したいと思ってしまうもの。しかし、そこに落とし穴があります。大切なのは、利用者がこれからも生活を続けていくこと。将来そうなることがわかっていたら、妥協したのに…という場合もあります。
今の意向を尊重したら、将来どうなることが予想されるか(いい面も悪い面も)を踏まえて、利用者、家族、職員で考えることが大切です。
4.寝たきり・全介助の人にも「有する能力」はある!
一般的に「寝たきり」「全介護者」と言われる人も、極端なことを言えば、呼吸はできます。ただ、ラクに呼吸ができる姿勢をとることが難しいのです。だから、介護職が適切な姿勢に整えることができれば、呼吸がラクになります。自分でできている部分には、その能力の維持につながるためのケアを、できづらい部分にはできやすいように関わっていく必要があります。そのために、介護職には正しい知識と介護技術が求められるのです。
もっと知りたい方に! おすすめ書籍
もっと自立支援について考えたい!という方は、ぜひ、下記書籍をご参照ください。
「自立支援」をテーマに、著者の山出貴宏さんと、山出さんに大きな影響を与えた田中義行さんに対談をしてもらいました。その内容は こちら からご覧いただけます!
