知ってるつもりの認知症ケア 第5回 非言語コミュニケーションは「仕分け」が肝心?
2025/04/18
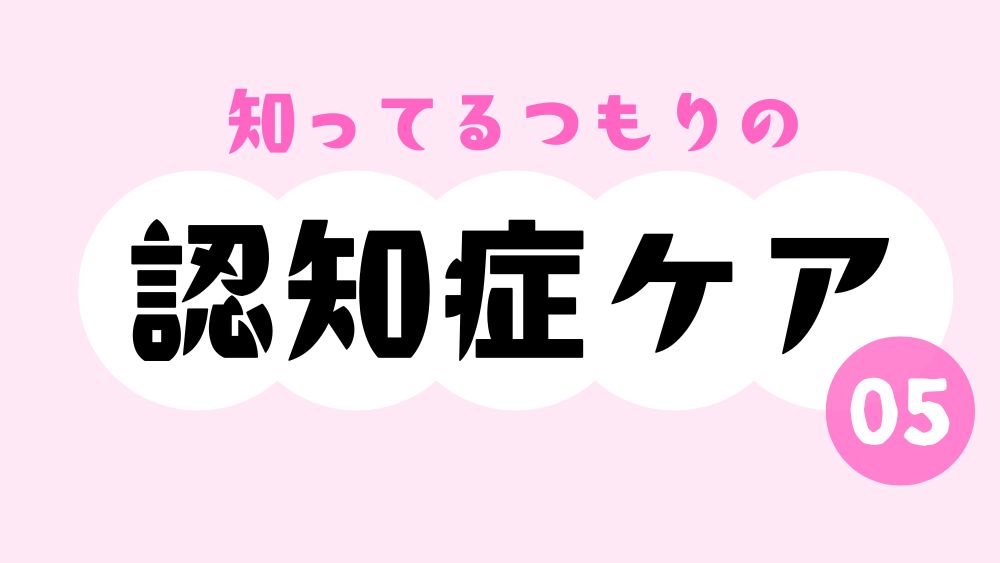
川畑智

認知症の人に接するときには「認知症の人の見ている世界」を正しく理解することが大切です。それによって適切で質の高いケアを提供でき、利用者は認知症になっても安心して生活することができます。
……とはいっても、さまざまな仕事をこなす日々の業務のなかでは、理想どおりのケアを行うことは一苦労です。
この連載では、認知症ケアの第一人者である理学療法士の川畑智さんのもとに、悩み多き介護職の方々が訪れ、ともに「現場のリアルな困りごとを理想に近づけるためのヒント」を模索していきます。
理想論ではなく、認知症ケアのリアルなつまずきにスポットを当ててみたいと思います。
Bさん : 川畑さん、はじめまして!
川畑 : どうもどうも。
Bさん : 実は相談がありまして。失語の症状がある認知症の利用者さんとのコミュニケーションについて、いろいろお話をうかがいたいんです。
川畑 : 失語のある方とかかわるのは、なかなか難しいですよね。今、どんな状況ですか?
Bさん : 返事が「はい」「いいえ」しか返ってこないことが多くて、こちらが尋ねたことと噛み合わなくなってしまうんです。
川畑 : なるほど。現場でも、そんなやりとりって多いですよね。「ご飯食べましたか?」と聞いたら「はい」。「食べてませんか?」と聞いても「はい」。どっちなんだろう? と迷ってしまうとか。
Bさん : まさにそんな感じで、話がなかなか進まないんです。会話になっているようで、実際は意思を汲み取るのが大変で……。すべて「はい」になるのは、どうしてなんでしょうか?
川畑 : コミュニケーションって、私たちが思う以上に脳のいろんな部分を使っているんですよ。たとえば耳の上あたりにある脳の側頭葉が「聴理解」を担当しています。そこがうまくはたらかないと、聞こえてはいても意味をとるのが難しくなる。英語のリスニングみたいに時間かければ慣れる場合もあるけど、認知症になると、その「リスニング」が苦手になりやすい。
Bさん : 私も英語のリスニングは苦手ですけど……。ただ、認知症がある方は、まず「聞く」こと自体が難しいわけですね。そこにコミュニケーションの問題が重なってくるわけですか?
川畑 : そう。リスニングや発話自体が厳しくなってくるんです。で、私たちって頭の中に5万語くらいの単語を持っていると言われています。まさに「ごまんとある」状態なわけですね。
Bさん : へー、そうなんですね。
川畑 : もっとわかりやすく言うと小学生向けの国語辞書が6万語くらいなので、辞書1冊分程度の単語が私たちの頭に入っていると言えますね。ただ、認知症が進行すると、だんだんそこから単語が引き出しにくくなるんです。その結果として「あれ」「これ」「それ」が増えていき、「ほら、あの『あれ』がこうなって……わかるでしょ?」なんて感じですね。
Bさん : それが最終的には「はい」「いいえ」だけになっちゃうってことですね。
川畑 : ですね。施設だったら呻き声とか喚き声、ぶつぶつ言っている声、ワンワンという擬音なんかが聞こえてくることもあるんじゃないでしょうか。これも言葉を話そうとしているのに、うまく構音できない状態と考えられます。
Bさん : 頭の中にある単語を引き出す力が制限されてしまっている、ということですかね。
川畑 : そう考えてもらってよいと思います。「はい」「いいえ」の状態からさらに進むと、1語だけになる。どちらが残りやすいかというと……
Bさん : それが「はい」なんですね!
川畑 : そうです。何を聞いても「はい」「はい」と応じてしまう。認知症が進んで失語の症状が表れることで、言葉のやりとりだけではだんだん難しくなるわけです。
Bさん : じゃあ、どうすればいいんでしょう?
川畑 : コミュニケーションは「受信と送信」が成立しているかどうかです。声を使ったコミュニケーションがうまくいかなくなったら、非言語的コミュニケーション、つまり表情やしぐさ、ジェスチャー、タッチなどがとても大事になってきます。実際、現場でも声かけだけじゃなく、利用者さんに近づいて肩をそっと触れたりすることがありますよね。今、私が車いすに座っているとして、ちょっと呼びかけてもらえますか?
Bさん : (マスクを外して)「川畑さーん」……こんな感じですか?
川畑 : ありがとうございます。今、声をかける前にマスクを外しましたね。これが意外に、すごく大事なことなんです。コロナ禍を経てマスクが当たり前になりましたが、以前は「化粧するのが面倒」「二日酔いを隠さなきゃ」なんて理由で着けていた程度だったかもしれません。今も衛生面で欠かせませんが、マスクで表情が隠れてしまうと、相手は「この人は敵か味方か」を判断しにくい。
Bさん : うーん。そうですね。
川畑 : だから、表情を見せるというのがとても重要なんです。優しい笑顔なのか、怖い顔なのか。それだけでも相手の安心感や拒否感が違いますよね。
Bさん : もし相手が怖いと思ってしまったら、それだけで溝ができちゃいますよね。
川畑 : まさに。怖い顔で「トイレに行きましょう」と言われたら嫌だけど、「おしっこ行きましょうか?」と優しい顔で誘われると応じやすいですよね。笑顔とセットで「お茶でも飲みません? 私も一緒にいただきたいんです」と言えば共感が生まれるわけです。
Bさん : でも、現場では「マスクを外しちゃダメじゃない?」「マスクの意味がないじゃない」って言われそうですし、感染リスクもゼロではなさそうで……。
川畑 : たしかにありそうです。もちろん、外した状態でベラベラしゃべるのはよくないですが、声をかけたあと、黙ったままマスクを下げて表情を見せるだけなら、飛沫感染のリスクはほとんどありません。このちょっとした気遣いがものすごく大事なんです。
Bさん : なるほど。でも、そんなこと全員にやってたら、今度は「時間がいくらあっても足りないよ」と言われるかもしれません。
川畑 : それもありそうですね。そこは「仕分け」が大事。「この利用者さんには顔を見せないと伝わらない」「あの利用者さんは言葉だけでわかってもらえる」みたいな判断をすることが大事なわけですね。「言葉が伝わりにくいから、安心してもらうためにマスクを下げよう」「この人はしっかり聞き取れるから、わざわざ口元見せなくても、眉毛の動きだけでいいかな」なんてふうに見極めるわけです。
Bさん : そうすると、利用者を見ることが大事になってきますね。とても勉強になりました。しっかり「仕分け」ができていれば、自分たちの仕事も楽になりますね。ほかにも現場で使えるコミュニケーションのヒントはありますか?
川畑 : もちろんありますよ。ただ、それは次回にお話ししましょうか。
Bさん : わかりました! よろしくお願いします。
川畑智さんのプロフィール
理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表
1979年宮崎県生。病院や施設で急性期・回復期・維持期のリハビリに従事し、水俣病被害地域における介護予防事業(環境省事業)や、熊本県認知症予防モデル事業プログラムの開発を行う。2015年に株式会社Re学を設立。熊本県を拠点に病院・施設・地域における認知症予防や認知症ケア・地域づくりの実践に取り組み、県内9つの市町村で「脳いきいき事業」を展開。ほかに脳活性化ツールとして、一般社団法人日本パズル協会の特別顧問に就任し、川畑式頭リハビリパズルとして木製パズルやペンシルパズルも販売。年間200回を超える講演活動のほか、メディアにも多数出演。著作に『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』シリーズなど。
