おすすめブックス
-
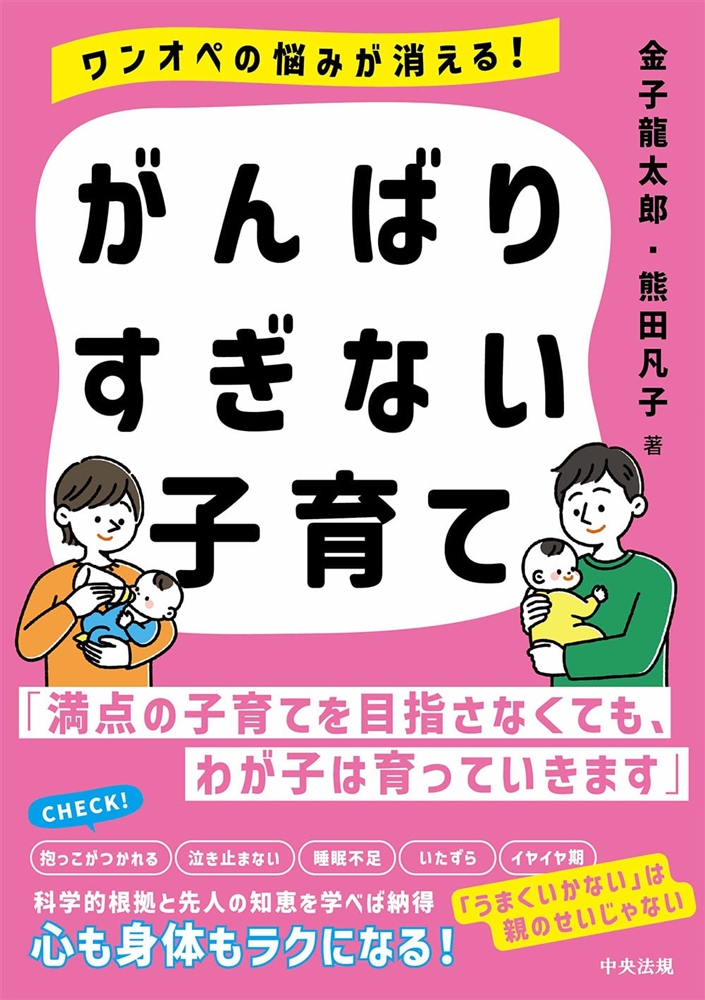
身体や精神の疲労、子どもの発達、教育・しつけなど、よくある育児の悩みに対して育児学の専門家がアドバイスする。一人で抱え込まず、家族や周囲と協力して育児をするヒントが満載で、読めば育児の不安感や負担感が軽くなる。
ワンオペの悩みが消える! がんばりすぎない子育て
-
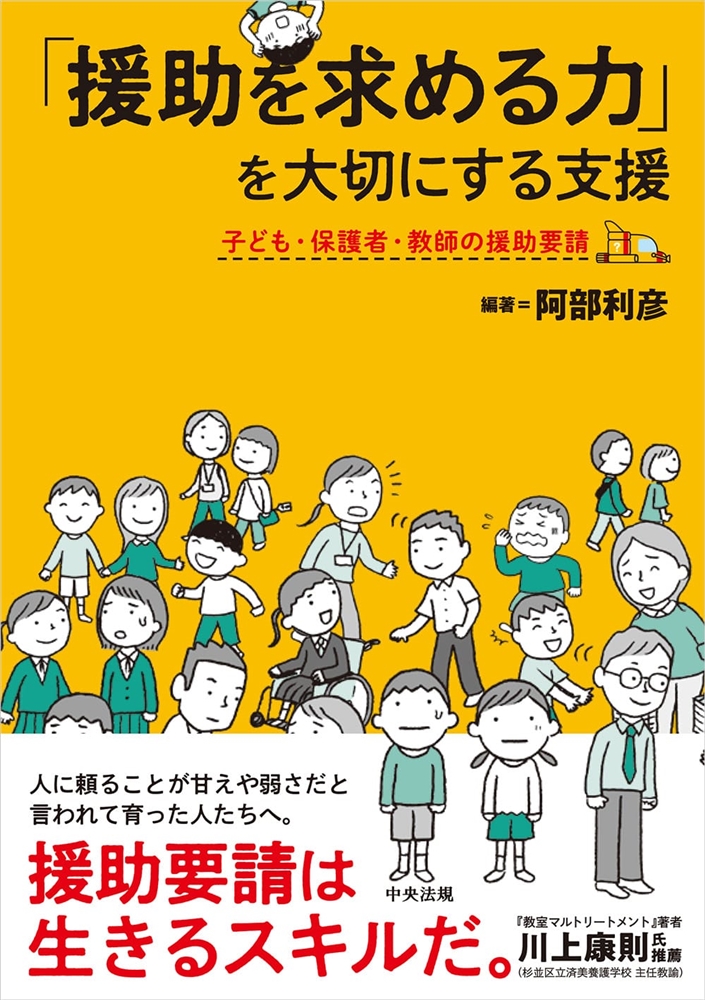
発達に特性がある子をはじめ、子どもたちはなかなか「教えて」「手伝って」と言うことができない。本書では、子どもたちが「人に援助を求めてうまくいく経験」を積み重ね、自立・社会参加につながるよう、教員の働きかけのコツやクラスづくりのポイント等をわかりやすく解説する。
「援助を求める力」を大切にする支援
-

園と保護者のコミュニケーションツールである連絡帳について、年齢別・場面別にそのまま使える記入例を掲載。子どもの姿や育ちを伝えるポイントや家庭からの記入に対する返信のポイントが示されているので、連絡帳を通して保護者との信頼関係を育むことができる。
手書きでも!アプリでも! 年齢別・場面別だからすらすら書ける 保育の連絡帳文例集 たっぷり150
-
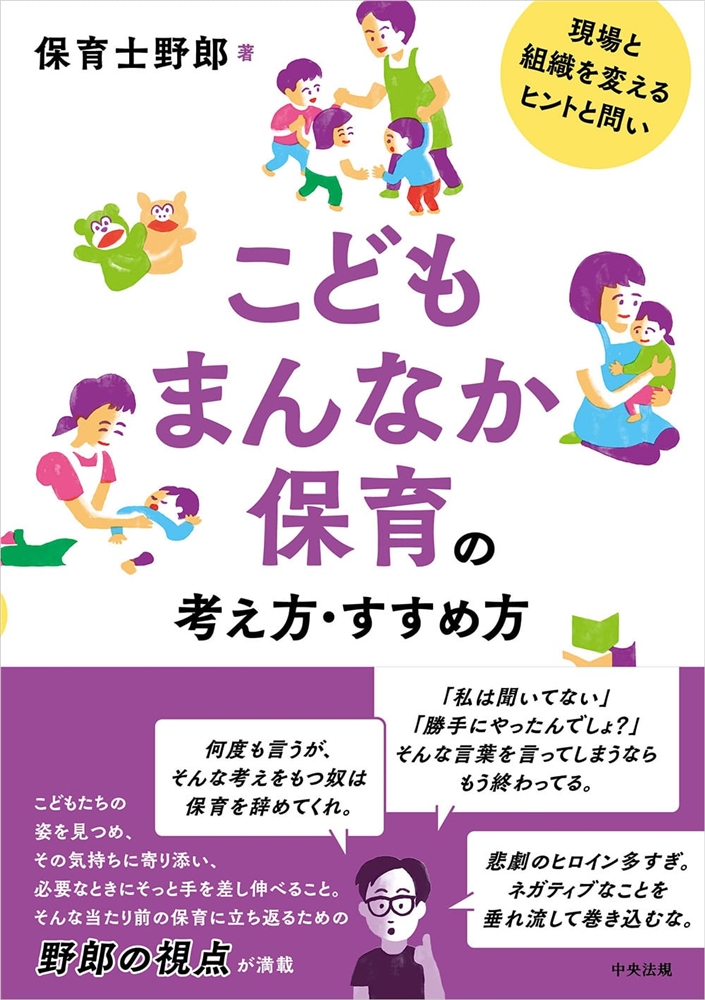
こども家庭庁の掲げる「こどもまんなか」社会の実現に向けた、保育の心得から実践にあたっての具体的なヒントなど、現場で迷ったとき、悩んだときに役に立つ視点が満載。こどもまんなか保育の実現への道を、新進気鋭の保育者・保育士野郎が提案する。
『こどもまんなか」保育の考え方・すすめ方』
-
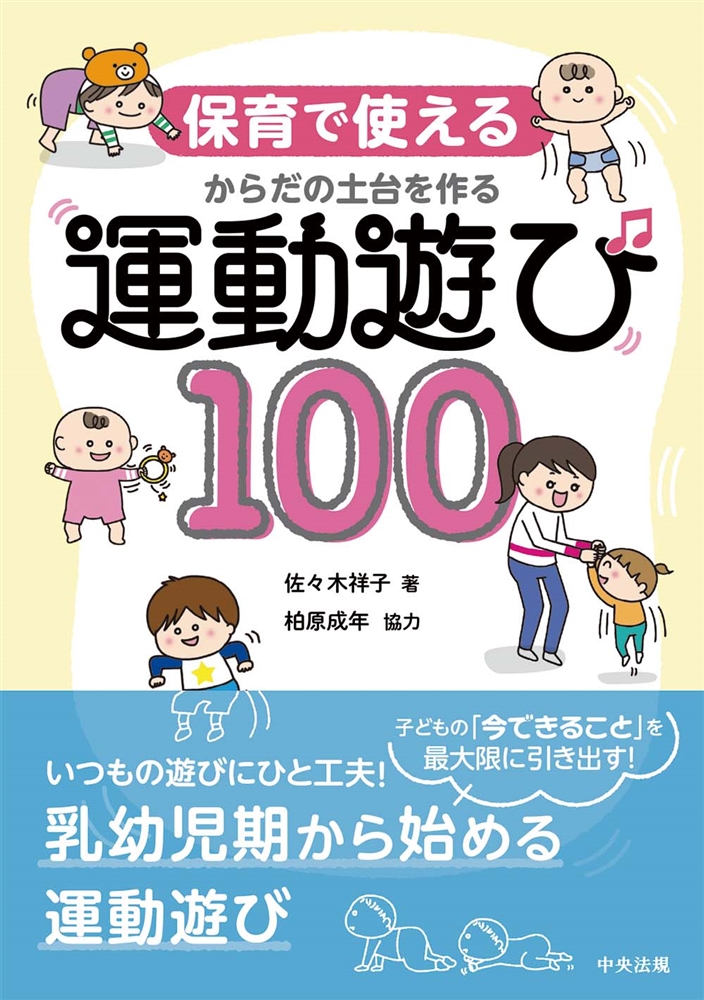
子どもの豊かな成長には、乳幼児期からの「動けるからだ」の土台づくりが重要である。本書では、保育現場で行われている運動遊びにひと工夫を加えた、身体機能を向上させる100の遊びを紹介。子どもの発達や観察ポイントなども解説し、遊びを通した身体づくりを提案する。
保育で使える からだの土台を作る運動遊び100
-
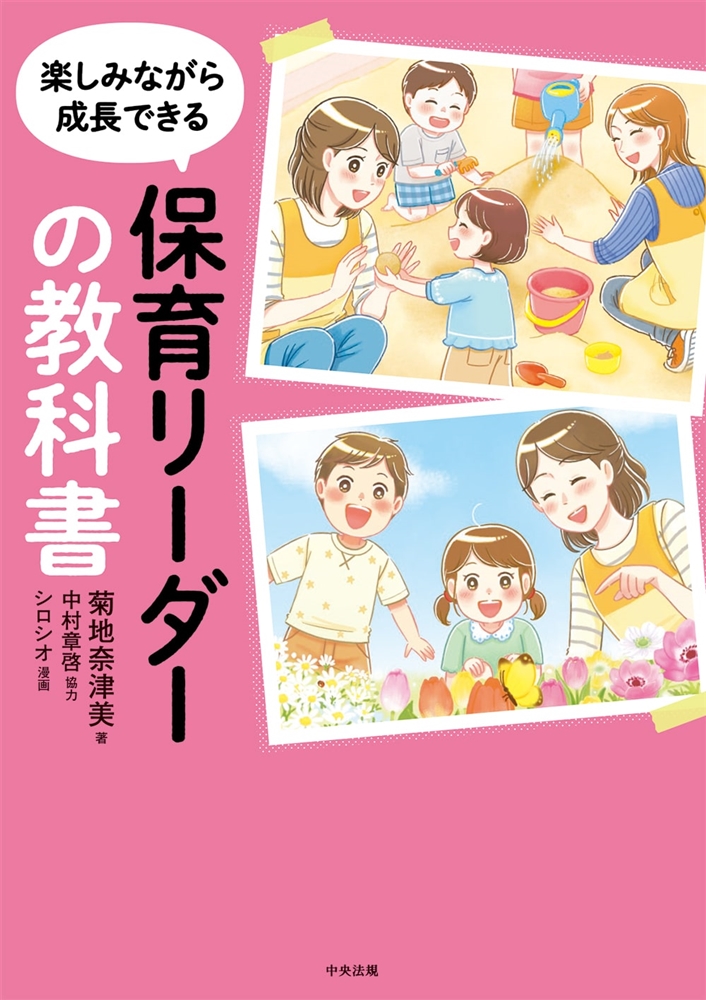
ミドルリーダーの業務や考え方を、イラストやマンガでわかりやすく伝授。新任リーダー・絢夏のストーリーを通じ、新人育成から保育実践、保護者対応、行事の進め方まで、さまざまな場面でリーダーがぶつかる壁や困りごとを解決する。リーダー業務に悩む保育者のための一冊。
保育リーダーの教科書 楽しみながら成長できる
-
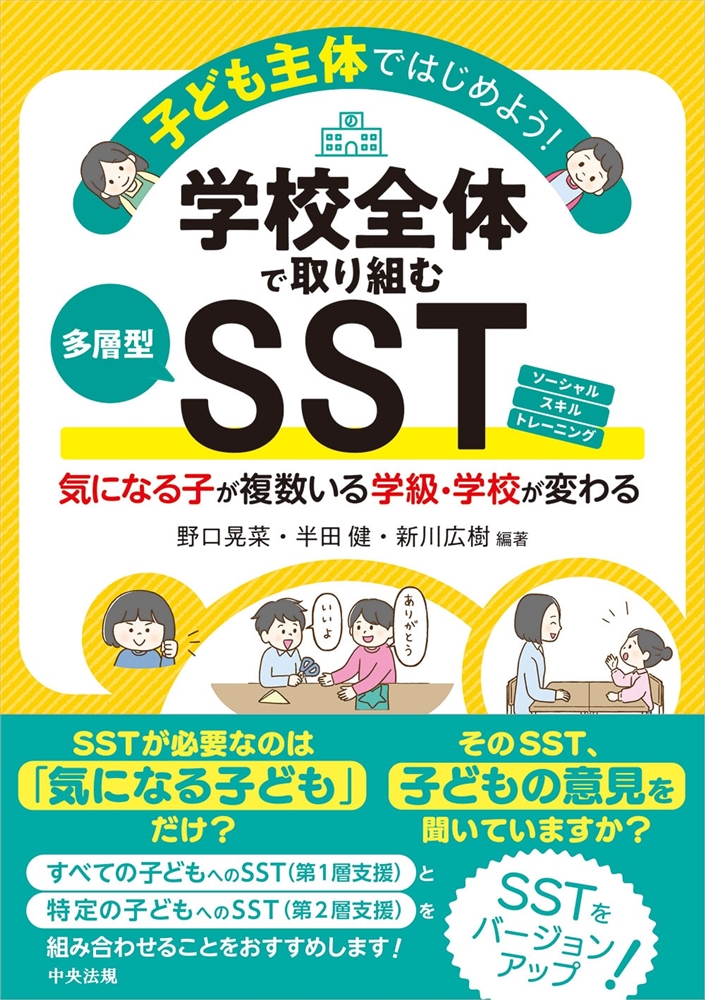
支援を要する子どもが増えている学校では学校全体を対象とするSSTの導入が有効。周囲に合わせて本人を変えるSSTではなく、本人の気持ちや意思を尊重して行うSSTの実践、多層型支援(第1層=すべての子ども、第2層=個別ニーズのある子ども)の導入方法を具体的に紹介。
子ども主体ではじめよう!学校全体で取り組む多層型SST 気になる子が複数いる学級・学校が変わる
-
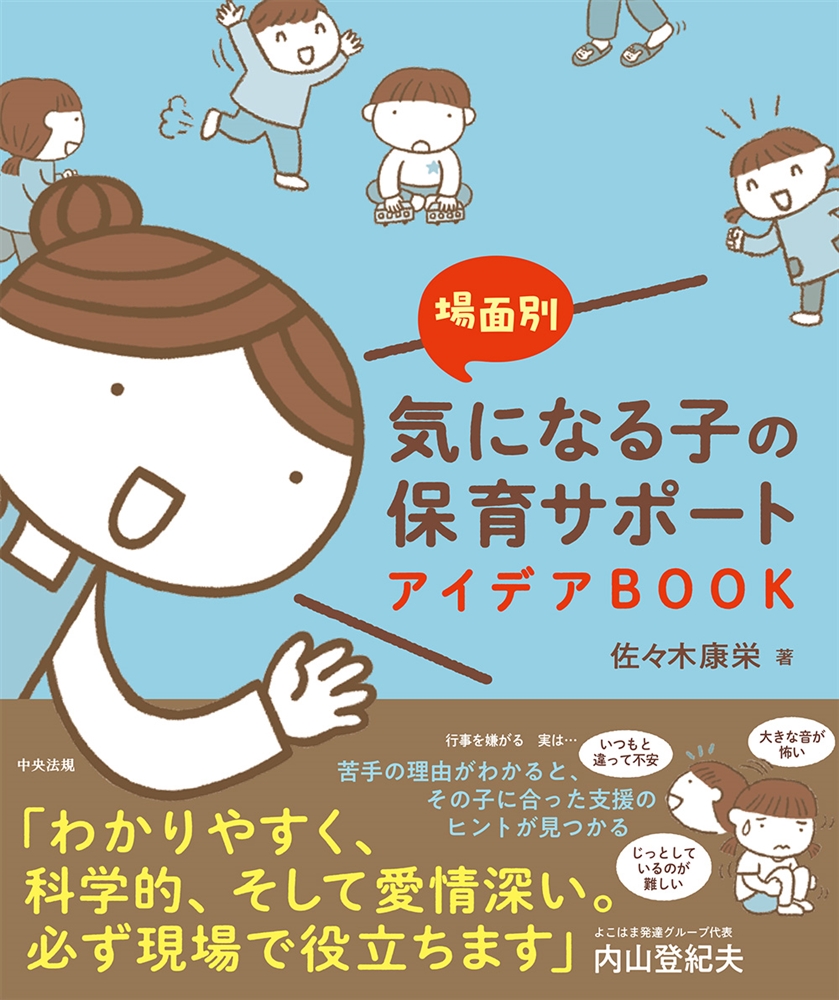
保育現場でよく見られる「気になる子」が苦手な場面について、その背景を探り、理由ごとに発達特性を解説し、支援・対応のヒントを提案。環境を見直すことで、できないことや難しいことが多く、自信をなくしがちな子どもも安心して園生活を送れるようになる。
場面別 気になる子の保育サポートアイデアBOOK
