障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(障害者)
2025/06/27
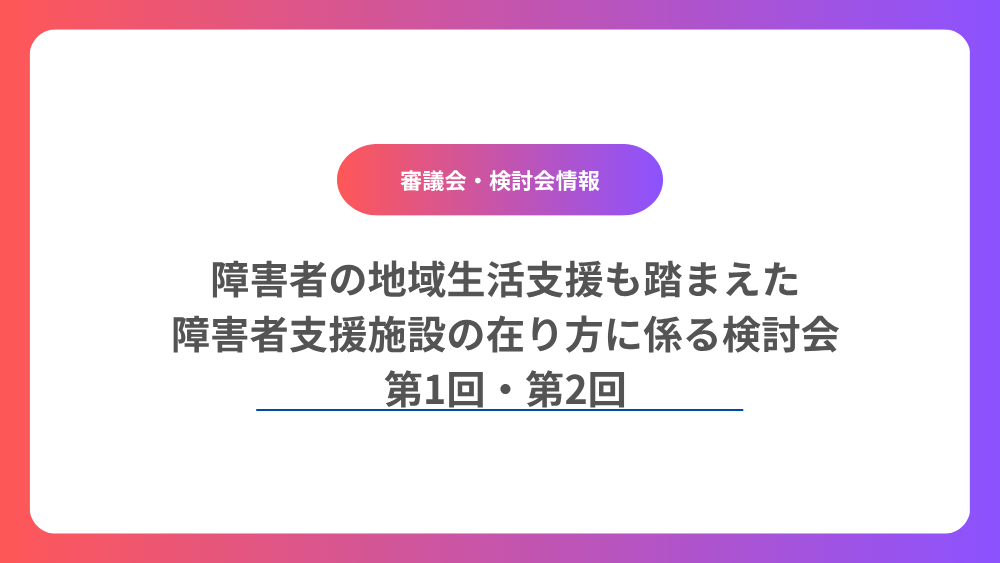
令和7年5月26日(月)に、第1回の「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」が開催され、6月25日(水)には第2回の検討会が開催されています。
「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」の開催状況や議事録・資料等は、
厚生労働省のホームページ
でご確認ください。
これまでの経緯等
国は、2014年の障害者権利条約批准を機に、障害者支援施設の地域移行を加速させてきました。
2022(令和4)年の社会保障審議会障害者部会の報告書は「障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実」「地域移行のさらなる推進」「障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等」「障害者支援施設と地域の関わり」の4点を今後の取組として挙げました。
そうしたなか、同年9月の国連障害者権利委員会による対日審査の総括所見では、脱施設化・自立生活支援の勧告を受け、同月
「脱施設化ガイドライン」(緊急時を含む脱施設化に関するガイドライン)(リンク先:DPI日本会議)
も公表されました。
その後、2023(令和5)年度策定の第7期障害福祉計画等の基本指針では、2024(令和6)〜26(令和8)年度に入所者の6%以上を地域へ移し、2028(令和10)年度末までに入所者数を5%以上削減する数値目標を掲げました。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、地域移行意向確認担当者の選任・指針策定を義務化や地域移行に向けた動機付け支援の加算の創設など、新たなインセンティブを導入しました。
併せて、国は、施設の役割を再定義する調査研究を進めており、当事者や関係団体の声を踏まえた見直しに着手しています。
検討会の役割
本検討会は、これまでの経緯等を踏まえて、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を行うものとされています。
開催要項の「1.趣旨」において、「障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められている。」と示されており、 並行して行われていく
「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」
(6月25日に第47回を開催)との関係性も強調されています。
障害者支援施設の在り方を問う検討会のスタート
第1回の検討会では、曽根直樹氏(日本社会事業大学社会事業研究所客員教授)が座長代理として進行を務めました。
事務局である厚生労働省(社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課)により、①障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿、②今後の障害福祉計画の目標(施設入所者数、地域移行数等)の基本的方向性の2つが、本検討会の大きな論点として示され、本検討会で障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定につなげていくことが説明されています。
曽根座長代理から、知的障害の当事者の方が初めて委員として参画した厚生労働省の公的な会議であり、非常に画期的な会議である旨の発言があり、その後、各構成員から、論点に沿った意見書に基づいて意見表明が行われました。
第1回から第2回の検討会へ
第2回の検討会では、小澤温氏(長野大学社会福祉学部教授)が座長として進行を務めました。
事務局から第1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理が示された後、各構成員から、①障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿、②今後の障害福祉計画の目標(施設入所者数、地域移行数等)の基本的方向性の2つの論点に沿って、意見・質疑が出されました。
②の論点に関しては、社会保障審議会障害者部会での障害福祉計画の基本指針の検討との関係も踏まえて整理することとされ、各構成員からの提案意見を考慮して、とりまとめに向けた準備がなされていくこととされています。
