第202回社会保障審議会医療保険部会
2025/11/11
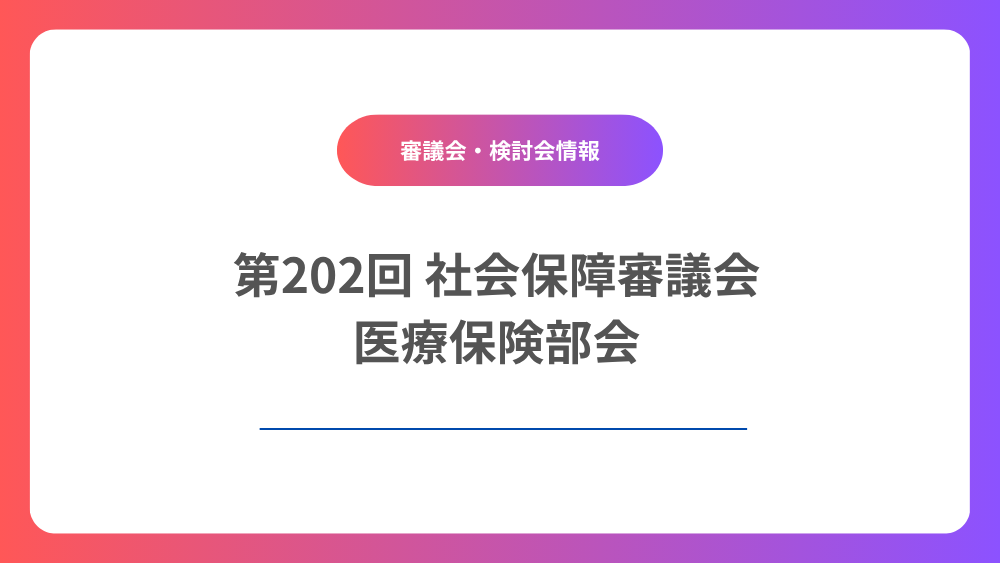
第202回社会保障審議会医療保険部会について紹介します。
第202回社会保障審議会医療保険部会
2025年11月6日(木)、第202回社会保障審議会医療保険部会が開催されました。
社会保障審議会医療保険部会とは
社会保障審議会医療保険部会とは、社会保障審議会の下に置かれた部会の一つです。医療保険制度の諸課題や対応策について議論、意見交換が行われます。
第202回の資料等は、厚生労働省のHPにて公表されています。
今回の部会での2つの論点
今回の医療保険部会では、次の2点が議題として挙げられました。
1.高額療養費制度について
高額療養費制度とは、一月の内に支払った医療費が定められた自己負担上限額を超えた場合、その超えた分の金額が支給される制度です。
2024年12月、政府は自己負担上限額を段階的に引き上げる見直し案を示しました。その後、がんなどの患者団体をはじめ反対意見が広がったことから、2025年3月には事実上の白紙撤回となり、改めて検討を行ったうえで2025年秋までに方針を決定することになっています。
それを踏まえて、患者団体や保険者、労使団体を代表する委員等から構成される 「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」にて、ヒアリングや具体的な議論が行われてきました。
その中で整理された論点は、次の3つです。
- ・ 高齢化の進展や医療の高度化等により増大する医療費への対応
高齢化の進展や医療の高度化等により医療費が増大する中において、自己負担限度額について一定の見直しを含めて、高額療養費の負担の在り方をどのように考えるか。 - ・ 年齢にかかわらない負担能力に応じた負担
年齢にかかわらない負担能力に応じた負担という全世代型社会保障の考え方に基づき、 70歳以上の高齢者のみに設けられている外来特例の在り方についてどのように考えるか。
また、負担能力に応じた負担を求める観点から、現行制度において大括りとなっている所得区分の在り方についてどのように考えるか。 - ・ セーフティネット機能としての高額療養費制度の在り方
高額療養費制度はセーフティネット機能として患者にとってなくてはならない制度であり、今後もこの制度を堅持していく必要性については認識が一致している。その上で、仮に自己負担限度額の見直しを行っていく場合であっても、患者の経済的負担に配慮したセーフティネット機能の在り方をどのように考えるか。
部会の委員からは、高額療養費制度の見直しは医療保険制度改革全体の中で考えなければいけないこと、現役世代の負担軽減は急務であること、セーフティネット機能が損なわれないよう慎重な議論を要することなどで同意が得られた一方、次のような意見も出されました。
- ・ 経済的格差が拡大傾向にある中、応能負担を強化し累進性を高める必要がある。
- ・ 長期にわたって医療を受ける方においては、傷病手当金などの所得保障の仕組みも含めて考える必要がある。
- ・ 高額療養費の支給対象にはいわゆる低価値医療・無価値医療も含まれている可能性があり、対応が必要ではないか。
2.薬剤給付の在り方について
薬剤給付については、次の3点が議題に挙げられました。
(1)長期収載品について
長期収載品とは、一般的に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品のことです。医療費の支出を抑制するため、政府はより安価な後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置き換えを促進しています。
長期収載品について示された論点は、下記のとおりです。
- ・ 後発医薬品の数量ベースでの使用割合は90%以上に上昇しており、後発医薬品の使用促進に一定の効果があったと言える一方、特に後発医薬品を中心に医療用医薬品の供給不足により、医療現場に負担がかかっているとの指摘もある。
- ・ このような状況にも配慮しつつ、創薬イノベーションの推進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて、長期収載品の選定療養の更なる活用について、どのように考えるか。
- ・ 具体的には、現在、患者希望で長期収載品を使用した場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を患者負担としているが、この水準を引き上げることについてどのように考えるか。
委員からは、後発医薬品の普及が一定程度進んでいることを評価しつつ、一層の普及促進を図ることが必要という認識が示されました。
その中で、医薬品の安定供給が大きな課題であると指摘されました。
(2)バイオ後続品について
バイオ後続品(バイオシミラー)とは、先行バイオ医薬品の特許期間・再審査期間満了後に、先行バイオ医薬品と同等/同質と認められた医薬品です。政府は後発医薬品(ジェネリック医薬品)同様、先行バイオ医薬品からの置き換えを促進しています。
バイオ後続品については、次のような論点が示されています。
- ・ 一般的に、バイオ医薬品は薬価が高く、製造体制の確保に時間を要する。
- ・ バイオ後続品は先行バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性・有効性を有することが臨床試験等で検証されているが、低分子後発医薬品に比べて、「バイオ後続品に切り替えるには医師の判断が必要」「先行品と後続品に共通の一般名が存在しない」「一般名処方加算やバイオ後続品を調剤できる体制を評価する点数がない」といった特徴がある。
- ・ バイオ後続品への置き換え率は数値目標にも達していないため、引き続き置き換えを促していく必要がある。
- ・ 患者がバイオ後続品を選択できるよう、環境整備を進めていくために、どのような方策が考えられるか。
委員からは、バイオ後続品の制度上の建付けに普及が進まない要因があるという指摘がなされ、診療報酬上の加算などの措置が必要ではないかという意見が出されました。
(3)OTC類似薬について
OTC類似薬とは、医師による処方を必要とする処方薬のうち、ドラッグストア等で購入できる市販薬(OTC医薬品)と同様の効用をもつものです。医療費の抑制のため、OTC類似薬を保険適用から除外するという案が出されていました。
OTC類似薬については、次のような論点が示されています。
- ・ 医療機関における必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、医療保険制度の持続可能性確保を目指す観点から、どのような仕組みとすることが適切か。
- ・ 医療用医薬品とOTC医薬品は成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、対象年齢、投与経路・剤形等に違いがあることを踏まえ、OTC類似薬の範囲についてどのように考えるか。
委員からは、OTC類似品の単純な保険適用除外には反対する声が多く上がりました。
医療へのアクセス確保、院内処方や薬局のない地域の問題、国民の理解を得られるかどうかなど、複数の課題点が挙げられました。また、議論の足掛かりとして、リスクの低い薬剤について具体的に絞って検討することも提案されました。
まとめ
今後、部会での議論を踏まえて、どのような制度のあり方が望ましいのか方針を取りまとめていくことになります。
いずれの論点でも、増大する医療費の抑制と国民の負担の抑制をどのように設定するか、給付と負担のバランスについて国民の理解と納得を得られるかどうかが重要となります。
