ナッジのススメ 第2回 ものを捨てられないのはなぜ?
2025/11/20
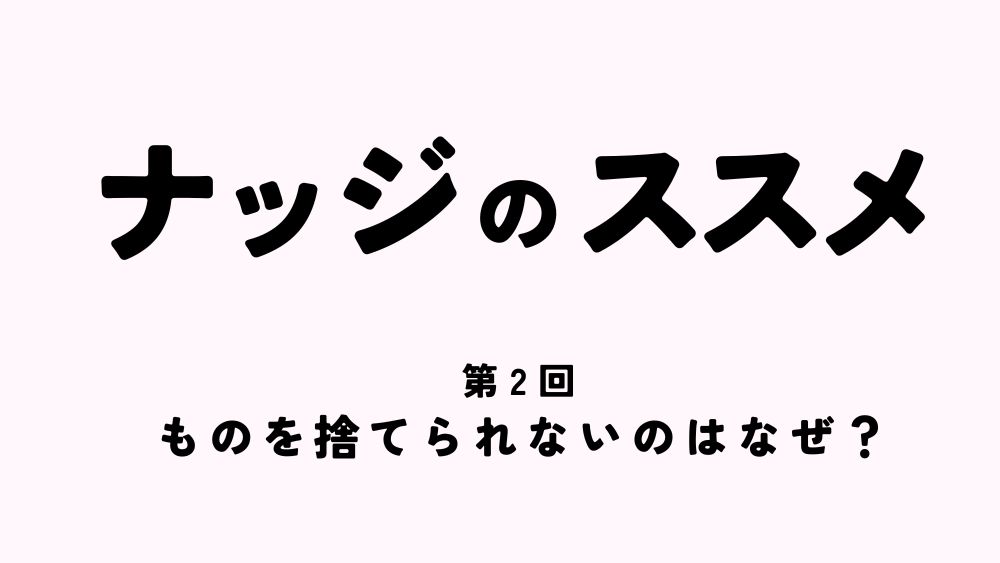
感情の習性に沿って、望ましい行動へと促す手法「ナッジ」。
今回から「介護の現場でのコミュニケーションを円滑にするためのナッジ」について、ナッジを用いたヘルスプロモーションを研究している竹林正樹さんと、在宅を中心とした高齢者支援に奔走する橘友博さんが語り合います。
橘 竹林先生に相談です! 空のペットボトルをためているMさんという利用者がいます。私たちが「片づけませんか?」と提案しても、「まだ使うから触らないでくれ」と言って、捨てようとしません。悪臭がしたり、カビが生えたりして衛生的に好ましくありませんが、無理やり捨てるわけにもいきません。どのように対応すればよいでしょうか?
竹林 Mさんは認知バイアスが強くなっているかもしれません。次の問いを考えてみましょう。
【問1】ある大学の学生Aに大学の紋章が入ったマグカップを渡しました。その後、同じ大学に通う学生Bにそのマグカップを見せて、「これをいくらなら買いますか?」と尋ね、Aにも「いくらならBに売りますか?」と聞きました。Aが示した金額とBが示した金額はどうだったでしょうか?
❶Aが高い
❷ほぼ同じ
❸Bが高い
竹林 正解は❶です。AはBが示した2・5倍の値段を設定しました。これは、一度手にしたものは手放したくなくなる「保有バイアス」という心理現象がはたらいていたことを示唆しています。
橘 私たちが「これ、もういらないよね」と感じたものでも、利用者さんは高い価値を感じている可能性があるのですね。
竹林 この実験では、大学のマグカップを対象に価格をつけましたが、自分が手がけたものになると、もっと高い価値を感じるようになります。
【問2】折り紙の初心者が折り鶴をつくりました。完成した折り鶴は不格好ですが、折った人は客観的評価よりも高い価値をつけました。
どれくらい高い価値をつけたでしょうか?
❶2・5倍
❷3倍
❸5倍
竹林 正解は❸です。この心理を「IKEA効果」と呼びます。北欧の家具メーカー、IKEAの家具も自分で苦労して組み立てるからこそ、多少不格好でも格別の愛着を感じることにちなんで、このように呼ばれています。
橘 その気持ちはわかります! そういえば、Mさんの家の庭にペットボトルでつくった猫除けが置いてあったような…。
竹林 Mさんは猫除けをつくっているうちに、ペットボトルに強い愛着を感じるようになったのかもしれません。特にペットボトルが毎日目に触れると、愛着が湧きやすくなります(単純接触効果)。そこでゴールを「短期間でもよいので目の前にペットボトルがない状態をつくること」に設定すると、解決策が見えてきそうです。Mさんには次のナッジを使ってみてはいかがでしょうか?
【ナッジ】「この前、タレントのNさんが『使い終わったペットボトルは活用すべき!』とテレビで言っていました。私も活用したいと思っているのですが、ここにあるペットボトルを少しお借りできませんか?」と尋ねる。
橘 これで大丈夫なのですか?
竹林 人の心理や行動について、「100%こうなる」と断言することはできませんが、可能性を高めることはできます。順に説明します。
❶タレントのNさんという第三者を出すことで、メッセンジャー効果(同じ内容でも誰が言ったかによって、受け止め方が大きく変わる心理現象)が生じやすくなります。
❷「少し借りる」というのは、保有しているけれども目に触れない状態をつくることです。物理的距離をとることで、愛着も薄れていきます。
❸「自分のものが人の役に立つ」と考えることで、他人のためなら行動したくなる心理(利他性バイアス)が刺激され、かつ自分のものが認められたという承認欲求が満たされ、悪い気がしないものです。
橘 たしかにこのやり方だと、Mさんは喜んで貸してくれそうですね。少し距離を置いてもらってから、改めて必要かどうかを聞いてみます。
また、Mさんの家族から「何度も事故を起こしそうになっているのに車の運転を続けている」という相談を受けています。ナッジで免許返納を促すことはできますか?
竹林 Mさんは免許に対しても保有バイアスやIKEA効果が強くはたらいていると考えられるので、難しいですね。運転の頻度を下げることをゴールにし、それに向けたナッジならできそうです。
たとえば、「車を修理に出し、修理が終わるまではタクシーに乗る」という形で、まずは一時的に本人に車から距離をとってもらうことから始めるのがよさそうですね。連続性を断ち切らないと、「いつもと同じ行動をして何が悪いの?」という感情になりやすいからです。納得できる理由があれば、「車がなくても仕方ないか」と、受け入れやすくなります。これは「理由による力」と呼ばれる心理を活用したナッジです。
橘 なるほど。認知バイアスに沿ったナッジを使うことで、お互いにストレスなく行動へと踏み出せる可能性が高まるのですね。よくわかりました!
まとめ
保有バイアスやIKEA効果が強いと、不要なものでも手放したくない気持ちが高まるので、まずは「目の前にない状態をつくり出す」ためのナッジを考える。
参考文献
ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー 下 あなたの意思はどのように決まるか?』村井章子訳、早川書房、2014年
ダン・アリエリー『不合理だからうまくいく 行動経済学で「人を動かす」』櫻井祐子訳、早川書房、2014年
竹林正樹
青森大学客員教授。青森県出身。行動経済学を用いて「頭ではわかっていても、健康行動できない人を動かすには?」をテーマにした研究を行い、年間10本ペースで論文執筆。各種メディアでナッジの魅力を発信。ナッジで受診促進を紹介したTED(テッド)トークはYouTubeで80万回以上再生。著書に『心のゾウを動かす方法』『介護のことになると親子はなぜすれ違うのか』など。
橘 友博
合同会社くらしラボ代表。介護福祉士、ケアマネジャーとして介護施設で勤務したのち、2015年に合同会社くらしラボを設立。「あなたの“ふつう”を考える」をコンセプトに複数の介護事業所を運営し、在宅を中心とした高齢者支援に奔走している。
