ナッジのススメ 第1回 相手に寄り添うケアって?
2025/11/13
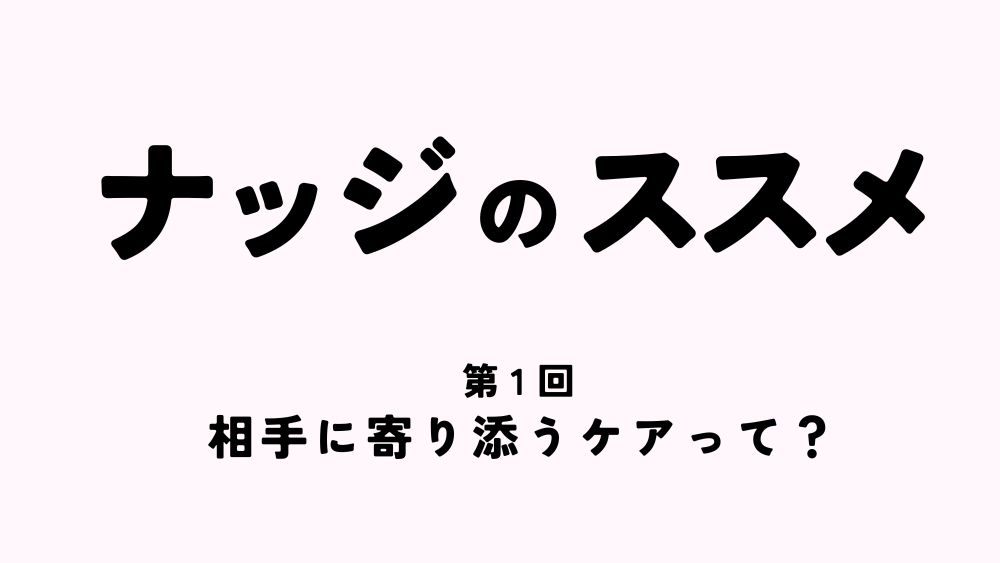
感情の習性に沿って、望ましい行動へと促す手法 「ナッジ」。
介護の現場でのコミュニケーションを円滑にするためのナッジを紹介します。
今回は導入として「認知バイアス」や「ナッジ」について、ナッジを用いたヘルスプロモーションを研究している竹林正樹さんが解説します。
介護現場では、利用者や同僚に対し、「もっとこうしたほうがいいのに」と思う場面がよくあるものです。支援は本人主体が原則であり、介護者の視点だけで利用者の行動を決めてはいけません。でも、その人にとって望ましい行動を自発的に行えるような手法を介護職が知っておくことは、大きな意義があります。
その手法の一つが「ナッジ」です。ナッジはもともと「そっと後押しする」を意味する英語で、ここでは「感情の習性に沿って自発的に行動を促す手法」として用います。
ナッジ提唱者のセイラー博士(米国)がノーベル経済学賞を受賞したこともあり、ナッジが世界中で注目されています。日本でも国が健康環境づくりにナッジを推奨し、管理栄養士国家試験にもナッジが出題されています。
今やナッジは健康支援に不可欠なスキルで、介護現場でも応用できます。
相手に寄り添うケア
「相手に寄り添うケア」が理想といわれます。しかし、相手の何にどう寄り添えばよいのでしょうか?
この答えを明確にするためには、科学的に「寄り添う」の意味を考える必要があります。本連載では、「認知バイアス(感情の習性)」と「ナッジ」の側面から考えていきます。
「認知バイアス」 とは
人間の脳には「感情(直感)」と「理性」という2つの機能があり、判断の大半は感情が担当します。
感情は存在感があり、本能的で力が強いことから、「象」にたとえられます。感情は面倒くさがりで、自分が大好きという習性をもち、これを「認知バイアス」と呼びます。認知バイアスが強いと、正しい情報を得ても自分に都合よく解釈するため、望ましい行動をしなくなる可能性が高まります。
一方、理性は「象使い」にたとえられ、自制を司ります。しかし、理性は有限であり、枯渇すると認知バイアスを制御できなくなります。
たとえば、多くの喫煙者は禁煙意思があっても、なかなか禁煙できません。
その背景には、次の認知バイアスが存在します。
現在バイアス
「現在バイアス」とは、将来の大きな利益よりも、目先の小さな利益のほうを優先したくなる心理です。
喫煙者は非喫煙者よりも現在バイアスが強く、「禁煙」という将来にかかわる重要な決断よりも「今すぐの一服」という目先の快楽を優先したくなります。その結果、「我慢するという精神的コストを今払いたくないので、禁煙は来週からにしよう」と先送りしやすくなります。そして、翌週も同様の思考をすると、また先送りされます。それが繰り返されるといつまでも禁煙が始まりません。
同調バイアス
同調バイアスとは、周囲の人の行動と同じ行動をとりたくなる心理です。
喫煙でいうと、集団の喫煙率が10ポイント上がると、個人の喫煙率も10ポイント上がることが報告されています 。
このような認知バイアスをもつ喫煙者に対して、「禁煙しないと20年後に肺がんリスクが高まります」「この地域での喫煙率が高いので、禁煙しましょう」といった指導は、あまり相手に寄り添っているとはいえません。
なぜなら、現在バイアスの強い喫煙者は20年後のことに関心が低く、さらに「皆が喫煙しているのなら、自分も」となる可能性が高いからです。認知バイアスを考慮しない禁煙指導は、逆に喫煙を促進する可能性があるのです。
「ナッジ」 とは
研究が進み、認知バイアスには一定の法則性があることが判明しました。
それにより、「このタイミングでこの刺激を受けると望ましい行動をする」ということが、一定の確率で予測できるようになりました。つまり、阻害要因となる認知バイアスを軽減し、促進要因となる認知バイアスを味方につける設計をすることで望ましい選択へと後押しできるようになったのです。この設計がナッジです(図2)。
ナッジは学術的には「選択の自由を確保しながら、褒美や罰を使わずに行動を促す手法」と定義されます。
さて、ここまでの議論から「寄り添う」という意味を次のように考えます。
寄り添う対象は相手の「感情と認知バイアス」、寄り添い方は「認知バイアスに合ったナッジを使う」
私たちは相手のすべてはわからなくても、「人は感情に従った行動が多く、感情には認知バイアスがある」ことはわかります。相手の感情を軽視すると、相手の心は大暴れします。何しろ感情は「象」なのですから。私たちは野生の象に接するときには、象の習性に逆らうことはしません。人間関係でも、感情の習性に沿ったコミュニケーションが求められます。
(次回に続く)
竹林正樹
青森大学客員教授。青森県出身。行動経済学を用いて「頭ではわかっていても、健康行動できない人を動かすには?」をテーマにした研究を行い、年間10本ペースで論文執筆。各種メディアでナッジの魅力を発信。ナッジで受診促進を紹介したTED(テッド)トークはYouTubeで80万回以上再生。著書に『心のゾウを動かす方法』『介護のことになると親子はなぜすれ違うのか』など。
参考文献
Haidt J. The righteous mind: why good people are divided by politics and religion, Vintage; 2013.
Lawless L, Drichoutis AC, Nayga RM. Time preferences and health behaviour: a review. Agricultural and Food Economics. 2013; 1. https://doi.org/10.1186/2193-7532-1-17.
Norton EC, Lindrooth RC, Ennett ST. Controlling for the endogeneity of peer substance use on adolescent alcohol and tobacco use. Health Econ. 1998; 7: 439-53.
大竹文雄『行動経済学の使い方』岩波新書、2019 年、44-46頁。
👉 第2回はこちら
