訪問看護における食支援の考え方と実践
2025/10/21
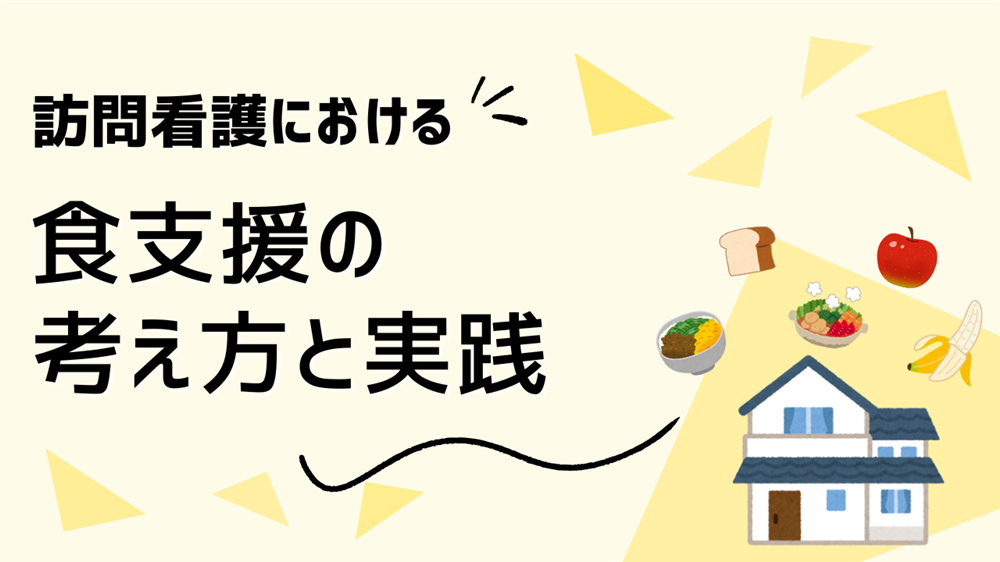
在宅で療養する高齢者には、予防的かつ適切な食支援の技術が欠かせません。ここでは、在宅療養者にみられる低栄養の傾向や加齢に伴う身体変化を踏まえ、訪問看護における食支援や多職種連携の重要性について解説します。
【記事の監修者・著者】
江頭文江(えがしら・ふみえ)
地域栄養ケアPEACH厚木 代表、管理栄養士
聖隷三方原病院栄養科にて嚥下調整食の研究や摂食嚥下障害者の栄養管理に携わる。2000年に管理栄養士による地域栄養ケア団体「ピーチ・サポート」を設立、2003年4月には「地域栄養ケア PEACH 厚木」と改称。訪問栄養指導や外来栄養指導、離乳食・介護予防講座など、赤ちゃんから高齢者まで幅広い年齢層に対応し、生活の視点をもった地域食支援を実践。
梶井文子(かじい・ふみこ)
東京慈恵会医科大学医学部看護学科老年看護学教授、看護師・管理栄養士
東京大学医学部附属看護学校を卒業後、女子栄養大学栄養学部栄養学科を卒業。東京大学医学部附属病院での勤務を経て、時事通信社(株) 健康管理室で栄養指導やカウンセリング等の保健活動、健診業務に従事。その後、おもて参道訪問看護ステーションで訪問看護師を経験。聖路加看護大学(現聖路加国際大学)での助教・准教授を経て、2015年より現職。
訪問看護になぜ食支援が必要か
訪問看護では、療養者の自宅等を訪問し、病状や障害の状態把握、日常生活の助言、保清、排泄ケア、服薬管理、栄養管理、褥瘡等の手当て、医療機器の管理・指導、リハビリテーションなど多岐にわたるケアを提供します。この中で特に栄養管理は、利用者の全身状態を安定させ、生活の質を維持するために極めて重要なケアの一つです。
低栄養のリスクと全身状態への影響
訪問看護の利用者のなかには、入院中の絶食や末梢静脈栄養、経管栄養が続くことでやせてしまい、ADL(日常生活動作)が低下するケースがしばしば見られます。例えば、回復期リハビリテーション病棟の脳卒中患者の約9割に低栄養リスクが認められるとの報告もあります。低栄養状態が続くと、リハビリテーションの効果が得にくくなるだけでなく、発熱や摂食嚥下機能の低下など、全身状態の不安定化につながります。
全身状態が不安定になると、利用者本人の苦痛や介護者の不安が増大するだけでなく、訪問看護にとっても緊急訪問や対応が増加する結果となります。そのため、利用者と支援者双方にとって、栄養状態の安定は非常に重要です。
食支援の4つのポイント
「食支援」とは、療養、疾患、介護、生活などを総合的に把握し、相手を尊重しながら、誰もが口から食べる喜びを実感できるよう支援することです。これは単に食や栄養の知識・スキルだけでなく、多角的な視点からの関わりが必要です。食支援には以下の4つのポイントがあります。
①おいしく食べる:
おいしい料理だけでなく、おいしく食べる心身の健康と食べるための機能が重要です。嗜好は味だけでなく食感や見た目にも影響され、認知機能や咀嚼・嚥下機能の低下によって変化することがあります。
②楽しく食べる:
誰かと食べる、盛り付けや食器の工夫、花や音楽による環境づくりなど、食べる行為を楽しいものにする工夫が求められます。一人暮らしや食事介助が必要な状況でも、楽しめる環境を整えることが大切です。
③健康に食べる:
病気の予防や再発防止に食事は非常に重要です。在宅療養者のなかには脳梗塞の後遺症、心不全、糖尿病などの慢性疾患を持つ方も多いため、体調の安定には適切な食生活管理が不可欠です。
④最期まで食べる:
「口から食べる」ことは栄養・水分補給だけでなく、楽しみやコミュニケーションの手段でもあります。終末期においても、本人の希望を尊重しつつ、口腔ケアや姿勢調整、嚥下調整食の活用などを通じて、最後まで「おいしい」と感じられる支援を目指します。
栄養管理は全身管理のひとつ
栄養管理は、専門的な領域と思われがちですが、「食べられていますか?」「少し痩せましたか?」といった日常の会話の中にもその要素は含まれています。栄養状態の安定は、顔色、眼球、頭髪、皮膚の状態など全身状態に大きく影響します(表1)。食事が減って痩せると、身体機能や咳嗽力が低下し、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。
表1 食事が関連する全身状態の変化
| 全身状態の変化 | 食事に関する要因の例 | |
|---|---|---|
| 皮膚の乾燥がみられる | → | 水分不足、油脂不足、低栄養 |
| 覚醒が悪い | → | 低栄養、水分不足 |
| 食べるときによくむせていたのに、最近はむせなくなった | → | 全身機能の低下、咳嗽力の低下 |
| 痰がごろごろと絡むようになった | → | 咽頭残留が増えた、喀痰力の低下、残留物を嚥下できない |
| 食べると疲れやすい | → | 体力低下 |
| 便秘や下痢が続く | → | 食事摂取量低下 |
低栄養状態では嚥下訓練の効果も出にくい場合があり、栄養状態が改善することで、嚥下機能や咳嗽力が改善し、たとえ誤嚥したとしてもむせられるようになります。このように、栄養管理は特別なものではなく、全身管理を行う上で重要な要素なのです。
在宅療養と低栄養状態
低栄養状態とは、エネルギーとたんぱく質が欠乏し、健康維持に必要な栄養素が不足した状態です。高齢者は咀嚼や嚥下機能、消化機能の低下により、栄養や水分を十分に摂取できないことがあり、低栄養状態には注意が必要です。低栄養状態になっても自覚症状がなく気づきにくいことがあるため、BMI(体格指数)、体重減少率、血清アルブミンなどが指標となります。BMIは、<18.5が低栄養状態のスクリーニングのカットオフ値となります。
特に在宅では、定期的に体重を測る習慣が非常に重要です。高齢になると、若いときに比べ、身体の筋肉や水分が減るといわれています。高齢者になると、実は肥満よりも「やせ」の方が死亡率が高い傾向にあるとの報告もあります。
加齢による身体機能の変化と食欲低下の要因
加齢に伴い、さまざまな身体変化が見られますが、なかでも食に関するものとしては①唾液の分泌が減る、②口の渇いたと感じにくい、③噛む機能が衰える、④飲み込む機能が衰える、⑤味覚が鈍くなる、⑥嗜好の変化や食欲がなくなる、⑦消化・吸収機能が低下する、⑧上肢・下肢の機能が衰える、⑨排泄機能が衰える等、さまざまな身体変化が見られます。
「食べられない」ということは、全身管理をするうえで非常に大きな問題です。「食べられない」のは単に嗜好が合わないということだけではなく、咀嚼・嚥下機能の問題、消化器症状、うつや認知機能、姿勢や食事介助など摂食環境、食事調達や調理スキル、介護者の理解や実践、服薬の影響、孤独や貧困など、複合的な要因を抱えていることがあります(表2)。これらの問題を整理し、利用者の生活情報をしっかりと把握した上で介入する必要があります。
表2 食べられなくなる要因
| 疾病 | がんや消化器疾患 糖尿病などの治療の影響 呼吸器系疾患や酸素療法 うつや認知機能の低下 下痢などの排泄問題 |
|---|---|
| 加齢 | 摂食嚥下機能の低下 視力の低下 サルコペニア、体力低下 嗜好の変化 |
| 生活環境 | 一人暮らし、高齢者世帯 共同世帯者の健康障害 買い物、調理、配膳、喫食状況 粗食、以前の食事療法の影響 |
ステージ別の栄養管理
地域包括ケアシステムでは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供できる体制を目指しています。このシステムにおいて、栄養ケア・食支援は重要な意味を持っています。
予防、治療(改善)、維持、終末での栄養管理
高齢者の加齢による変化は個体差が大きく、疾患の影響も加わるため、個々の身体状況や機能を把握した上で支援することが重要です。
フレイル期(虚弱な状態)にある場合は、健康な状態に戻るためにも、適度な運動とともに、十分なエネルギーとたんぱく質の摂取が重要です。フレイルから要介護状態に移行してしまうと、機能低下や障害がある中でも、機能を維持して口から食べる機能を改善するための支援が必要です。この段階でも十分なエネルギーとたんぱく質が必要ですが、疾患の食事療法も考慮して対応します。
要介護度が進み、人生の最終段階がみえてきたときには、身体機能に合わせて栄養補給の「ギアチェンジ」が必要となります。衰えた身体は栄養を吸収しにくくなるため、身体が吸収できる分だけの栄養を補給し、過度な栄養や水分は不要となります。最期まで口から味わう喜びを支えるために、誤嚥に配慮した口腔ケア、安楽な姿勢調整、本人の嗜好に合わせた安全な食形態の調整をして支援します。
病院から在宅へのシームレスな食支援
医療の現場では、入院と同時に退院を見据えた看護計画の作成や、退院後の在宅支援者との合同カンファレンスが行われるようになってきました。自宅へ戻るためには、1日3食食べることを支えられるかどうかが鍵となります。病院と在宅のスタッフが情報共有し支援することが、患者や家族の在宅生活への不安軽減につながります。
口から食べる支援は、栄養管理(経口・経管)や食事内容(食形態、調理支援)だけでなく、口腔ケア、嚥下リハビリテーション、食事姿勢、食具、一口量、食事介助法、呼吸リハビリテーションなど、トータルでの環境調整・支援が必要です。さらに、低栄養や慢性疾患の食事療法では、栄養バランスと食形態の両方に配慮した工夫が求められ、365日3度の食事準備は介護者にとって大変なケアになります。
食に関する多様な課題に対して、訪問看護師には多職種と連携し、利用者と介護者を総合的に支援することが求められます。
