有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会
2025/10/14
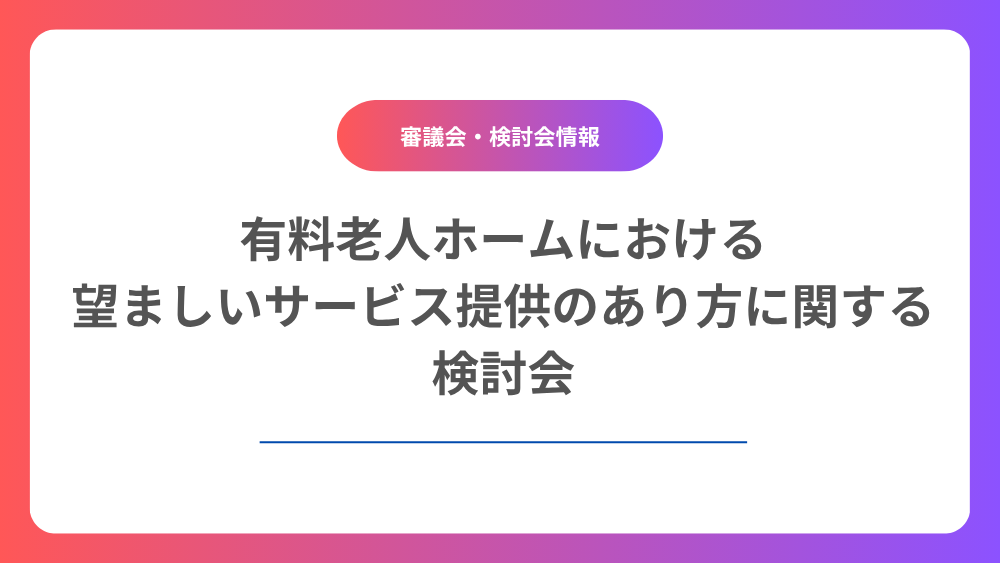
2025(令和7)年10月3日、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の第6回が開催されました。
今回の会合で大筋での合意が得られたとりまとめ素案の内容について紹介します。なお、詳細な資料や議事録は 厚生労働省HP に掲載されています。
目的・背景
本検討会の目的は、有料老人ホームの運営やサービスにおける透明性・質の確保に関する課題への対応策を検討することです。
高齢者の住まいに関するニーズが多様化する中で、有料老人ホームはそのニーズの受け皿として重要性を増しています。その中で、過剰な介護サービス提供(いわゆる「囲い込み」)や、給料未払いによる職員の一斉退職、入居者紹介事業者に対する高額な紹介手数料の支払いなど、様々な課題も浮き彫りになってきています。
これらの課題を踏まえ、検討会の議論の中心となったポイントは次の4点です。
1. サービスの質・安全性の確保と事前規制の導入
多くの住宅型有料老人ホームにおいて、入居者の高齢化・重度化が進み、要介護3以上が55.9%を占めるなど、中重度の要介護者や医療的ケアを必要とする高齢者の受け皿となっています。しかし、現行の届出制では運営基準や設備基準に関する厳格な規制がなく、都道府県等による指導監督にも限界があると指摘されていました。
具体的な対応方針
中重度の要介護者や医療ケアを要する要介護者を対象とする有料老人ホームについては、行政の関与を強化するため、登録制といった事前規制の導入が検討されます。
この事前規制として、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令上設ける必要性も示されました。具体的には、介護・医療ニーズや夜間・緊急時対応を想定した職員配置基準、ハード面の設備基準、虐待・事故防止措置、看取り指針の整備、不当な契約解除を禁止する基準などが求められています。
また、都道府県等が事業の開始前・開始後ともに効果的な対応を取ることができるよう、事前規制を老人福祉法に基づく統一的な基準として策定することが提案されました。
2.情報・契約の透明性向上と入居者による適切なサービス選択
有料老人ホームは施設によって様々なコンセプト・経営方針をもっているため、入居希望者はそれぞれのホームについて情報を精査する必要があります。しかし入居契約は複雑で不透明な要素が多く、高齢者やその家族と事業者の間で情報量や交渉力に格差があるため、消費者にとって不利な契約になる可能性が指摘されていました。
また、介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームの違いなど、制度の建付けが高齢者やその家族には理解されにくい状況も課題とされていました。
具体的な対応方針
消費者保護の観点から、契約書や重要事項説明書、ホームページなどで、事業者が十分な説明や情報提供を行うことを確保し、契約前に書面で説明・交付することを義務づける必要性が示されました。
具体的には、特定施設・住宅型の種別、介護保険施設等との相違点、要介護度や医療必要度に応じた受入れの可否、介護サービス費を含む費用、介護・医療・看護職員の常駐の有無、看取り指針の有無、退去・解約時の精算・返還等について確実に説明することが求められます。
また、入居希望者が活用しやすいよう、情報公表システム(介護サービス情報公表システム等)の充実が求められるほか、住まい選びや苦情相談について、地域ごとに専門機関と連携したワンストップ型の相談窓口を設けることが有益であるとされました。
3. 入居者紹介事業の高額紹介手数料への対応
都市部を中心に存在感を増している入居者紹介事業において、有料老人ホームが要介護度や医療の必要度に応じた高額な紹介手数料を支払っている事案が明らかになり、社会保障費の使途の適切性や、高齢者の尊厳確保の観点から逸脱しているのではないかという懸念が示されました。
具体的な対応方針
事業者団体が運営する既存の届出公表制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みの創設が有効とされました。
紹介事業者は、利用者に対して中立的な立場から正確な情報に基づきホームを紹介すること、成約時に有料老人ホーム側から紹介手数料を受領すること、および紹介手数料の算定方法等を、入居希望者に対し事前に書面で明示する対応が求められました。
紹介手数料の設定については、高齢者の状態像に関わることなく、賃貸住宅の仲介を参考に、例えば月当たりの家賃・管理費等の居住費用をベースに算定することが適切であると提言されました。有料老人ホーム運営事業者も、紹介事業者の活用有無や手数料の算定方法等を公表すべきとされました。
4. 「囲い込み」対策とケアマネジメントの中立性確保
住宅型有料老人ホームにおいて、ホームと同一・関連法人が居宅介護支援事業所や介護サービス事業所を併設・隣接し、実態として住まいと介護が一体的に提供されている場合が多く、入居者のニーズを超えた過剰な介護サービス提供(囲い込み)が生じる背景となっていました。これにより、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対し、同一法人のサービスを支給限度額一杯に利用するよう要請する事例が報告されています。
具体的な対応方針
居宅介護支援事業所やケアマネジャーの独立性を担保するため、指針の公表や管理者研修などの措置を行うことが提案されました。
入居者の自由なサービス選択を確実に担保するため、ホームと資本・提携関係のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所の利用を契約条件とすることや、利用する場合に家賃優遇などの条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁止する措置を設けるべきとされました。
また、自治体による事前チェックを働かせるため、有料老人ホームと介護サービス等の運営事業者が同一・関連事業者である場合には、ホームの事業部門と介護サービス等部門の会計を分離独立して公表し、行政がその内訳や収支の妥当性を確認できる仕組みが必要とされました。
今回の素案で、有料老人ホームのあり方に関する論点が整理されました。今後、パブリックコメント等を通じて国民全体から意見を聞いた上で、秋頃に取りまとめが公表される予定です。
