第4回障害児支援における人材育成に関する検討会
2025/07/29
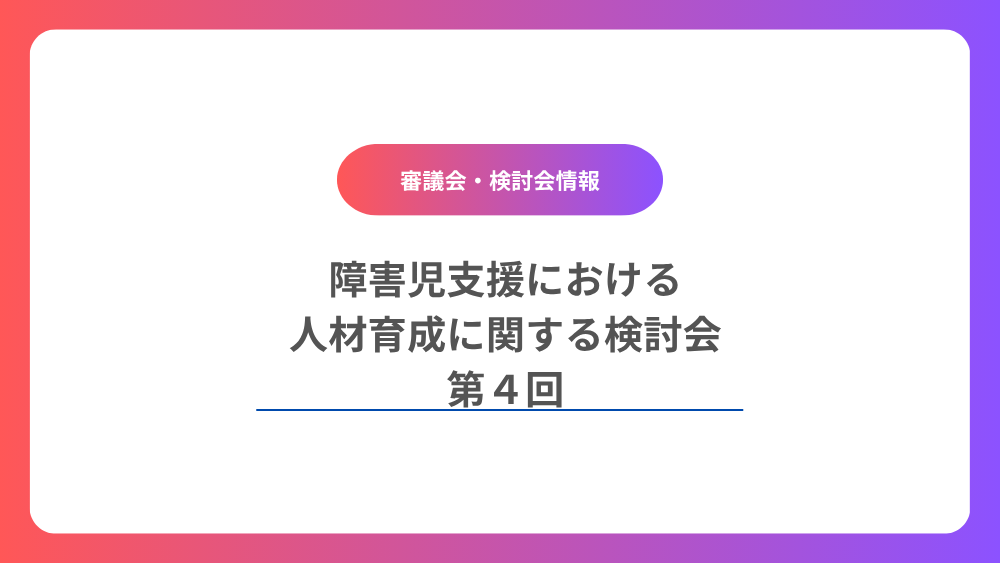
「第4回障害児支援における人材育成に関する検討会」の内容を紹介します
令和7年7月28日(月)、「第3回障害児支援における人材育成に関する検討会」が開催されました。
障害児支援における人材育成の在り方と、その具体的な研修体系について議論・検討が行われており、第3回では報告書(案)が示されました。その内容を紹介します。
なお、検討会の開催状況や議事録・資料等は、
こども家庭庁HP
に掲載されます。
これまでの経緯
平成24年の児童福祉法改正以降、障害児通所支援の事業所数・利用者数は大きく拡大してきました。その一方で、適切な運営や支援の質の確保が課題とされてきました。
これまでガイドラインや運営指針の策定が行われてきましたが、令和5年3月に取りまとめられた「障害児通所支援に関する検討会」報告書において段階的な研修体系の構築の必要性が指摘されたことを受けて、全国どの地域でも質の高い障害児支援の提供が図られるよう、障害児支援における研修体系の構築を目指して検討が行われました。
ここでは、主な論点を4つ紹介します。
1. 研修体系創設の意義
人材育成における課題
近年、障害児通所支援の事業所数・利用者数が飛躍的に増加している一方で、適切な運営や質の確保が課題とされてきました。
人材育成は体系化されておらず、各事業所での実施に委ねられているため、事業所間で理念や価値の捉え方、知識、技術に格差が生じています。また、地域において事業所同士が十分な協働関係になっていないという指摘もありました。
研修体系創設の意義
国が全国共通の枠組みで研修体系を構築することにより、全ての支援者が共通の理念や価値、知識、技術を学び、質の高い支援を全国どこでも提供できる土台を築き、支援者自身の成長やキャリア形成にも繋がることが期待されます。
また、地域での学び合いを通じて、事業所の垣根を超えた協働関係の地域づくりが進み、子供や家族が安心して支援を受けられる環境につながることが期待されています。中長期的には、本研修を他のこども施策にも活用し、インクルージョンの推進や共生社会の実現に向けた土台となることも期待されています。
支援者の基本姿勢
全国共通の共通の考え方として、「障害のあるこどもとその家族とともに歩むための支援者の基本姿勢」が整理されました。
この基本姿勢には、こども・若者、子育て当事者のヒアリングで出された意見が反映されています。基本姿勢は、次の5つの柱で構成されています。
・尊重し合いながら、ともに生きる
・想いに寄り添い、ともに支え合う
・支援をともにつくる
・安心できる場をともに育てる
・ともに学び合い、ともに育ち合う
障害児支援者における重要な共通要素
支援者が発達支援に必要な専門性を発揮するために重要なスキルや行動特性として、「対人支援における倫理的姿勢」「自己理解と省察」「こどもの理解に基づく支援」「計画と評価に基づく支援の実践」「家族支援」「地域支援・地域連携」「チームアプローチ」「虐待予防・対応」「相互理解・相互支援」の9領域が整理されました。
構成要素と人材像
研修は「障害児支援基礎・実践研修(Ⅰ)(Ⅱ)」「障害児支援リーダー研修」「障害児支援コア人材研修」の3階層で、それぞれについて科目数や実施時間、受講期間のイメージとともに、期待される人材像が整理されています。
2. 標準カリキュラムと効果的な実施手法
標準カリキュラム
障害児支援基礎・実践研修(Ⅰ)(Ⅱ)、障害児支援リーダー研修、障害児支援コア人材研修それぞれの科目とねらいが詳細に整理されています。
受講期間や実施時間は、実施主体となる事業者等が現場の実態に合わせて柔軟性のある運用ができるよう、幅を持たせた設定となっています。
基礎・実践研修の効果的な実施
事業者の負担軽減のため、動画視聴による講義の実施体制を整備し、隙間時間での受講や学び直しが可能なコンテンツ(約15分~20分/科目)が想定されています。
講義だけでなく、「支援者自身の振り返り」「上司や先輩職員との対話」「事業所内の他の職員との学び合い」といった取り組みを組み合わせることが基本とされ、合計で約7時間(基礎Ⅰ)と約22時間(基礎Ⅱ)を目安としています。
想定された受講期間は基礎Ⅰが最長半年、基礎Ⅱが最長3年目程度までとなっています。
リーダー・コア人材研修の効果的な実施
演習は対面研修を基本とし、地域での関係づくりに繋がることを期待しています。オンライン代替も可能ですが、対面研修と同等の効果を担保し、地域支援者間の関係づくりを促す機会も設ける必要があります。
事業所内・地域内でリーダー的役割を担うことが目指されており、受講期間は定められておらず、それぞれの役割等に応じて任意受講とされています。
3. 研修の実施主体
基礎・実践研修
速やかな研修受講のため、事業者が実施主体となることが定められています。
また、座学以外にもOJT等と組み合わせるなどして、実践の中での具体的な支援方法を身につけていくことが必要であるとされています。
実施に当たっては、事業者団体や児童発達支援センター等との合同実施など、柔軟な運用が認められています。
リーダー・コア人材研修
都道府県・指定都市(都道府県等)が実施主体となり、地域での学び合いを重視されています。コア人材研修では、受講者が少数になる場合があるため、複数の都道府県等による合同開催も認められますが、地域性を踏まえた実施方法(例:同一県参加者でのグループ分け)が求められます。
都道府県が実施主体となり、研修事業者の指定などを行うことが妥当とされています。
4. 研修の具体的運用に向けた方向性
全ての研修を同時期に本格実施するのではなく、段階的に進めることが適当とされています。
研修受講の取り扱い
基礎・実践研修については、職種や実務経験を問わず、全ての支援者が受講することを基本とします。
既存の研修による一部免除については、現行では内容の標準化が困難なため導入せず、本格実施当初は全ての研修で免除を認めない方針ですが、将来的に再検討の余地を残しています。
研修の修了評価
受講者の「理解度」を評価基準とし、リーダー・コア人材研修では知識・技能の習得状況の確認を目的とし、試験的な要素は含まず、振り返りやテストなどで確認する方針です。
質の確保を図る実施体制
国は企画・運営の中心となる人材育成を進め、都道府県等は学識経験者や当事者団体等も参画する協議の場を設けます。子供・若者、子育て当事者の意見を反映する機会の設置が重要です。
テキスト・ガイドライン等の作成
標準カリキュラムに基づくテキスト教材等が整備されます。円滑な研修実施のための具体的な取り組みや振り返り・対話・学び合いのポイントを示したワークブック、都道府県等や市町村に期待される役割を整理したガイドラインなども作成されます。
動機づけとなる取り組み
研修効果を高めるため、支援者自身が学びの履歴を振り返られる仕組み(例:ポートフォリオ)や、基礎・実践研修では受講者が自ら受講順序を考えられる柔軟な運用を検討します。
事業者の主体性を高めるため、研修に取り組んだ成果の「見える化」(例:修了者数の公表、ロゴマークの創設)を検討します。報酬上のインセンティブについては、慎重な検討が必要とされています。学び自体が動機づけとなることが最も重要とされています。
また、国が定める研修体系であることから、転居等によって別の都道府県に移った場合でも受講状況を引き継ぐことができるような仕組みの必要性も挙げられています。