成年後見制度のあれこれ 第9回 死後事務の取扱い方
2025/04/30
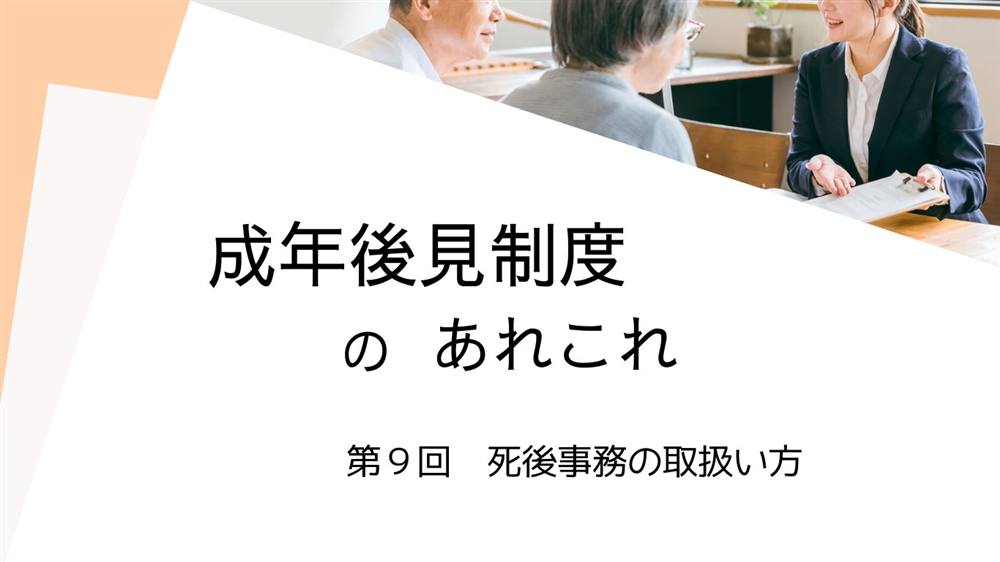
|
【執筆】 |
前回はエンディングノートと遺言を取り上げましたが、今回は死後事務のお話です。
死後事務もすでに就任直後から始まっていると言えます。つまり、いつか必ず人は亡くなるわけですから、後見支援計画として、相続人調査から被後見人等の方々の意思確認・方針など、来るべき日に備えた活動があってその日を迎えるということになります。
時として就任直後や審判申立中にお亡くなりになることもありますが、基本的には就任からお亡くなりになるまで、ある程度の時間があります。最後まで被後見人等の方々に寄り添う後見人の責務として、死後事務は存命中以上に大事な業務であると思います。
死後事務の内容と範囲
死後事務とは、被後見人等の方々がお亡くなりになった後に必要となる一連の事務手続きや対応のことです。これらは法律上、原則として成年後見人の職務とは区別されています。
なぜなら、本人の死亡をもって成年後見契約や後見人の権限は終了するため、死後事務を行うには別途契約や委任、あるいは遺言等の明確な根拠が必要であるためです。このため、任意後見契約では併せて「死後事務委任契約」を締結しておくことで、本人の意思に基づいた死後の対応が可能となり、また法定後見ではご遺族となる相続人と同様に契約を結ぶことで、その業務が可能となります。
なお、この契約を結ぶかどうかは後見活動とは全く別のことで、結ばないことも多いのではないでしょうか。結ばなかった場合、亡くなられた後のことは原則としては全て相続人の方にその権限と共に業務も引き継がれることになります。
では、身寄りのない方や親族が関わりを拒否している方の場合は誰がその役割を果たすのでしょうか? この点は後半で触れたいと思います。
死後事務の具体的内容
成年被後見人等の方がお亡くなりになった後の対応としては、まず(当たり前ですが)家庭裁判所に電話で連絡することです。この時点で、成年後見人は既に「成年後見人であった者」となっており、残る業務は主に次の4つです。
①東京法務局への後見終了登記の申請
- 死亡届の写しをつけて申請します。
- ②管理計算業務(民法第870条)
前回の定期報告終了から死亡届までの収入と支出を計算して、財産の流れを明らかにし、財産目録を作成します。被後見人等の方の死亡から2か月以内に管理計算を行い、家庭裁判所へ報告します。 - ③相談財産引き渡し業務
管理計算が終わり引き渡し財産を確定したら、相続人の一人に残余財産を引き渡します。 - ④家庭裁判所への終了報告
上記の①~③について、お亡くなりになった日から2か月以内に報告します。
以上が、死亡後の事務として後見人等に課せられている業務となります。これらは必ず行うべきものですが、以上の内容を読んで「何だ、そう難しくないな」と思われた方もいるかもしれません。
実際のところ大変なのが、相談財産引き渡し業務(身寄りのない被後見人等の方や親族が関わりを拒否している場合)と、「応急処分義務」(民法第874条による第654条の準用)への対応です。
「応急処分義務」とは、民法第654条において定められている、急迫の事情がある時は、成年後見人等であった者のために必要な範囲で後見の事務の処理が定められています。
被後見人等の方々はご本人に身寄りがない場合や親族がいても関わりを拒否している場合も多いため、この「応急処分義務」により、成年後見人等であった者が病院や施設の求めに応じて死亡確認の立会いや葬儀社への連絡、ご遺体引き取りの依頼といった死後の対応しているのが実情です。
なお、2016(平成28年)年の成年後見事務円滑化法により、家庭裁判所への許可申立の上で、成年被後見人の死亡後のご遺体の火葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為を成年後見人が行えるようになりました。
ただし、本規定は「成年後見人」に関してのものであり、「保佐人」「補助人」等は、これまで通り「事務管理」や「応急処分義務」による対応になります。
死後事務の具体例
1.死亡届の提出
死亡の連絡を受けた際は、まず深夜・早朝などでも病院等に駆けつけ、確認を行います。
その後ご遺体の引き取りが必要となりますので、葬儀会社の手配と死亡届の提出も必要となります。ちなみに、葬儀を行う場合は葬儀会社が死亡届を代行提出してくれますが、成年後見人は家庭裁判所に許可を得た場合でも、葬儀の執行までは認められないことがほとんどです。したがって直葬(葬儀を行わず、火葬と埋葬のみを行う)になりますので、死亡届の提出も後見人が行う場合が多いです。
2.遺骨、遺留品の取扱い
また、ご遺骨や遺留品の扱いも難題です。これもやはり身寄りがない場合や親族が関わりを拒否している場合に発生することですが、まずご遺骨については、遺骨だけは引き取るという親族(相続人等)の方もおられますので、その場合は火葬後に直接お渡しするか、また遠方の場合はゆうパックで郵送の手配をします(ゆうパックのみ可能。他の民間宅配便等は不可)。
引受先がない場合は、無縁墓等への納骨となります。遺留品については、こちらも引き受け先があれば良いのですが、やはりない場合が多く、その場合は残念ながらほぼ処分となります。
3.相続財産の取扱い
最後に相続財産についてです。預貯金等が大部分ですが、遺骨や遺留品は引き取らなくとも、財産は引き受けられる方はおられます。
業務的には引き受けていただいた方がありがたいので、その場合はその方にお渡しして問題なく終了です。問題は相続人がいない場合と、相続人はいるが連絡がつかないあるいは財産受け取りも拒否される場合です。
前者については、相続人がおられないため「相続財産清算人(相続財産管理人)」の申立となります。ケースとしては少ないですが、この場合予納金が必要なので、その金額を事前に用意出来ているかが鍵となります。
後者についての方がより難題です。この場合は様々なケースが考えられ、一概にどうするとは言えない部分があります。その都度状況に応じて、関係者と調整しながら解決策を検討していくことになります。
これらの前提として全て共通するのが、これらを執り行うには、一定程度の金銭が必要ということです。
お亡くなりになる最後までお金の話ということで嫌になりますが、これが実情でもあり、本当に大切なことです。そのためにも、後見人としては、生前中から適切な財産の確保と収支計算が重要になってきます。
