成年後見制度のあれこれ 第8回 エンディングノートと遺言書
2025/04/18
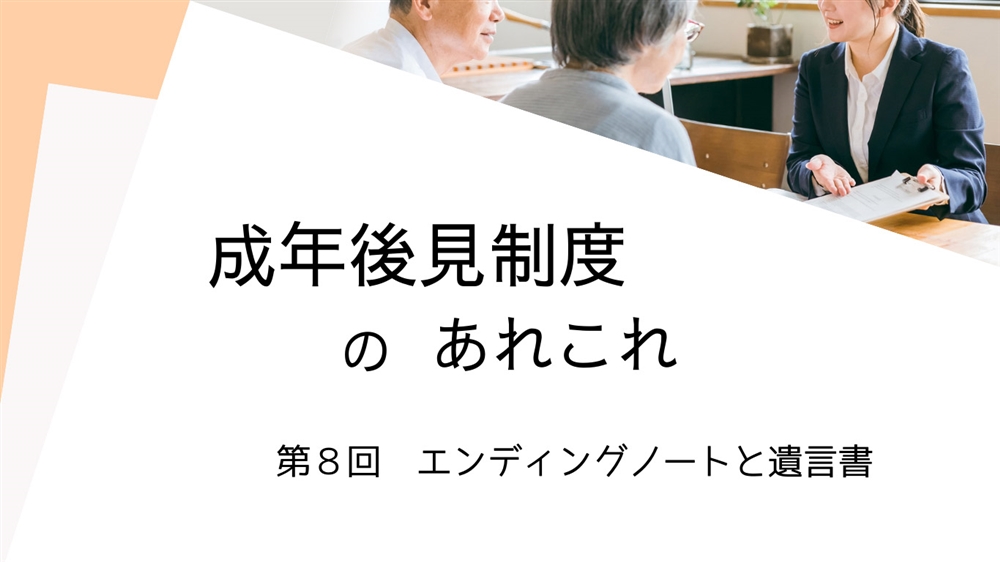
|
【執筆】 |
2025(令和7)年3月27日、第9回地域共生社会の在り方検討会議が
開催されました
。日常生活自立支援事業の見直し(新日自事業(仮称))や中核機関の法的位置付けなど、成年後見制度に関係する内容が出ていますが、参考資料として引き取り手のない遺体・遺骨に関する調査も出ています。
厚生労働省が行った初の全国調査になりますが、無縁遺体が年間約4.2万人と、衝撃の結果が出ています。
(参考)引き取り手のないご遺体の数に関する粗い試算
令和5年度の引き取り手のないご遺体の数を、概況把握調査結果をもとに試算したところ、推定約42,000人となった。令和5年の死亡数(1,576,016人、人口動態調査)と比較すると、その2.7%に相当する。
|
墓地埋葬法9条に基づく火葬 |
8,694人 |
|
行旅死亡人法に基づく火葬 |
1,209人 |
|
生活保護法18条2項1号の適用 |
26,138人 |
|
生活保護法18条2項2号の適用 |
5,928人 |
|
合計 |
41,969人 |
出典:「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業報告書」(令和7年3月)
身寄りのない人が亡くなり、引き取り手が現れないまま火葬される……、そんなケースが今の日本で年間4万件を超えています。1人暮らしの高齢者、家族との関係が薄れた方などの増加が背景にあるとみられ、今後さらに増加する可能性があります。
このような方々のうち、エンディングノートや遺言書という形で個人の意思を明確に反映できた方は、いったいどれくらいおられたでしょうか? 頼れる身寄りがいない方々も、人生の最期まで安心して歳を重ね、自分らしく地域で自立した生活を送るためには、事前に意思表明を行っておくことは非常に大事なことだと思います。
そんなエンディングノートと遺言書が、今回のテーマです。
終活と成年後見人
終活という言葉が登場して以降、今では世間一般に違和感なく浸透しています。成年後見人の間においても、利用者の方々への意思決定支援として重要な事項となっています。
終活は、それまではどちらかと言えばネガティブなものとして扱われることの多かった「死」に関連・付随する行動を、「残りの人生をより有意義に楽しく生きるための活動」とポジティブに捉えるということで、成年後見活動において積極的に関わるべきものであると思っています。
ただそうは言っても、終活となればその範囲は幅広く、また意思の把握が困難な場合も多いことから、後見人にとっては非常に難題です。ご年齢を考えると長い時間(期間)をかけられないこともあり、筆者はまず最低限の活動として「お墓はどうしましょうか?」ということだけは確認しています。
この確認の時期ですが、審判が降りて初回面談等を行う時期にもよりますが、本当に真っ先に確認しています。これはどのような被後見人等の方でも変わりません。
筆者が活動を開始した頃は、研修などで「成年後見人の辞任はご利用者様がお亡くなりになられた時」と言われていました。つまり後見人に就任したら被後見人等の方々の一生の伴走者になるということです。今後は後見人等も適切な時期で交代・終了がなされてゆくことになると思いますが、とはいえ、人生のいつ終わりはいつ来るか分かりませんので、備えておくことの重要性は変わりません。このための鉄則として、「聞きにくいことは早めに」ということで必ず就任直後に確認しています。自身がお亡くなりになった時のことだけは、後々で信頼関係ができてからだと本当に聞きにくくなるためです。
実務的には、ご本人の戸籍等を取得させていただくなど親族調査を行う必要がでてきます。その中でお亡くなりになった時にご遺骨をどうされるか、お墓をどうするかを事前に聞き取ります。親族がおられる場合、存命中の関わりは拒否される場合でも、ご遺骨だけはお引き取りとされるご親族の方もおられます。そのためにも、ご本人の意思を把握することは非常に大事なこととなります。
ご本人の意思確認がないままその時を迎えると、不幸な結果になってしまうことが少なくありません。
エンディングノートと遺言書
エンディングノート
エンディングノートとは、ご本人に何かあったときに備えて、親族等が様々な判断や手続を進めるために必要な情報を残しておくためのノートです。
エンディングノートについては書籍等も含め色々なものが出ておりますので、ご本人にとって良いものを選ぶとよいでしょう。参考までに、エンディングノートそのものではないですが、筆者が良いと思って活用させていただいているのが、おおた成年後見センターの「 老いじたくパンフレット 」です。
おおた成年後見センターは各区市町村に設置された「成年後見制度推進機関」の一つということもあり、成年後見人としては業務全般も含めてとても参考になります。エンディングノートは本来、ご本人が内容を理解した上で自由な意思により最良の方策を選んでゆくものですが、実情としては、被後見人等の方々は判断能力が不十分なため、後見人等が本人の意思を尊重した上での代行決定(後見活動記録としての代行記入によるエンディングノート)になりがちです。
その解消のためには代行決定から意思決定支援へのパラダイムシフトが必要なのですが、まだまだその転換はエンディングノートに限らず容易なことではありません。
遺言書
エンディングノートをもとに、後見人等の方々にとって大事なことを一つひとつ確認してゆくことで終活を進めていくことになりますが、特に相続など財産に関わる部分については、(法定相続によらないならば)遺言書を活用することが出てくるでしょう。
広義ではエンディングノートの内容も遺言ではありますが、遺言書とエンディングノートの違いは法的効力があるかどうかです。形式がしっかり定められている遺言書は、被後見人等の方々の財産分与などについて意思を明確に反映させるためにも、非常に重要になってきます。
このための遺言書としては、公証役場で作成する公正証書遺言が最も良いとされています。被後見人の方でも成年被後見人が公正証書遺言を作成することは可能ですが、作成のためには法律上いくつかの厳格な要件が必要とされています。
法律上の要件(民法第973条)
①事理弁識能力を一時的に回復したときであること
②医師2名以上の立会があること
③医師が立ち会い、遺言者が遺言作成時に事理を弁識する能力を有していた旨を遺言書に付記し、これに署名押印をすること
結論としては、実際に成年被後見人の方が公正証書遺言を作成することは極めて厳しいと言えます。そもそも成年被後見人の方が事理弁識能力が回復したと感じ、本人に遺言作成の強い意思がある場合は、後見解除の申立を家庭裁判所に行うでしょう。
エンディングノートは、前述の通り被後見人の方から口頭で伝えられたものを書き記したものになりますが、成年後見人は身分行為を代理して行うことができないため、遺言書を作成することはできません。よって被後見人から口頭で伝えられたものを書き記したエンディングノートも法的には無効の遺言書になります。
なお、被保佐人や被補助人の方の場合には、意思能力さえ有していれば、上記のような法律上の要件がなくとも、遺言を作ることが可能です。ただ、この場合でもやはりハードルは大きいため、なかなか遺言書の活用ということの機会があっても、作成までには至らない場合が多いように思います。
