成年後見制度のあれこれ 第7回 家庭裁判所の役割と機能
2025/04/15
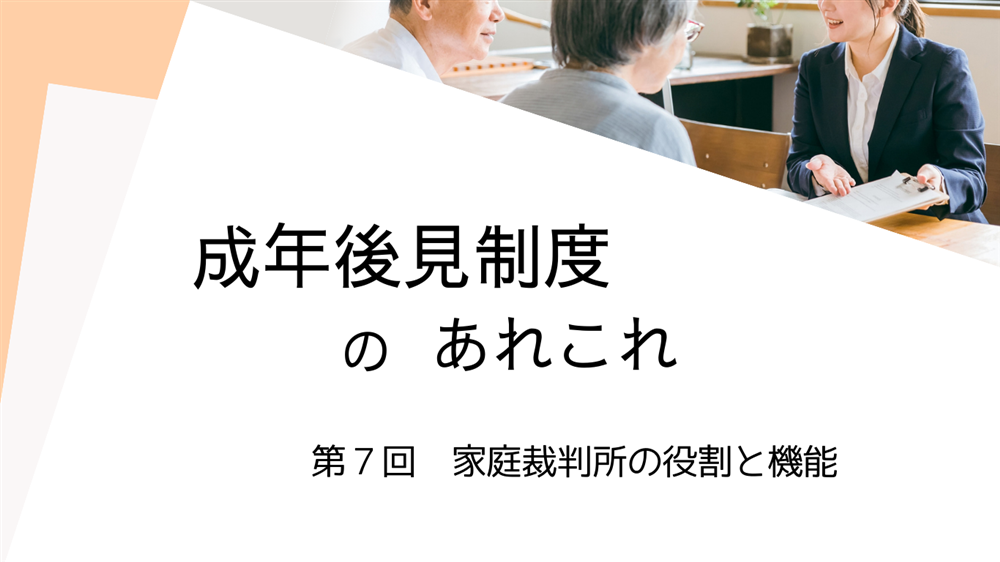
|
【執筆】 |
皆さんは最近家庭裁判所に行かれたことはありますか?
成年後見人としては、選任後に申立書の閲覧や、類型変更および新たな代理権・同意権追加申立てをした際の調査官面接など、活動にあたって出向く必要もそれなりに出てきます。ただ報告書等は郵送なので、用向きがなければほぼ行くようなことはないでしょう。
家庭裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50箇所に本庁が設けられているほか、203箇所の支部及び77箇所の出張所が設けられています(本庁と支部の数は地方裁判所と同じ)。
筆者は、仕事や旅先のついでに時間があれば各地の家庭裁判所を見学しています(成年後見活動にそう資することとも思えませんが……)。裁判の傍聴は一部を除いてできないので専ら庁舎見学ですが、2024年NHK連続テレビ小説「虎に翼」の主人公モデル、三淵嘉子氏が女性初の裁判所長となった新潟家庭裁判所を以前見学したことがあり、ドラマが身近に感じられたものです。
今回は、後見制度上の機関として非常に大事な、家庭裁判所の役割と機能についてです。
成年後見人の監督と指導
後見人等には、広範な代理権・財産管理権が付与されています。
このため権限については常に濫用の危険が内在していることから、その行使が適正に行われているのかどうかを監視し、問題がある場合にはこれを是正させる方策が必要です。
この成年後見人への監視・監督を行うのが家庭裁判所であり、適時に後見人等へ後見等事務の報告や財産目録等を提出させ,これを点検していくことを基本としています。
その過程で後見等事務に問題がある(または問題が含まれている可能性がある)ことを認識した場合には、金融機関に対する調査嘱託や、家庭裁判所調査官による事実関係の調査等を行って問題の有無・対応などにつき検討したり、財産の管理その他後見等事務について必要な処分を命じたりします。
場合によっては、家庭裁判所調査官の調査等を経ずに直ちに専門職後見人等の追加選任・権限分掌の措置を講じて財産保全と後見等事務の調査を行い、後見人等を解任することもあります。さらに後見人等の不正事案については、業務上横領、背任等の刑罰法規に触れるものとして、家庭裁判所として刑事告発を行うことがあります。
残念ながら、専門職による横領事件は弁護士・司法書士・社会福祉士ともに発生しています。このため近年では、専門職団体による所属会ごとの自主的な会員への監督・指導ということで、研修受講の必須化や、所属会へ後見活動の報告などを通じて、問題がある会員への指導等が行われています。
家庭裁判所への報告
監視・監督の方法の基本は、先に述べたように裁判所への報告です。家庭裁判所は基本的に必要と判断した時期にはいつでも報告を求めることができますが、①初回報告、②定期報告、③終了報告(死亡時等)は、必ず行う必要があります。
①初回報告
審判確定から1ヶ月以内に提出します。
この時に特に大事なのが、財産目録(初回報告用)です。申立時には不明だった新たな財産がわかる場合もあり、就任当初は何かと大変な時期です。
②定期報告
後見人は毎年1回,所定の時期に裁判所に対し,後見事務の状況を報告しなければなりません。この時期は個別に決まっており、審判確定月の当月25日までに前月までの1年分の報告を行います。
この時期に大事なのは、後見等事務報告書(定期報告)や財産目録(定期報告用)もそうですが、報酬を請求する場合は、報酬付与申立書の提出でしょうか。
やはり専門職としての支援ですので、正当な報酬をいただくことは必要です。なお、報酬は本人財産からいただきますが、本人に財産がないなど報酬が見込めない場合(いわゆる無報酬案件)でも申立ては行います。なぜなら、成年後見制度利用支援事業による自治体からの報酬助成や、専門職団体独自の報酬助成を受ける場合には、この裁判所への申立てが必須なためです。
③終了報告(死亡時等)
被後見人等の方がお亡くなりになれば、当然に後見等契約は終了します。入院費や施設費などを支払った後、2か月以内に終了報告を行います。
上記報告すべてに共通して言えることですが、期限は厳守する必要があります。
専門職の場合、もし何の連絡もなく報告期限を過ぎるとそれだけで解任事由になります(筆者の周りではまだそのような事態は聞いたことがありませんが)。それだけ期限を守ることはとても大事です。
この他にも、保険金受領や不動産、株、生命保険等の処分などにより財産状況が大きく変動した場合は、随時報告や連絡票も必要となります。
裁判所の許可を要するもの
繰り返しになりますが、後見人には、本人の意思を十分に尊重し、本人の心身の状態や生活の状況にも十分に配慮した上で、被後見人等の財産を管理し、本人の身上の保護を図る義務があります。したがって、被後見人等の利益のためにどのようなことをすべきかは、基本的には後見人の責任において自ら判断することとなります。
ただ、①居住用不動産の処分と②死後事務だけは、家庭裁判所が「許可」をした場合に限り行うことができます。
①居住用不動産の処分
被後見人等の方が住んでいた家(土地・建物)を売却したり、賃借して住んでいた部屋の契約を解除する場合は、事前に裁判所の許可が必要となります。処分という言葉で間違いやすいですが、賃貸住宅の解約も対象となります。
なお、介護施設等は居住用不動産に含まれないため、例えばグループホームや有料老人ホーム等から退去し、特別養護老人ホームへ入所する場合などには許可は必要ありません。
②死後事務
民法873条の2第1項第3号に規定されている死後事務(死体の火葬または埋葬に関する契約の締結、その他相続財産の保存に必要な行為)を行う場合、裁判所の許可が必要です。なお、保佐人や補助人はこの申立をすることはできません。
以上、家庭裁判所の役割と機能と成年後見人の実務活動について紹介しました。
これら内容については、『三訂 成年後見実務マニュアル 基礎からわかるQ&A』(2022年6月刊行)が書籍としては最も役立つものと思います。筆者も改定(二訂)版で養成研修を受け、三訂版ではQAの数も改定版の71から81に増加し既項目の内容も充実していることもあり、折に触れて参照しています。会員であれば1割引ですのでぜひ以下からの購入をお勧めする次第です。
・日本社会福祉士会 出版物のご案内( https://jacsw.or.jp/citizens/shuppan/index.html )
