どうすれば実現できる? 意識して望ましい保育を!
2025/10/29
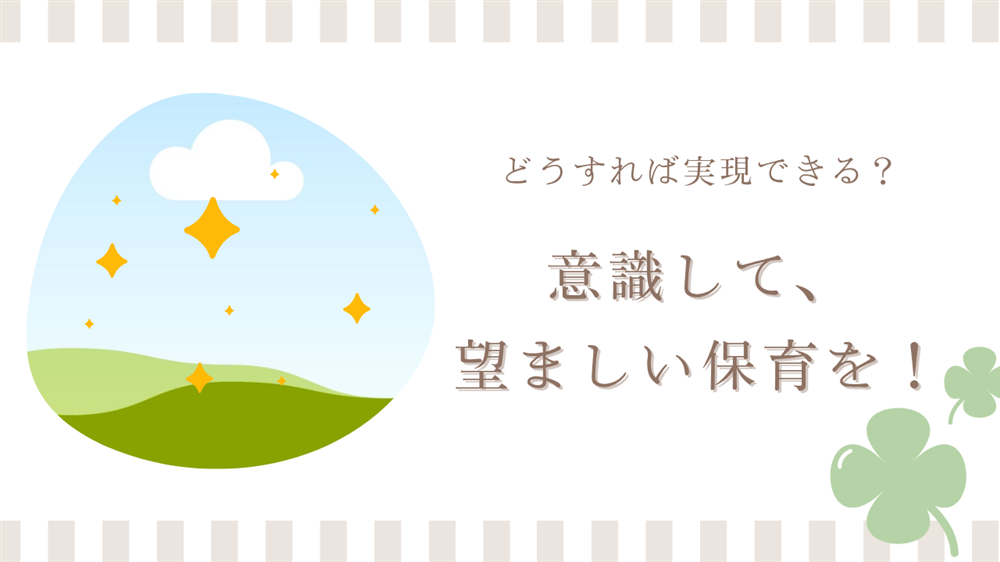
こどもの育ちを真ん中に置く保育へ
保育の現場では、こどもたち一人ひとりが安心して、自分らしく過ごせる環境をつくることが何より大切です。そのためには、日々の活動や関わりの一つひとつにどのような意味があるのかを保育者自身が理解し、意図をもって行うことが求められます。
こどもの姿をどう受け止めるか、何を支えとして関わるかを考えるうえで、国や自治体が示す各種ガイドラインには、保育の基本となる理念や方向性が明確に記されています。それらは保育の枠組みを定めるだけでなく、こども中心の考え方を実践するための指針でもあります。
ガイドラインは現場を導く羅針盤
ガイドラインには、「こどもの最善の利益の尊重」「一人ひとりの発達や個性への理解」「家庭や地域との連携」など、保育を進めるうえで欠かせない視点が示されています。
これらを理解することは、単に法令を守るということではなく、現場の保育者が自らの判断や関わりを支える根拠をもつことにつながります。
例えば、遊びをどう展開するか、生活の流れをどう組み立てるか、職員同士で話し合うときにも、ガイドラインを共通の土台として考え合えば、こどもを真ん中に置いた議論がしやすくなります。チームとして方向性を共有することが、保育の一貫性や質の向上にも結びつきます。
こどもの「今」を見つめるまなざし
ガイドラインの根底には、「こどもを評価の対象としてではなく、成長の途上にある存在として受け止める」という考えがあります。
泣く、笑う、試す、考える——そうした日常の姿すべてが、こども自身の力で世界と出会い、関わろうとする過程です。その一つひとつを丁寧に見取ることが、保育者の専門的なまなざしです。ガイドラインを理解することで、私たちは「どんな行動も育ちの一部として大切にする」という視点を再確認できます。
そこにあるのは、こどもを動かそうとする保育ではなく、子どもとともに動き、感じ、考える保育です。
理念を実践に変えるために
ガイドラインを現場で生きたものにするには、文章に書かれた理念を自分たちの言葉でとらえ直すことが必要です。 「こどもの最善の利益」とは園の中でどういうことか、「主体的な活動を支える」とはどんな環境づくりなのかを、日々の保育を通して考えていく。こうした積み重ねが、こども一人ひとりの育ちを確かに支える力になります。
保育の方向に迷いが生じたとき、ガイドラインを読み返し、理念を実践に照らして考えることは、私たち自身の保育を深める大きな手がかりとなります。ガイドラインを理解することは、こどもの今を大切にする保育を実現するための、確かな一歩なのです。
こうした「こどもの育ちを大切にする保育」の考え方と実践について、より具体的にお知りになりたい方は、以下の書籍をご参照ください。保育現場のエピソードを通して、ガイドラインの理念を日々の実践にどう活かすかを丁寧に解説した一冊です
もっと知りたい方はこちら
本記事は、以下の書籍の内容をもとに編集・作成しております。
