「エデュケーショナル・マルトリートメント」を知っていますか?
2025/09/24
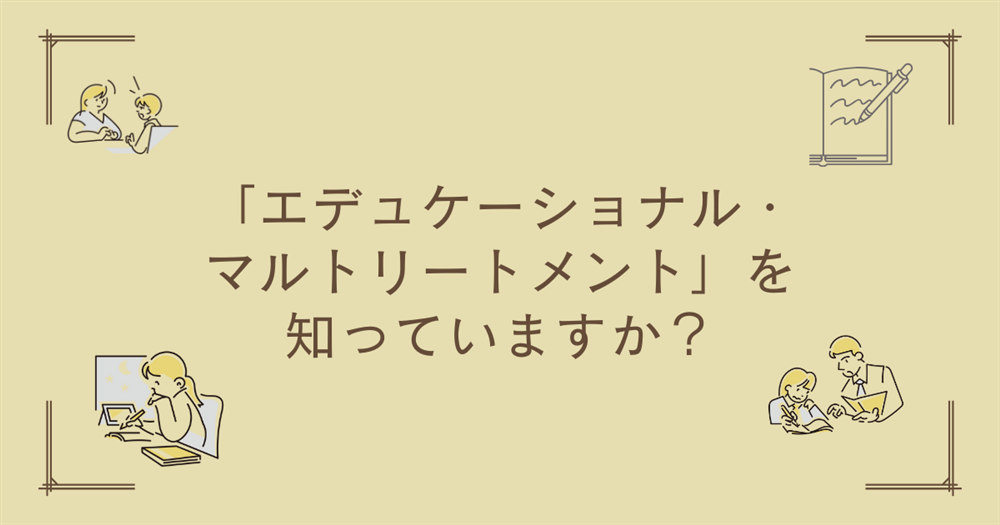
「子どものため」が、子どもを追い詰めていませんか。
エデュケーショナル・マルトリートメントとは
「エデュケーショナル・マルトリートメント」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。エデュケーショナル・マルトリートメントとは、「大人が教育のつもりで行う、子どもの発達や健康にとって不適切な行為」を指し、教育虐待と教育ネグレクトを含む概念です。この行為は、親が「子どもの将来のため」という思いから、勉強や習い事などを子どもに強制する形で生じることが特徴です。
その背景には、戦後の受験競争の激化や核家族化・少子化に伴う子どもへの過度な期待など、日本の社会的・文化的な特徴が存在しています。つまり、エデュケーショナル・マルトリートメントは、個人の問題にとどまらず、社会全体に浸透した「歪んだ教育観」から生じる社会問題であり、社会全体で向き合う必要がある課題といえます。
どこまでが「教育熱心」で、どこからが「不適切な行為」なのか
多くの親は「子どものため」を思い、よかれと思って子どもの学習環境や学習機会を整え、「ちゃんと勉強しなさい」「勉強しないと、あとで困るよ」と声をかけていると思います。または、「いまはまだ、こんなに勉強しなくてもよいのでは…」と迷いながらも「でも、みんな塾に通っているし…。クラスの半分は受験するみたいだし…」と、親も子どもも明確な意思をもたないままに長時間の学習を余儀なくされていることもあると思います。そして、そのような現状に、何ともいえない「モヤモヤ」や憤りを感じている大人は少なくないのではないでしょうか。
「熱心な教育」とエデュケーショナル・マルトリートメントの線引きは、とてもむずかしい問題です。どこまでが「熱心な教育」で、どこからが「エデュケーショナル・マルトリートメント」にあたるのかを考える判断基準として、子どもが自分の意思で行動を選択できているかどうか、心身の健全な発達に有害な影響を及ぼすほどの過度なストレスを感じていないかどうかが挙げられます。つまり子どもが「いやだ」とか「しんどい」と主張できる環境や関係性があるかどうか、子ども自身が自覚していなくても、腹痛、頭痛、体力や気力の減退など、心身の不調が生じていないかどうかがポイントになります。しかし、「教育熱心な親」の行動が子どもに過度なストレスを与えていても、それが将来の糧になる可能性もあるため、判断は複雑です。また、同じ行為でも子どもの特性によって感じ方が異なるため、個別的な状況を考慮する必要もあります。

子どもへの対応:安心して話ができる環境を整える
実際に、エデュケーショナル・マルトリートメントは、子どもの心身にさまざまな影響を及ぼします。不安や抑うつ、腹痛、不登校などの「内在化問題」、頑固さや攻撃的行動、反社会的行動などの「外在化問題」、さらには自己肯定感の低下や「自己疎外」といった「自己発達の阻害」につながることがあります。これらの「問題行動」は、子どもが苦しい環境に抗う中で発するSOSのサインととらえることが大切です。
子どもへの対応では、「意見表明権」(子どもの権利条約第12条)を保障し、子どもが安心して自分の気持ちや考えを表現できる環境を整えることが不可欠です。多くの子どもは自身の権利を十分に知りません。学ぶ機会もほとんどありません。そこで、大人が子どもの権利について学び、伝える機会を設ける必要があります。また、子ども一人ひとりの発達段階や個性、発達特性を理解し、それに合わせた適切な教育環境や合理的配慮を提供することが重要です。特に、発達障害のある子どもには、特性に応じた正しい支援が過度な叱責やストレスを防ぐうえで不可欠です。
保護者への対応:不安な気持ちに寄り添い、支援する
学校や学習塾、その他の習いごとの場において、または学生相談やカウンセリング、療育の場などにおいて、エデュケーショナル・マルトリートメントが疑われる親子に出会ったときは、どのように対応したらよいのでしょうか。
保護者に対しては、子どもの将来や学業に関する不安に寄り添い、責めるのではなく支援する姿勢が求められます。親が子を「一人の人間」として認識し、自立を見守る「子離れ」のプロセスを支援することも大切です。これは、親子の信頼関係を築き、子どもが安心して自分の道を選択できるための土台となります。子どもたちが健康で、良好な人間関係を築き、自分の歩む道を自分で決められる「自己決定力」を身につけることが大切です。

エデュケーショナル・マルトリートメントを防ぐために
エデュケーショナル・マルトリートメントの予防には、個人レベルから社会レベルまで多層的なアプローチが必要です。まず、私たち大人一人ひとりがエデュケーショナル・マルトリートメントへの認識を深め、「子どもの主体性を尊重した学び」が実現しているかという視点を持つことが重要です。
社会構造としては、日本の「競争的な教育環境」の見直しが必要です。少子高齢化が進む現代社会において、競争よりも「協働」の価値を認め、教育システムに取り入れること、学校、家庭、地域が連携し、親も教師も他の大人と支え合いながら子育てや教育を行う「協働性」の意識をもつことで、孤立を防ぎ、多様な価値観が共存する環境を整えることができます。
習いごとの場も、エデュケーショナル・マルトリートメントを緩和する可能性を秘めています。塾などの指導者が、保護者や学校の先生と協働し、第三者の立場で子どもの進路選択や自立をサポートする積極的な役割を担うことが期待されます。支援者は、子どもの問題行動をSOSのサインととらえ、適切な専門機関(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、医療機関など)と連携し、子どもと家族を包括的に支援することが不可欠です。特に、学業成績がよく、目立った問題がない子どもでも、エデュケーショナル・マルトリートメントの影響を受けている可能性があるため、支援者は幼少期からの経験に意識を向ける必要があります。
* * *
従来の児童虐待とは異なる、一見「熱心な教育」や「あたりまえの親心」に見え隠れするエデュケーショナル・マルトリートメントの実態をとらえ、子どものSOSを見逃さない取り組みが求められています。
