子育てがつらい…がんばりすぎずに乗り越える方法5選
2025/09/01
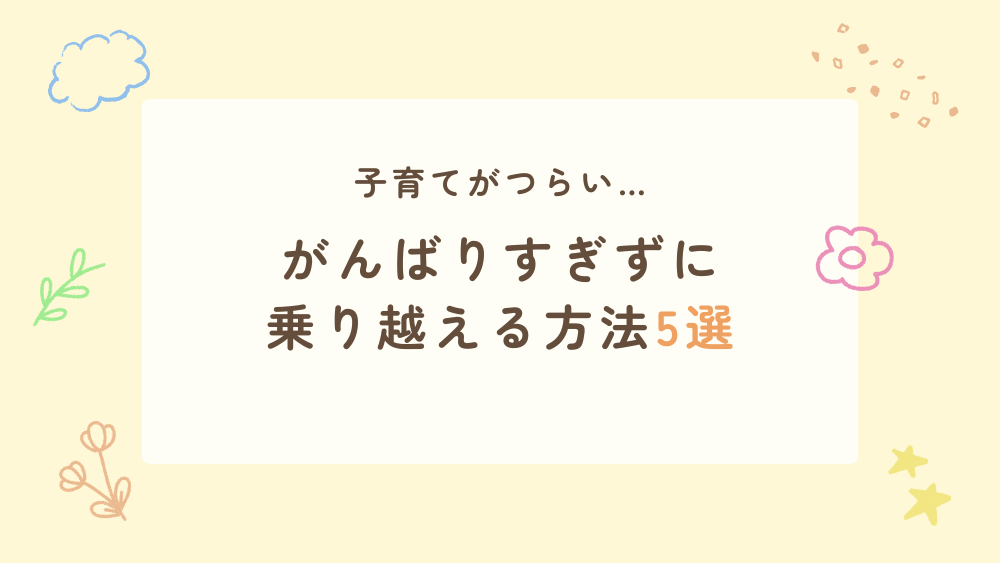
「完璧な育児」を目指さなくても、子どもはすくすく育っていきます。がんばりすぎずに子育ての「つらい」を乗り越える方法を解説します。
子育ての「つらい」はどこから?
子育て中の母親は、「疲労の限界!」「夜眠れない」「目が離せない」といった悩みを抱えることが少なくありません。
これらは、わが子を大切に育てるゆえの悩みであり、子どもの成長に伴って変化していきます。その一方で、一人で育児を抱え込む「ワンオペ育児」は、人類の歴史になかった異常な育児形態であり、心身に無理が生じやすい状況です。
特に産後は、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少により、強い不安や孤独を感じやすくなる時期です。
また、赤ちゃんは「ウルトラディアンリズム」という遺伝子に組み込まれた3~4時間ごとの睡眠・覚醒サイクルを持つため、母親は細切れ睡眠に陥りやすく、疲労が蓄積します。さらに、子どもの成長による体重増加は、授乳や抱っこに伴う腰痛、肩こり、腱鞘炎といった身体的負担を増大させます。
このような状況下では、夫婦関係にも影響が出やすく、夫に対してイライラを感じてしまうこともあります。これは、育児に一生懸命向き合っている証拠ですが、産後のホルモン減少の影響も大きく、誰にでも起こりうることです。
「神話」にとらわれず、肩の力を抜いてOK
「子育ては母親一人でするもの」という意識は、明治時代に政府が富国強兵のために作った「家制度」や「父親は仕事、母親は家庭」という価値観、さらには戦後の「3歳児神話」の影響で広まったものであり、科学的根拠はありません。
むしろ、人類は太古から、母親一人ではなく、父親や家族、集落の人々と共同で子育てをする「共同育児」をする存在として進化してきました。
これは遺伝子に組み込まれた本能的な特性であり、母親が産後に感じる不安や孤独感は、「一人では育児できないから、みんなに手伝ってもらうように促している」本能的なサインだと考えられます。
「3歳児神話」は、平成10年度の『厚生白書』で「合理的根拠は認められていない」と否定されています。また、「母性神話」も、すべての母親が子どもを愛し育てる本能を持つという科学的根拠はなく、育児力は性別ではなく「経験」の差によるものであるとされています。
これらの「神話」にとらわれず、母親が自分を責めず、「60点の子育てでよい」と肩の力を抜いて育児に取り組むことが重要です。子どもは生まれ持った「生きる力」「育つ力」で成長していきます。
がんばりすぎない子育て術5選
がんばりすぎずに子育てをするために、以下の5つの方法を試してみましょう。
1. 家族や周囲に頼る
人類はもともと共同育児をする動物であり、母親一人で子育てをするのは無理があります。父親は育児休暇を活用し、少なくとも産後1か月は家事と育児を担いましょう。
また、祖父母や友人にも積極的に助けを求め、孤立を避けることが大切です。特に、産後の母親は身体を休ませることが不可欠です。
2.自分自身の時間を大切にする
子どもの成長を喜びつつも、自分の時間も大切にしましょう。
フランスの母親のように、罪悪感なく自分の自由時間を確保し、「オフのときはオフ」と割り切る考え方も参考にできます。
赤ちゃんに「待つ」ことを知らせるのも良いしつけであり、母親が自分の生活リズムを保つ上で重要です。
3. 育児用品や便利家電を活用する
抱っこによる身体の負担を軽減するために、抱っこひもやスリング、授乳まくらなどを活用しましょう。
また、家事の負担を減らすために、ロボット掃除機、洗濯乾燥機、食器洗い乾燥機などの便利家電や、食材宅配サービス、家事代行サービスなどを積極的に利用することも有効です。
ワンオペ育児は、「高額な無償労働」。「ここにはお金をかける」と決めたら、家電やサービスを積極的に活用しましょう。
4. 子どもの個性や成長ペースを尊重する
赤ちゃんには生まれつきの気質や個性があり、親がそれを変えることはできません。他の子と比べることは自然な感情ですが、子どもの成長を急がせず、一人ひとりの多様性を尊重しましょう。
遊びやいたずらは、子どもの脳や心の成長に必要な本能的な学びです。危険がない範囲で自由に遊べる環境を整え、子どもが好奇心を満たし、自己肯定感を育めるように見守りましょう。
5. 制度を積極的に利用する
妊娠中から、妊婦健診の助成金や出産育児一時金といった自治体の制度について確認し、活用しましょう。
また、産後ケア事業として、医療機関での母子ショートステイや、助産師による心身・授乳ケア、育児支援などが利用できます。
それでもつらいときは…
産後うつは出産後の女性に多く見られ、コロナ禍以降は4人に1人がうつ状態とも言われています。慢性的な睡眠不足、自分の時間がないストレス、周囲のサポート不足、ホルモン変化などが原因となります。
母親自身は自分の異変に気づきにくい場合があるため、周囲の家族が母親の様子に気をつけ、異変を感じたら早期に専門家への受診を促すことが大切です。
疲労やストレスを一人で抱え込まず、家族や信頼できる人に「つらい」と伝え、助けを求めること、育児の愚痴や悩みを吐き出すことが重要です。
自治体の育児相談会や一時預かりなどの外部サービスも積極的に利用し、一人で抱え込みすぎないようにしましょう。
わが子の命を守るためにも、母親自身が倒れないことが最も大切です。
もっと詳しく知りたい方はこちら
本記事は、下記書籍の内容をもとに編集・作成しております。
