例文あり! 保育の連絡帳の書き方を解説
2025/07/07
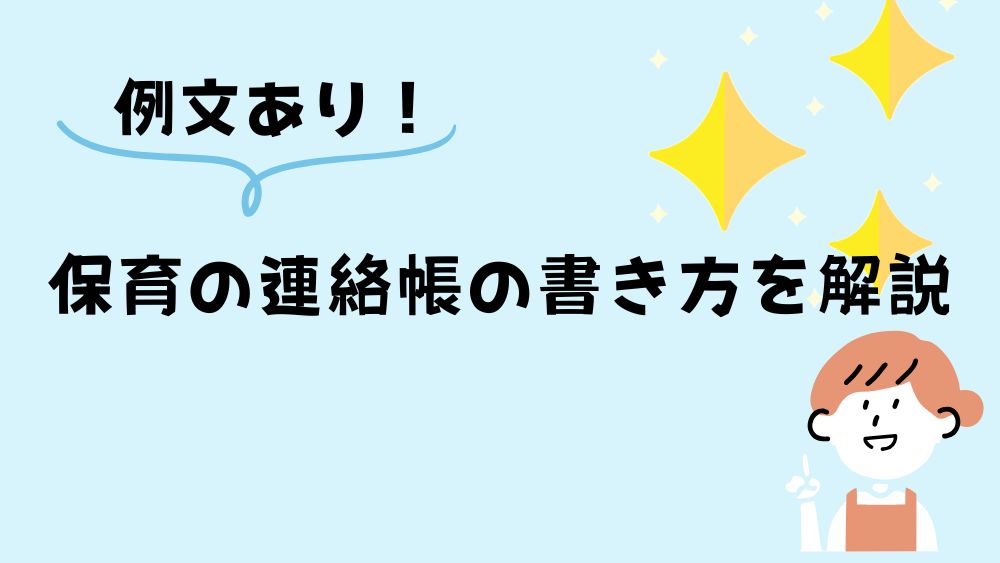
もう書き方に迷わない!日々の連絡帳に何をどう書けばよいのかがわかります。
保育現場において子どもたちの成長を見守るうえで、「連絡帳」は、保護者とのコミュニケーションツールとして欠かせません。しかし、「何を書けばいいか」「どう書けば伝わるか」といった悩みを抱える保育者も少なくありません。本記事では、連絡帳の基本から具体的な書き方、困ったときの対処法までを解説します。
1 連絡帳の基本
連絡帳は、保護者と保育者が「子どもをまんなかに気持ちを分かち合い、喜びを共有できる」関係性を築くためのものです。子どもが園で安心して過ごせるよう、情報を共有し、保護者と保育者の信頼関係を育む役割を担います。
よい連絡帳を作成するためには、保育者が連絡帳の意味と役割を理解し、保護者に伝えること、子どもの具体的な姿をとらえ、保護者の気持ちに寄り添って伝えることが大切です。
信頼関係を育む連絡帳にするポイント
・「キャッチボール」を意識する
まず保護者の記入を読み、それに答えることを意識しましょう。
・子どもの姿を具体的に肯定的な言葉で書く
保護者が子どもの姿をイメージしやすいよう、実際に発した言葉や行動など、具体的なエピソードを通して伝えます。
・「みんな」ではなく、「その子ども」の姿や成長を伝える
保護者が知りたいのは、園でのわが子の具体的な姿です。
・保育者の専門性を取り入れる
保育者の目を通した子どもの姿は、子どもの成長の貴重な記録となります。子どもの発達の姿をとらえて書き、気になる姿には、家庭でもできる対応を添えて伝えましょう。
・保護者の子育てを積極的にほめる
保護者が自分の子育てに自信をもてるような言葉かけを心がけます。
・「丁寧」「正確」「わかりやすく」を意識する
手書きの場合は読みやすさを意識し、文章は口語体を避けます。一文は短くまとめ、「いつ」「どこで」「誰が(誰と)」「何を」「どのように」を押さえて書くとわかりやすくなります。
2 年齢・場面別の記入ポイント&記入例
主な場面ごとの記入ポイントと文例の概要を解説します。
子どもの姿や育ちを伝える場面
・0歳児
一人ひとりの生活リズムが異なるため、24時間の生活リズムを把握し、時間軸に沿って記入します。発達の小さな変化(寝返り、喃語など)、睡眠・食事・排泄の様子、安心して過ごせた様子、機嫌や泣き方の特徴、体調などの気になることを丁寧に伝えます。
・1歳児
周囲への興味・関心が広がり、言葉の発達が著しい時期です。気持ちの動き(安心・不安)、言葉や動作の模倣が始まる姿、生活リズムや食事の変化、「自分でやりたい」気持ち、そして安心できる場面を具体的に伝えます。
・2歳児
自我が芽生え、「じぶんで!」の気持ちが強くなる時期です。トイレが成功した、上手に片づけができたといった成功体験の積み重ね、言葉での意思表示、友だちとのかかわりの芽生え、そして感情の起伏や切り替えの様子を伝えることで、家庭と園で成長を見守ります。
・3~5歳児
心身ともに大きく育ち、仲間とのかかわりが深まる時期です。集団生活での姿勢や社会性、子ども自身の考えや気持ち、挑戦や達成感を感じた瞬間、友だちとのやりとりや遊びの広がり、活動への意欲や集中している様子を具体的に伝えます。
保護者の悩みや質問に答える場面
子どもの発達や子育ての悩みが書かれていた場合は、必ず返事を書きます。
・発達の気がかりに答えるポイント
「言葉があまり出てこない」「目が合いにくい」「落ち着きがない」といった発達に関する保護者の不安に対し、月齢差があることや、園での具体的なかかわり方を伝え、安心感を与えます。
・健康の気がかりに答えるポイント
「お腹がゆるい」「鼻水が続く」「便秘気味」など、子どもの健康に関する情報は最優先で対応します。園での観察結果や対応、看護師など専門職との連携状況を正確に伝え、必要に応じて受診を促すなど、具体的なアドバイスを行います。
悩みや質問への回答ポイント
・共感の言葉を添える
「○○なのですね」「ご心配なお気持ち、よくわかります」など、まずは保護者の気持ちを受け止め、やりとりの土台を整えます。
・子どもの様子を具体的に伝える
保護者が子どもの様子を目に浮かべられるような描写を心がけます。
・肯定的な視点を大切にする
悩みの背景にある子どもの姿を前向きにとらえ、「○○ができるようになってきたところですね」「自我が芽生えてきたのだと思います」など、発達過程に基づいた視点を伝えることで、保護者の気持ちも前向きになります。
・今後の見通しや対応を共有する
「今後も気をつけて見守っていきます」「必要があれば一緒に対応を考えていきましょう」など、園と家庭が協力する姿勢を示すことで、保護者の孤立感を和らげ、信頼関係を深めます。
・丁寧な言葉遣いと伝わる表現を意識する
専門用語や曖昧な表現を避け、保護者が読みやすく、理解しやすい言葉を選びます。
3 記入に困ったときは?
連絡帳を書くうえでよくあるお悩みと、その解決のヒントを紹介します。
・書くことが思いつかない/同じ内容ばかりになる
子どもの小さな変化や成長を見逃さずとらえ、日々の感動や発見を伝えましょう。子どもたちの姿を見て感動や驚きがあるはずです。保育者同士で語り合うことも役立ちます。
・子どもの姿を言葉にできない
本を読んだり研修に参加して専門性を高めることで、子どもの姿や内面がよく見え、言葉にできるようになります。クラスや園全体、同僚と子どものことを語り合う機会をもつとよいでしょう。
・ネガティブな内容の伝え方が難しい
子どものけんかや体調不良などのネガティブな内容は、一人で抱え込まず、主任や園長、看護師などに相談することが重要です。連絡帳では、読み手が書き手の意図と違った印象で受け取る可能性もあるため、慎重に伝え方を検討しましょう。
・保護者のコメントが長く返信に困る
保護者は聞いてほしいことがたくさんあるため、コメントをしっかり読み込み、どの部分に説明を求めているのか、一番必要なことから返信しましょう。
・外国籍の家庭とのやりとりが難しい
日本語の読み書きに困難がある家庭には、やさしい日本語で簡潔に書き、絵や写真などを取り入れる工夫が有効です。
もっと知りたい方に! おすすめの書籍
本記事の内容は、下記書籍の内容をもとに編集・作成しております。
