精神保健福祉士 わたしの合格体験記(第3回)
2025.08.27

今年の合格者にご登場いただきました。
ペンネーム:ツバキさん(昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科令和7年卒業)
「ネームの由来は私が好きな競走馬です。当てたらすごい」
受験の動機
医療系ドラマ
子どもの頃から「コード・ブルー」や「ドクターX」など病院を舞台にした医療系ドラマが好きで、そこに出てくる医師や看護師のような人たちをいつか実際に見てみたい、自分も一緒にそこに居てみたい、そんな漠然としたあこがれがどこかにあったと思います。医療機関で働くことに惹かれたのは、きっとそのあたりです。
OLはちょっと
中学のときに将来これだけはないと思っていたのは、会社の中で働く女性事務職いわゆるOLでした。あくまでイメージですから現実は違うかもしれませんが、日常の中に「変化がない」ように思えて、自分は日々変化がほしい、だとすると何か専門の資格があるとよいのではないか、そんなふうに考えたのが資格を取ろうと思ったきっかけです。
資格取得+心のケア
「資格取得」を考え始めた時期に、身近な人が心を患うという出来事がありました。私が小さかった頃は元気だった人がそうではなくなっていることに、どうしたんだろう、なぜだろうと思い、資格も探しているなかでやがて知ったのが精神保健福祉士でした。最初に知ったのは社会福祉士のほうで、こちらのイメージは市役所とかの窓口で何でも相談にのってくれる人、精神保健福祉士のほうは「心のケア」などもう少し医療寄りでした。2つの資格取得を心に決め、大学は自分の学力と家からの通いやすさも考えて選びました。

受験勉強
努力に目覚めた中学3年
自信をもっている人はかっこいい。子どものときにそう思ったのは、先のドラマの影響があったかもしれません。自信をつけるためには「努力」をしなければならない。そう思って勉強に取り組み始めたのは中学3年のときでした。中学2年のときにオール3だった成績がオール4~5に変わり、性格のほうもそれまでの人見知りがなくなったようでした。今、振り返ってみると、自分に自信をつけることで堂々と人前に立ち、話すことができるようになったのだと思います。以上は、勉強の話をするときの私の原点です。
小テストでモチベーションアップ
私の大学では社会福祉士は1年生から、精神保健福祉士は3年生から専門課程の内容が履修項目に登場し、そして3年生になると過去問を使った小テストが定期的に行われる、という具合に、わりと早い時期から国家試験に関係する内容を学びました。小テストの頻度は週1回、学科の学生数は約40名いて、結果は順位をつけて学生番号が実習室に貼り出されました。この小テストでトップを取りたいと思い、それならと意識的に取り組み始めたのが受験勉強としてのスタートでした。目的をもってやるとこれが楽しく、結果もだいたいトップ10に入ることができました。トップを取ったときは嬉しく、自己満足ではありましたが間違いなくモチベーションの素になっていました。

単語帳=拾い出しとまとめと暗記
中学高校の受験勉強のときから暗記するのが得意で、表などもそれぞれの位置を記憶しながら丸暗記していました。この勉強スタイルは今回の資格試験でも取り入れました。単語帳を使って、①重要と思った用語を拾い出す、②その用語の意味を短くまとめる、③丸暗記する、が基本的な手順です。用語の拾い出しは科目単位ではなく、全科目横断かつ用語の並びをランダムにして、規則性や関連性ではわからないようにします。用語の意味は自分で理解しやすいように作るので、まとめる作業そのものが勉強になります。丸暗記は、単語帳のどちらの面からも(用語からも意味からも)できるようにする、これで万全になります。単語帳をばらして用語をシャッフルする、苦手だけを残して特訓するなど、使い方も工夫しました。通学の電車の中やスキマ時間にも活用できたので重宝しました。

声に出して読む
どうしたらいちばんよく覚えられるかといったら、これでした。先ほどの単語帳や、テキストであれば大事なところにマーカーを引いて箇所を特定してから声に出して読む。読むと頭に入ります。こうした勉強法もあって、私の場合、勉強だけは友達と一緒にするということはなく、一人でやっていました。覚えづらい内容も、何度も読むとそれだけ頭に入りやすくなります。カタカナの人名など自分にとって覚えるのが苦手なものは何度も声に出すようにしていました。

「日記」のすすめ
試験前の1月から毎日、日記をつけることにしました。やろうと思ったのは、勉強のために自分一人で過ごす時間が長くなり、何となくひまを持て余したからです。内容は何時から何時まで何をやってどうだったか、どう思ったか、どんな一日だったかなど。始めてみると、日記には達成感のようなものがもてる効果があることに気がつきました。振り返りそのものでもあるので、明日をどう過ごすかをそこから考える効果もあったと思います。とくに受験期間の後半はメンタル面で行き詰まりやすくなるため、そこを調整してくれる意味で有用でした。おすすめです。
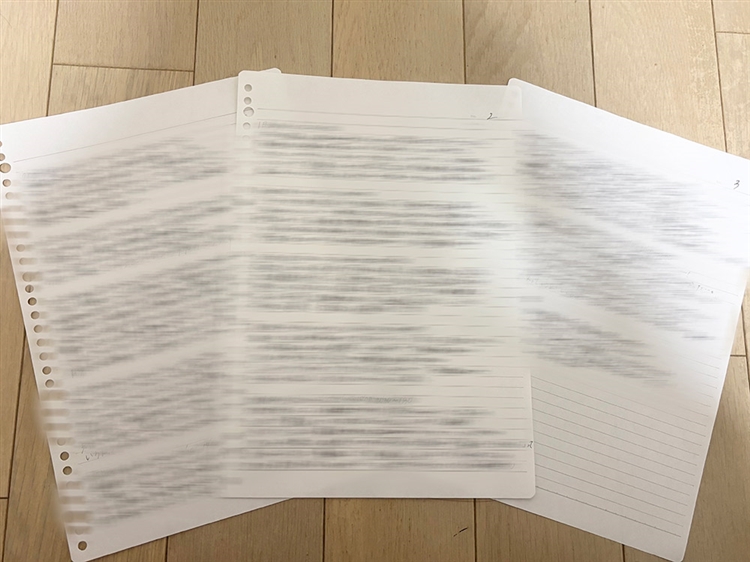
試験の手応え
当初の目標どおり、精神保健福祉士と社会福祉士のダブル受験で臨みました。精神専門は簡単で、48問中間違えても4問と確実な手応えがありました。一方、共通科目と社会専門は難しいというより解きづらく、これまでの試験の傾向とはずいぶん違うと感じました。ただ、この内容ならみんなわからないから大丈夫とも思い、答え合わせも合格圏と思える得点でした。2資格の合格を知ったときは、大丈夫とは思っていましたが嬉しかったです。たくさん勉強してきたことが報われたんだと心から思えました。
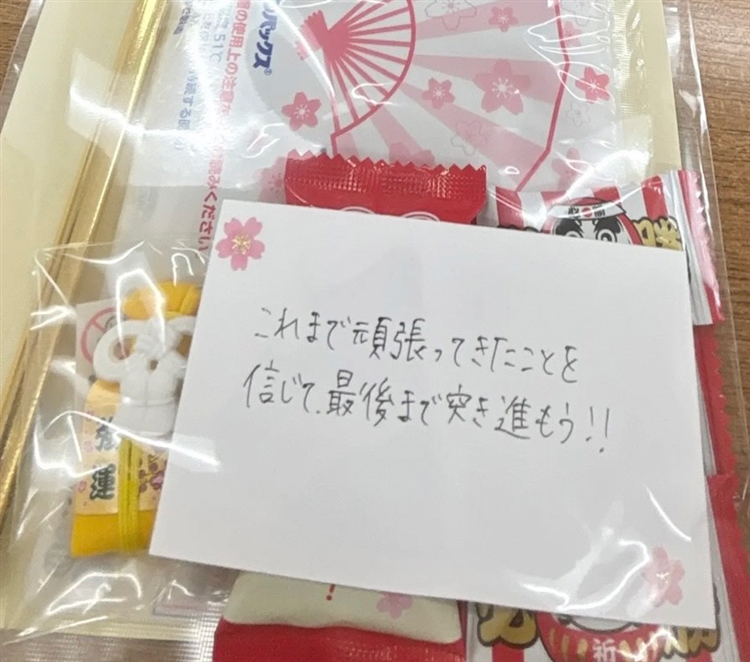
私が目指す精神保健福祉士
今私が働いているのは、精神科病院の精神科救急病棟です。はじめの志望動機で紹介した3点(病院で働きたい、日々に変化がほしい、資格を取って心のケアに携わりたい)をすべて満たした環境にいます。中学3年の一念発起から高校受験の成功体験がきっかけとなって人と話すこと、人にかかわることが好きになり、いずれそういう仕事に就きたいと思ってきました。それが実現できて幸せです。新しい人や新しい考え方との出会いがあり、毎日に発見があり、毎日が勉強です。この仕事を続けながら、昔ドラマで観たような世界が自然と重なっていったらすてきだなと思います。新しい発見を自分自身の新たな目標に結びつけられるように日々努力していきます。
