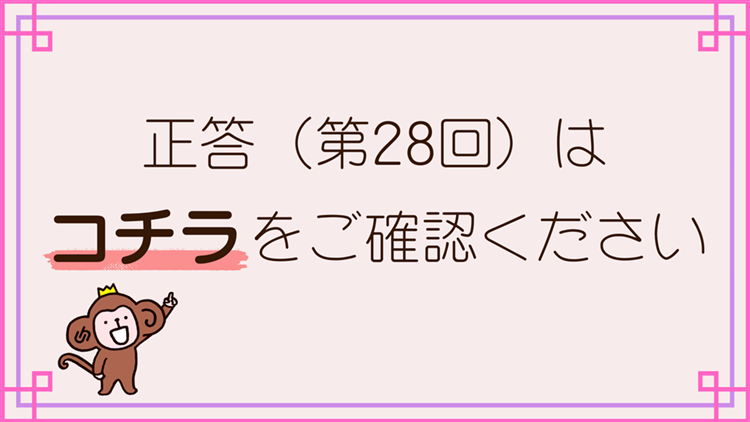◎令和7年度(第28回)ケアマネジャー試験の講評
2025.10.14

2025年10月(第28回)試験の全分野の講評
ケアマネジャー試験の講評
◇はじめに
第28回試験が終わりました。受験された皆さまおつかれさまでした。仕事と勉強を両立しながら受験された方、子育てや介護をしながら参考書と向き合ってきた方など、様々な方がいらっしゃると思います。まずはゆっくりお休みください。
そして頑張ってきた自分にどうぞご褒美を!(贅沢な食事をする、テンションがあがる服を買う、素敵な場所へ旅行するなどなど)
それでは、今回の試験について分野別の講評をします。なお、この講評は合格予想点を出したり、来年の試験問題を予想したりするものではありません。今年の試験の内容の分析としてご参考にしていただければ幸いです。
介護支援分野
例年同様、問題1と2は解きにくいものが出題されました。社会保険と認知症基本法について押さえていた方は解けたと思います。ただし、問題2の選択肢4と5は難問です。地域医療構想をご存知の方は消去法で4を○にしたのではないでしょうか。
サービスを選ぶものや短い単語(項目)など覚えているかどうかの知識を問うものも、昨年同様に多く出題されました(問題12:一般介護予防事業、問題13:介護サービス情報の公表項目、問題16:要介護認定の認定調査を行える者、問題17:要介護認定の有効期間、問題19:課題分析標準項目、問題22:基本チェックリストの質問項目)。問題22の選択肢2「自宅は持ち家ですか」は、真剣に解いているなか、ちょっと肩の力が抜けた方も多かったのでは…。
問題9と10は、第1号・第2号被保険者の基礎的な問題でした。問題14の介護保険審査会については3年連続出題され、やや細かい部分には注意が必要でした。問題18(介護認定審査会)の選択肢4は、サービスの種類を指定できるのは市町村(保険者)です。問題20(サービス担当者会議)の選択肢4(テレビ電話装置等の活用)は最近の動向を反映しての出題で、選択肢5(記録の保存)は頻出なので解けたと思います(アセスメントやモニタリングの記録に保存期間もその完結の日から2年間です)。
問題21(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針)は、頻出テーマです。ケアマネジャーになった際に必要な知識ですので、しっかりと得点してほしい問題です。
事例問題は、昨年と同じく2問でした。利用者主体、ケアマネジャーの勝手な判断は×と認識している方は、迷わず解けたことでしょう。
保健医療サービス分野
今年も全体的に難問といえるものはなく、基礎的で解きやすい出題でした。正答が分からなくても、明らかに×の選択肢を消していく消去法で答えられるものが数多くありました。
特徴的であったのは、問題35の感染症、問題39の臨死期の徴候、問題40のアドバンス・ケア・プランニング(ACP)のような、昨今の現場を重視した出題がされたことです。普段から医療・福祉の時事情報にアンテナを張っている方やターミナルケアに関わっている方は、比較的簡単に解けたことと思います。余談になりますが、問題35(感染症)の選択肢5「エプロンやガウンは、節約のためできるだけ使い回しをする」もちょっと力が抜ける選択肢でしたね。
保健医療サービス分野の問題を解いて改めて感じたことは、せん妄、老年期うつ病、誤嚥性肺炎、腹膜透析、胃ろう、中心静脈栄養、糖尿病、心筋梗塞、関節リウマチ、パーキンソン病など、病気や疾患の症状や留意点を改めて押さえておくのが、とても大切だということです。
また、サルコペニア、フレイル、オーラルフレイル、軽度認知障害(MCI)、パーソン・センタード・ケア、インフォームド・コンセント、パルスオキシメーター、ストーマなどの用語をきちんと理解しているかが、得点を増やすための要因の一つであったように思えます。
以下に、特にポイントと思われる3つを説明しておきますね。
|
□サルコペニア □フレイル □インフォームド・コンセント |
事業者・施設に関する問題は、問題29(訪問・通所リハビリテーション)、問題41(訪問看護)、問題 43(通所リハビリテーション)、問題44(看護小規模多機能型居宅介護)、問題45(介護医療院(3年連続出題))と、昨年より1問減り5問でした。それぞれサービスの特徴(類型)や人員基準の理解を求められるものでした。なお、頻出の介護老人保健施設は、今回は出題されませんでした。
福祉サービス分野
例年どおり問題46~49までがコミュニケーション技術やソーシャルワークなどについて、問題50~57までが事業者・施設の問題(問題50~54:居宅サービス、問題55・56:地域密着型サービス、問題57:介護老人福祉施設(毎年おなじみ))、問題58~60が関連諸制度(問題58:生活保護、問題59:成年後見制度、問題60:高齢者虐待防止法)となっていました。
問題50~57までは、人員基準と運営基準をしっかり押さえておかないと解けなかったでしょう。問題56(小規模多機能型居宅介護(4年連続出題))は、選択肢2と5で迷われた方が多かったと思います。今回の試験で一番の悩みどころでした。正解は選択肢2で、解釈通知(※『令和7年度介護保険六法Ⅰ』(中央法規出版)P.1931「指定地域密着型サービスの事業の運営基準等について」中段では「宿泊サービスの上限は設けず」と規定されています)に出ています。細か過ぎますよね。もしくは、選択肢5の宿泊室が、宿泊専用の個室以外も認められていることを知っていれば、消去法で解けたかもしれません。
今回の福祉サービス分野で新しいこと(事業者・施設の出題について)は、各サービスの「基本方針」が問われたことです。今後この傾向が続くかは分かりませんが、『十訂 介護支援専門員基本テキスト』や『ワークブック』などの参考書をよく読み込んでおかないといけませんね。
関連諸制度では、生活保護が8年、成年後見制度が12年連続で出題されました。過去問を解いていた人は正答できたと思います。問題60の選択肢2は、5つの虐待を正確に把握しておかないと答えられないものでした。「著しい暴言」は身体的虐待ではなく、心理的虐待です。
おわりに
自己採点された方もされていない方も、合格発表日までは真の合否は分かりません。自信のある方は、介護支援専門員実務研修に備えケアマネジメントプロセスを再度勉強するのもよいでしょう。今年は厳しかったという方は、ひとまず少し休んで、また新たな決意でチャレンジをしていただきたいと思います。
最後に一言、『積み上げた知識は、現場に出たときに無駄になりません。利用者さんに寄り添うケアマネジャーとして、常に役に立ちます。皆さま、第28回試験おつかれさまでした!』

竹内 太一(たけうち たいち)
医療法人社団 輝生会 在宅総合ケアセンター成城
居宅介護支援事業所 成城リハケア 介護支援専門員
1995年からソーシャルワーカーとして在宅福祉にかかわり、介護保険制度施行後はケアマネジャーとして相談業務、介護保険事業に携わる。
30年以上にわたり現場実践をつらぬく傍ら、ケアマネジャー試験対策を二足の草鞋(わらじ)として受験対策講師や執筆業に携わる。長年の出題研究をベースとした傾向と対策には定評がある。
○資格
社会福祉士、精神保健福祉士、主任介護支援専門員
○著書
・『ケアマネジャー試験 ワークブック2025 』(分担執筆)中央法規出版
・『ケアマネジャー試験 合格問題集2025 』(分担執筆)中央法規出版
・「2025年度 ケアマネジャー試験 統一模擬試験 」(分担執筆)中央法規出版