おすすめブックス
-
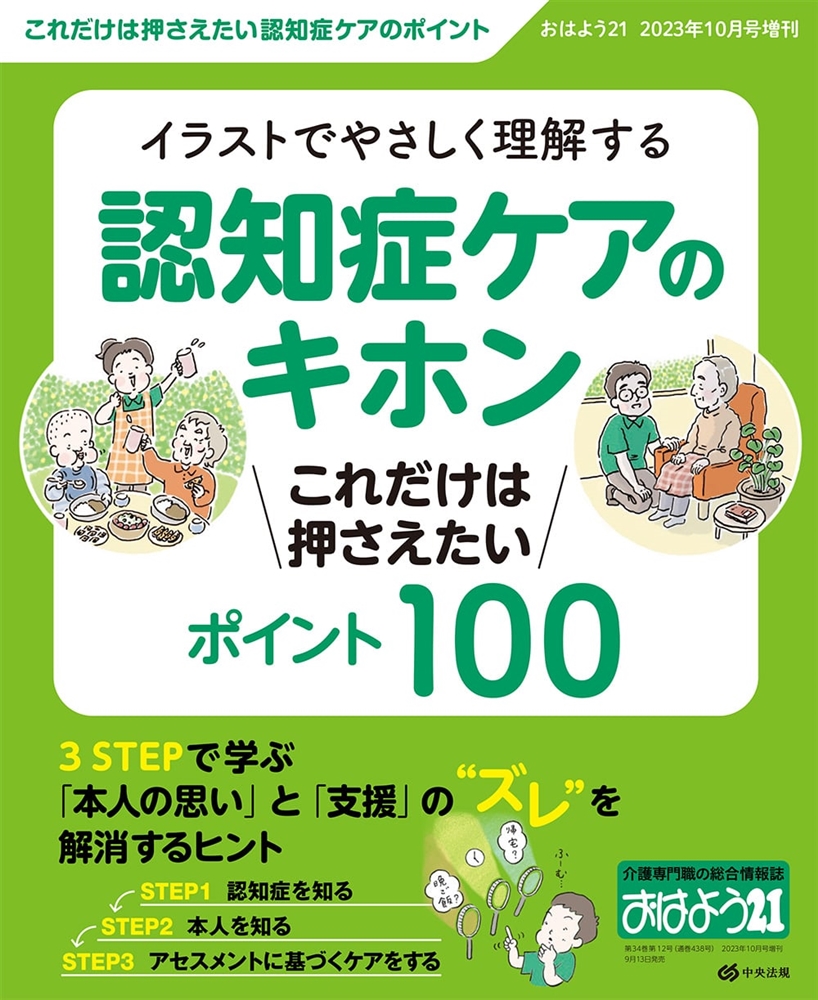
認知症の人への支援では、病気の理解とともに、利用者の「これまで」と「今」を知り、それに応じたケアを行うことが大切です。①病気を知る、②その人を知る、③アセスメントに基づく支援を行うという3つのステップで、認知症ケアの基本をわかりやすく解説します。
おはよう21(2023年10月号増刊) イラストでやさしく理解する認知症ケアのキホン これだけは押さえたいポイント100
-
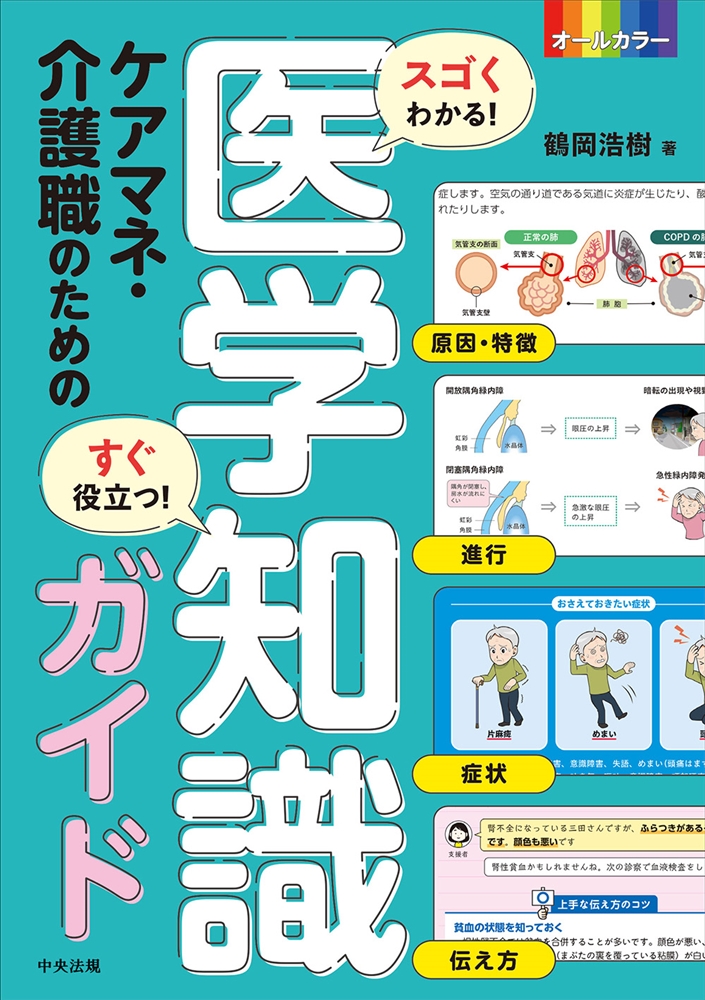
ケアマネジャーや介護職に向け、実務で必要な医学知識をフルカラーで解説。高齢者に多い病気について、症状や病気の原因・特徴、症状の進行、薬の種類や副作用等を図やイラストでわかりやすく整理した。医療職への伝え方は会話例を示したうえで上手に伝えるためのコツを伝授。
スゴくわかる!すぐ役立つ! ケアマネ・介護職のための医学知識ガイド
-
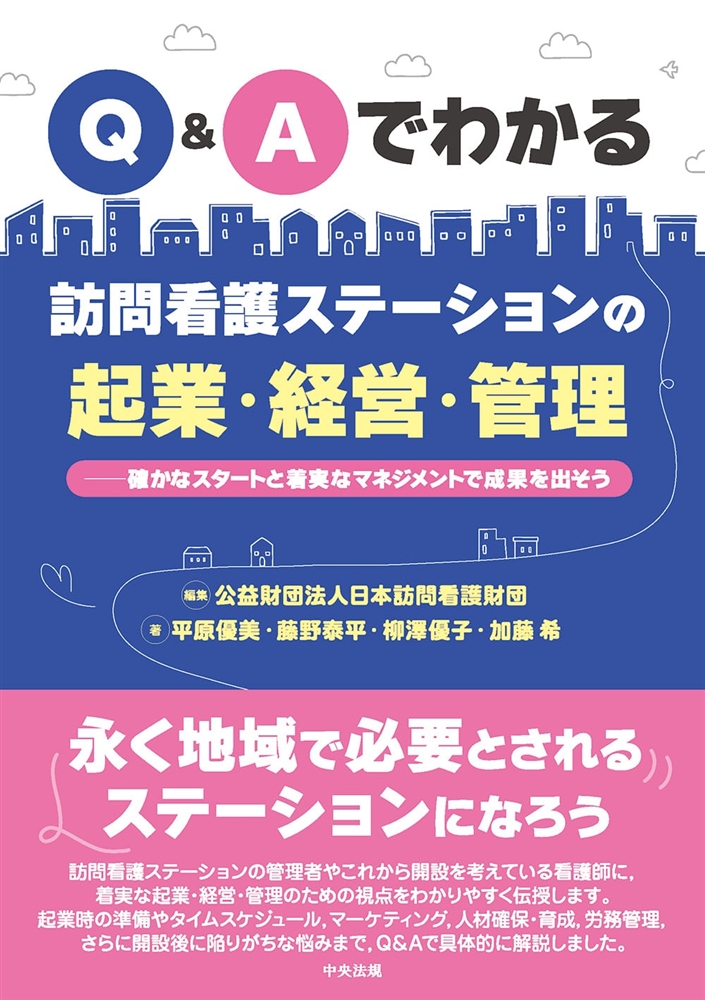
訪問看護事業所管理者やこれから開設を考えている看護師に向け、着実な起業・経営のための視点をわかりやすく伝授。起業時の準備やタイムスケジュール、マーケティング、人材確保・育成、労務管理、さらに開設後に陥りがちな悩みまで、QA形式で具体的に解説した。
Q&Aでわかる 訪問看護ステーションの起業・経営・管理 確かなスタートと着実なマネジメントで成果を出そう
-
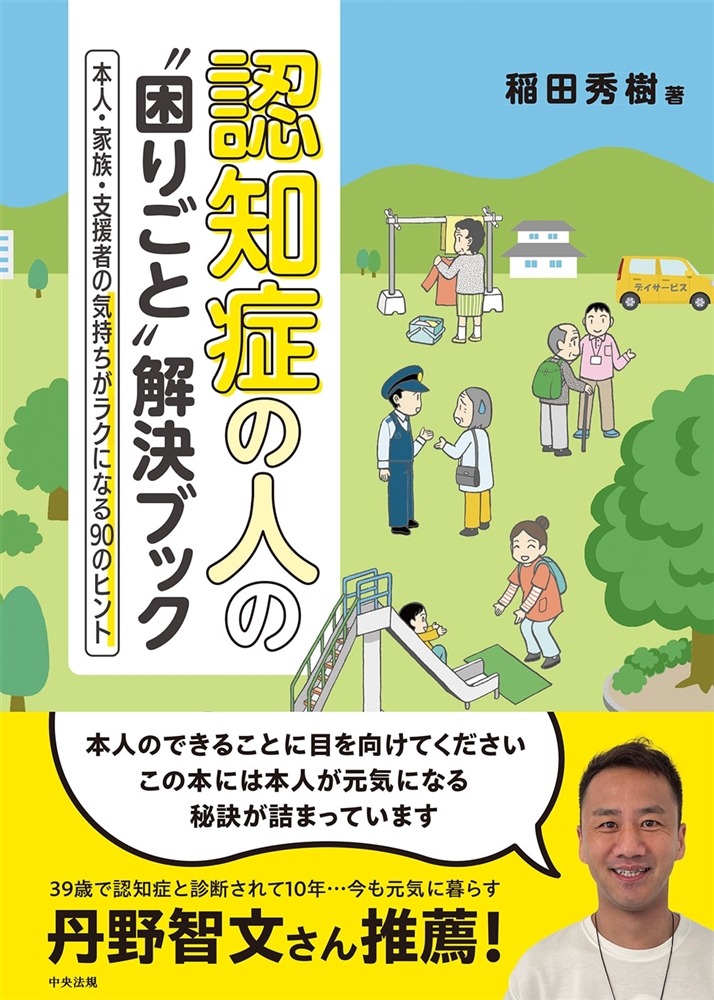
「思い出せない」「大事なものが見つからない」「いま何時なのかがわからない」など、認知症の人が感じる90の“困りごと”を解決するヒントを紹介する。本人は生活のどんな部分に困難さを感じ、それにどう対応すればよいかがわかる。本人、家族、支援者の心を軽くする一冊。
認知症の人の“困りごと”解決ブック 本人・家族・支援者の気持ちがラクになる90のヒント
-
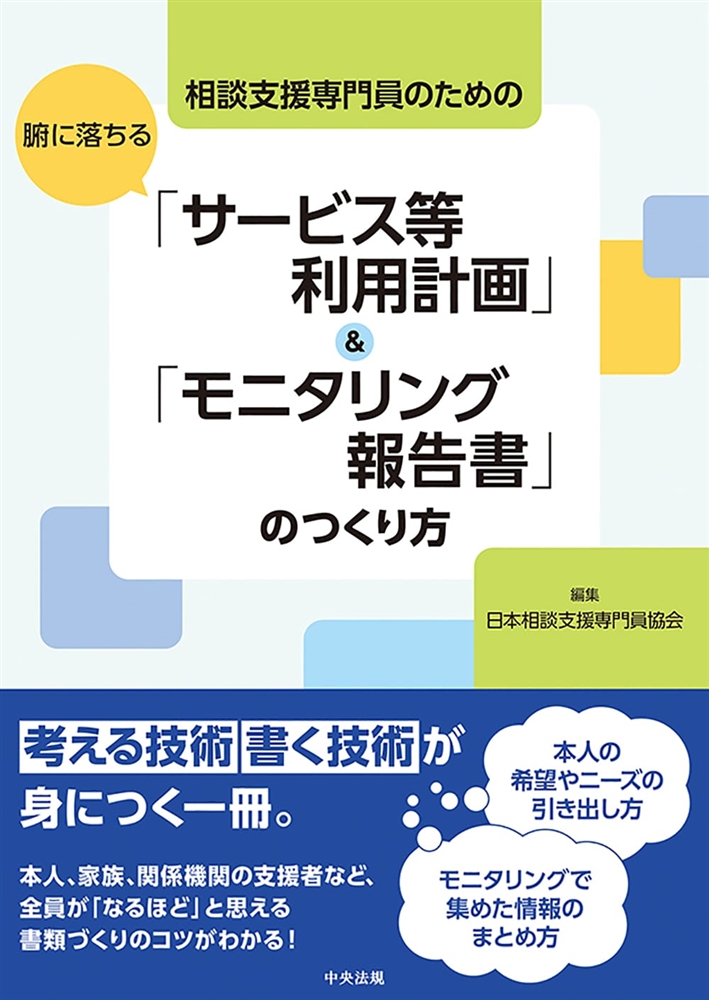
サービス等利用計画、モニタリング報告書の書き方事例集。記入すべき内容を、「良い例」「悪い例」を対比しながら、多様な事例を通じわかりやすく解説した。加算取得の考え方を含め、よりよい支援を実現するための相談支援のプロセス全体を学べる一冊。
相談支援専門員のための 腑に落ちる「サービス等利用計画」&「モニタリング報告書」のつくり方
-

身近で手軽な素材を使った「自立課題」を紹介した大好評書の第2弾。ねらい別に多数の課題を掲載し、個別性に応じたかかわりができる。また、シューボックス、ファイル、マグネットの課題タイプごとに作り方動画をWEBに掲載。現場でよくある疑問もQ&Aで収載した。
TEACCHプログラムに基づく 自閉症・知的障害児・者のための自立課題アイデア集 第2集 目的別に選べる102例
-
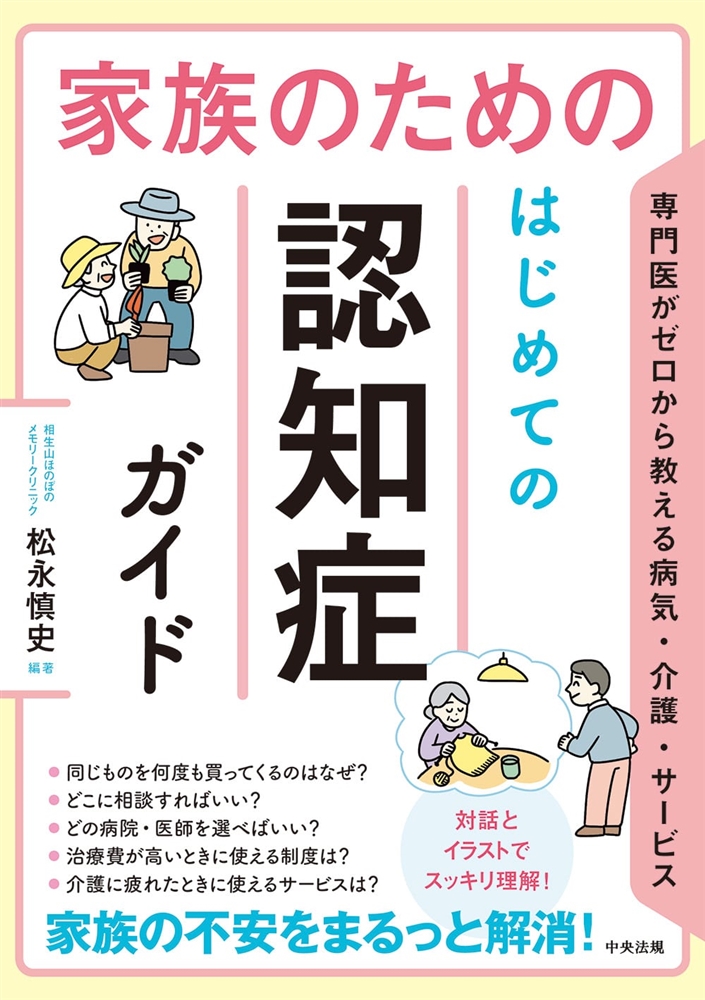
家族が認知症かも?と思ったときまず手に取りたい1冊。病院の選び方・相談先、認知症の種類・症状、本人へのかかわり方、介護保険サービスの種類・使い方、活用できる制度、死亡後の手続きまでフルカラーで整理。家族支援に強い認知症専門医が対話形式でやさしく解説する。
家族のための はじめての認知症ガイド 専門医がゼロから教える病気・介護・サービス
-
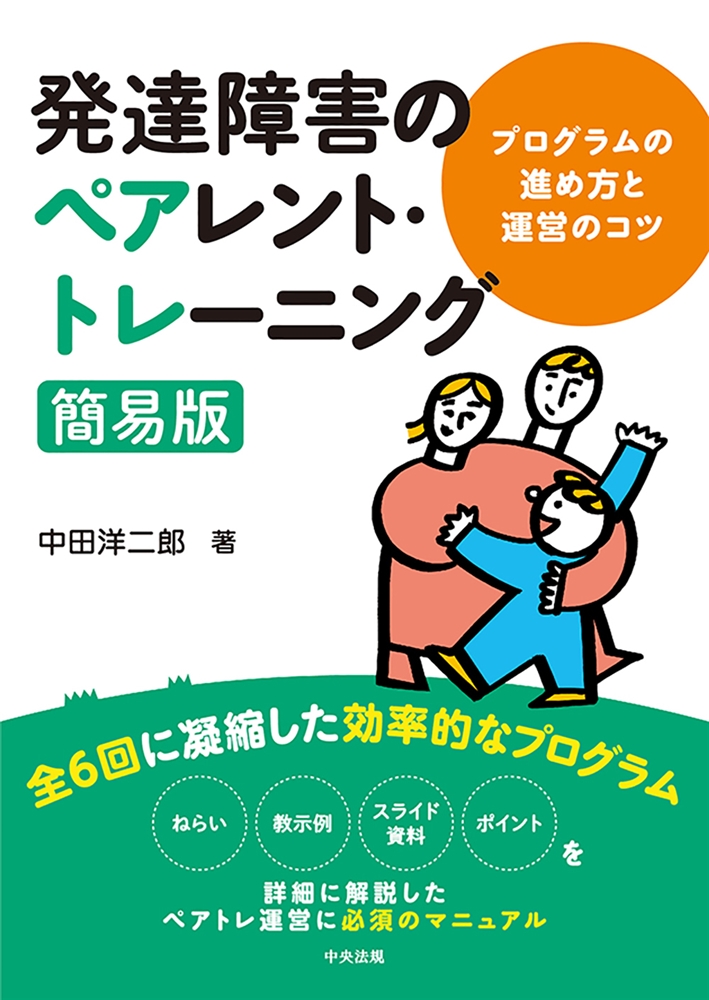
発達障害のある子どもの親が子どもへの適切なかかわり方を身につける「ペアレント・トレーニング」を、効率的に実践するためのマニュアル。通常全10回のプログラムを全6回に凝縮し、ADHDだけでなくASDの子どもにも効果的な内容へと改良。詳細な進め方と運営のコツがわかる。
発達障害のペアレント・トレーニング簡易版 プログラムの進め方と運営のコツ
