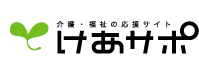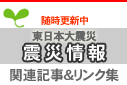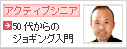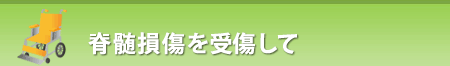
年間約5000名の新患者が発生するという脊髄損傷。
ここでは、その受傷直後から患者およびその家族がどのような思いを抱きながら治療に臨むのかを、時系列に沿ってご紹介します(執筆:丸山柾子さん)。
それに呼応する形で、医療関係者によるアプローチ、そして当事者の障害受容はどのような経緯をたどるのか、事例の展開に応じて、専門家が詳細な解説を示していきます(執筆:松尾清美先生)。
ここでは、その受傷直後から患者およびその家族がどのような思いを抱きながら治療に臨むのかを、時系列に沿ってご紹介します(執筆:丸山柾子さん)。
それに呼応する形で、医療関係者によるアプローチ、そして当事者の障害受容はどのような経緯をたどるのか、事例の展開に応じて、専門家が詳細な解説を示していきます(執筆:松尾清美先生)。
第22回 「第20回 心にちょっぴり灯がともった瞬間」「第21回 大学へはいますぐにでも連れて行きたいくらいです」の解説
高位脊髄損傷の急性期の思いがけない身体の変化を受け入れることの難しさを知ることができる内容です。「丸山さんには、手足に感覚が残っています。肛門の反応もあるので、希望があります……」という主治医が院長へ説明している内容を捉えて、丸山さんは、「当時絶望感の極みにあった自分にとって、それは心にちょっぴり灯がともった瞬間であった。……主治医は院長への説明のかたちで、間接的に私を絶望させまいとの気遣いのメッセージをくれていたように思う。……このときの希望が急性期の私の精神の支えになっていたのである」と記述しています。肛門に反応があるということは、完全麻痺ではなく、不全麻痺で、回復の程度が計り知れないのです。CTやMRIでの診断像はありますが、個々の脊髄の障害程度や回復程度は、この時点では不明なことが多いからです。
急性期の脊髄損傷者は、動かせない身体でベッドに休んでいる間、回復への期待と回復しないことへの不安が入り混じるため、毎日の医師や医療スタッフ、そして家族などとの会話の中で、自分の身体に関する情報や将来への不安を解消するための情報を収集するのです。
排便や排尿についての機能回復は見えなくてわかりません。丸山さん本人の言葉では、「神経因性直腸・膀胱障害……。脊髄損傷がもたらす四肢麻痺から受けた心のダメージに必死に耐えて来た私は、少し遅れて入ってきたこれらに関する情報には、まさに心身ともに打ちのめされていった。将来ずっと自分の意志で排尿・排便のコントロールができない身体とその生活は想像を絶することだった」とあります。四肢麻痺者では、排泄の感覚がないことに加え、これまで習慣や感覚でトイレへ行って排泄行為を行っていたすべての動作ができないのです。「悲しいなあ」という言葉に集約されています。加えて、「摘便の訓練(奥さんの)をされたほうがよいでしょう」というナースの言葉は、身体の回復はわからない上に、排泄の介助が継続して必要であることを示唆された本人と家族の驚きと絶望感がこの文章の中に読み取れます。
この2つのエピソードを通して、脊髄損傷者の急性期における医療スタッフの言動によって、患者とその家族の心の中の動きである回復への期待や不安に大きな影響を与えていることがわかります。重篤な障害を残す可能性が高い疾患の急性期は、希望をつないでいく時期であり、将来の生活を考え始めなければならない時期でもあります。『脊髄損傷の方の健康管理のしおり』を読んだ奥様の不安と覚悟の形成の様子が大変微妙に上手く表現されており、その5日後、受傷して2か月程経過したときに次のような告知が行われました。「2か月経過しても大きな変化(痛みなど)が見えて来ないことなどから、おそらくいまのような状態で、このまま車いすの生活となるでしょう」
これを聞いた奥様は、夫が一生車いす生活になることに加え、その生活がどのようなものになるのか不明であることの不安を伝えています。「目の前の夫に言えないものを抱え込んでしまったことは、この上なく辛いことでした」この時期が奥様と家族にとって一番不安な時期であったと思われます。奥様は、家族の一緒に生活する覚悟について話をした後、「定年までの最後の1年は職場に戻したいと考えていますが、大学への復帰は難しいでしょうか?」と尋ねると、「車いすに座れるし、頭もしっかりしているし、しゃべることもできるんですから、いますぐにでも連れて行きたいくらいです。ぜひそうしてください。そのほうが励みになります」とむしろ賛成してくれました。主治医の過去の経験から、将来を見据えた素晴らしいアドバイスが今後の丸山さんと家族へ希望をつないだと考えています。
主治医が告知した場合は、家族の動揺は当然あるので、専門職によるチーム医療を行っているリハビリテーションセンターなどでは、患者がその動揺を乗り越えるための情報交換を専門領域ごとにしっかり連携して支援しなければなりません。医療スタッフの常識は、患者の常識ではないので、そのことを踏まえてチーム医療することが求められています。
急性期の脊髄損傷者は、動かせない身体でベッドに休んでいる間、回復への期待と回復しないことへの不安が入り混じるため、毎日の医師や医療スタッフ、そして家族などとの会話の中で、自分の身体に関する情報や将来への不安を解消するための情報を収集するのです。
排便や排尿についての機能回復は見えなくてわかりません。丸山さん本人の言葉では、「神経因性直腸・膀胱障害……。脊髄損傷がもたらす四肢麻痺から受けた心のダメージに必死に耐えて来た私は、少し遅れて入ってきたこれらに関する情報には、まさに心身ともに打ちのめされていった。将来ずっと自分の意志で排尿・排便のコントロールができない身体とその生活は想像を絶することだった」とあります。四肢麻痺者では、排泄の感覚がないことに加え、これまで習慣や感覚でトイレへ行って排泄行為を行っていたすべての動作ができないのです。「悲しいなあ」という言葉に集約されています。加えて、「摘便の訓練(奥さんの)をされたほうがよいでしょう」というナースの言葉は、身体の回復はわからない上に、排泄の介助が継続して必要であることを示唆された本人と家族の驚きと絶望感がこの文章の中に読み取れます。
この2つのエピソードを通して、脊髄損傷者の急性期における医療スタッフの言動によって、患者とその家族の心の中の動きである回復への期待や不安に大きな影響を与えていることがわかります。重篤な障害を残す可能性が高い疾患の急性期は、希望をつないでいく時期であり、将来の生活を考え始めなければならない時期でもあります。『脊髄損傷の方の健康管理のしおり』を読んだ奥様の不安と覚悟の形成の様子が大変微妙に上手く表現されており、その5日後、受傷して2か月程経過したときに次のような告知が行われました。「2か月経過しても大きな変化(痛みなど)が見えて来ないことなどから、おそらくいまのような状態で、このまま車いすの生活となるでしょう」
これを聞いた奥様は、夫が一生車いす生活になることに加え、その生活がどのようなものになるのか不明であることの不安を伝えています。「目の前の夫に言えないものを抱え込んでしまったことは、この上なく辛いことでした」この時期が奥様と家族にとって一番不安な時期であったと思われます。奥様は、家族の一緒に生活する覚悟について話をした後、「定年までの最後の1年は職場に戻したいと考えていますが、大学への復帰は難しいでしょうか?」と尋ねると、「車いすに座れるし、頭もしっかりしているし、しゃべることもできるんですから、いますぐにでも連れて行きたいくらいです。ぜひそうしてください。そのほうが励みになります」とむしろ賛成してくれました。主治医の過去の経験から、将来を見据えた素晴らしいアドバイスが今後の丸山さんと家族へ希望をつないだと考えています。
主治医が告知した場合は、家族の動揺は当然あるので、専門職によるチーム医療を行っているリハビリテーションセンターなどでは、患者がその動揺を乗り越えるための情報交換を専門領域ごとにしっかり連携して支援しなければなりません。医療スタッフの常識は、患者の常識ではないので、そのことを踏まえてチーム医療することが求められています。