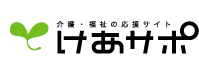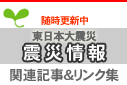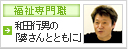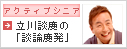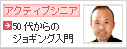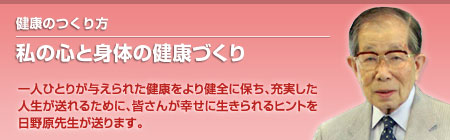
第102回 医療のシステムをどう変えなくてはならないか(1)
最高の結果を出すには
大正から昭和に入ってからの戦前の医療は、医師がオーケストラの指揮者のような役割を果たしていました。医師がタクトを振るい、それに看護師、臨床検査技師、薬剤師などのコメディカルが従属していました。
私は明治44(1911)年生まれですから、1914(大正3)年の第一次世界大戦やその後の不況の影響で、各地に暴動が起こったことなどをはっきりと覚えています。とくに1918(大正7)年に富山県の女性を中心に始まった米騒動は、瞬く間に全国に広がっていきました。お米が高くなりすぎたために、子どもにお米を食べさせたいという母親の願いが暴動となったのです。女性には、「子どものため」ともなると、こういうすばらしい行動力が発揮されるのです。
その頃は、医師は「診療する」という役割をもち、看護師はベッドメイキングなどの「診療の補助」をしていました。医師が診察するための医療機器の用意や、注射器・注射針の消毒、尿のたんぱく質や糖の簡単な検査というようなことが看護師の仕事とされており、小さな役割を担っているにすぎませんでした。
しかし、医療に放射線検査が導入されるようになって、X線撮影の専門家として放射線技師が養成され、この仕事は放射線技師に依頼するようになりました。また、患者にとって大切な食事療法の指導はカロリー計算などに詳しい栄養士が担当するようになりました。
このようにどんな職種の人が何を行っているかを調べると、医師のやっていることの半分以上は看護師をはじめとしたコメディカルの人たちが担っていることがわかってきました。そして、今ではそのようなさまざまな専門職が一人の患者さんやその家族にかかわっていくチーム医療になっています。医師、看護師、薬剤師、理学療養士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、そして時にはボランティアまでが一緒に協力して医療を提供していくことになりますが、さらに病気の主体者である患者や家族の参与も不可欠であるといわれるようになりました。
このように、現代の医療はチームを構成するみんなで多面的に問題を検討し、総合的判断が下せるようなシステムを構築していかなければなりません。臨床に関するあらゆる知識を集結することによって、最高のアウトカム(結果)を生み出すことができるからです。
私は明治44(1911)年生まれですから、1914(大正3)年の第一次世界大戦やその後の不況の影響で、各地に暴動が起こったことなどをはっきりと覚えています。とくに1918(大正7)年に富山県の女性を中心に始まった米騒動は、瞬く間に全国に広がっていきました。お米が高くなりすぎたために、子どもにお米を食べさせたいという母親の願いが暴動となったのです。女性には、「子どものため」ともなると、こういうすばらしい行動力が発揮されるのです。
その頃は、医師は「診療する」という役割をもち、看護師はベッドメイキングなどの「診療の補助」をしていました。医師が診察するための医療機器の用意や、注射器・注射針の消毒、尿のたんぱく質や糖の簡単な検査というようなことが看護師の仕事とされており、小さな役割を担っているにすぎませんでした。
しかし、医療に放射線検査が導入されるようになって、X線撮影の専門家として放射線技師が養成され、この仕事は放射線技師に依頼するようになりました。また、患者にとって大切な食事療法の指導はカロリー計算などに詳しい栄養士が担当するようになりました。
このようにどんな職種の人が何を行っているかを調べると、医師のやっていることの半分以上は看護師をはじめとしたコメディカルの人たちが担っていることがわかってきました。そして、今ではそのようなさまざまな専門職が一人の患者さんやその家族にかかわっていくチーム医療になっています。医師、看護師、薬剤師、理学療養士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、そして時にはボランティアまでが一緒に協力して医療を提供していくことになりますが、さらに病気の主体者である患者や家族の参与も不可欠であるといわれるようになりました。
このように、現代の医療はチームを構成するみんなで多面的に問題を検討し、総合的判断が下せるようなシステムを構築していかなければなりません。臨床に関するあらゆる知識を集結することによって、最高のアウトカム(結果)を生み出すことができるからです。
チーム医療をどのように行うか
では、チーム医療をどのように行っていけばよいのでしょうか。例としてPOSのシステムからとらえたチームワークについて説明しましょう。
POSとは、“Problem Oriented System”の頭文字をとったものですが、アメリカで考案されたこのシステムを私が約45年前に日本に紹介しました。
ウィードというアメリカの医師が、「医師が病歴を書くときにはこういうようにすべきだ」ということから、1969年に『Medical Record,Medical Education and Preventive Care』という著書を出版しました。これは問題志向型診療記録(Problem Oriented Medical Record)に関するもので、医療職による患者の問題解決のために、環境情報や患者や家族の情報、そして身体的アプローチ、人間的アプローチ、社会的アプローチ、QOLに関わるアプローチを整理するというためのものでした。それを受け手1972年、エモリー大学教授であるハーストは、ウィードの提唱したシステムはもともと医師のために作られたものではあるけれども、実際はナースも使うのだから、ナースと医師は同一のチャートに患者の記録を記述するように提唱し、『The Problem Oriented System』を著しました。
私はこの本を1987年に翻訳して医学書院から出版しました。POSは日本語に訳すと「問題志向型システム」といいます。これは、患者のデータを診療録に書くときに、いったい患者の問題は何であるかを考えて記録をすることです。
身体的な問題は何か、精神的な問題は何か、あるいは投薬上の問題は何か。そして、それを解決するためにはこういう検査をやってというように計画する方法が“Problem Oriented System”です。そして病歴を管理するのが病歴管理士“Medical Record Administrator”です。
このような記録を共有するシステムを構築することで、それまでの医師中心の医療から、チームで行う医療が行われるようになりました。患者さんの病歴を、チームのそれぞれが記入して、それぞれが同一の診療録を読む。これは看護師だけが見るもの、あるいは医師だけが見るもの、これは理学療法士、作業療法士だけ見るチャートやカルテというように別々のものにするのではなく、一つに全部が記入される診療録にするものです。この“Problem Oriented System”によって、医師中心の医療からチーム医療に、そして患者中心の医療を普及させるようにするということです。
POSとは、“Problem Oriented System”の頭文字をとったものですが、アメリカで考案されたこのシステムを私が約45年前に日本に紹介しました。
ウィードというアメリカの医師が、「医師が病歴を書くときにはこういうようにすべきだ」ということから、1969年に『Medical Record,Medical Education and Preventive Care』という著書を出版しました。これは問題志向型診療記録(Problem Oriented Medical Record)に関するもので、医療職による患者の問題解決のために、環境情報や患者や家族の情報、そして身体的アプローチ、人間的アプローチ、社会的アプローチ、QOLに関わるアプローチを整理するというためのものでした。それを受け手1972年、エモリー大学教授であるハーストは、ウィードの提唱したシステムはもともと医師のために作られたものではあるけれども、実際はナースも使うのだから、ナースと医師は同一のチャートに患者の記録を記述するように提唱し、『The Problem Oriented System』を著しました。
私はこの本を1987年に翻訳して医学書院から出版しました。POSは日本語に訳すと「問題志向型システム」といいます。これは、患者のデータを診療録に書くときに、いったい患者の問題は何であるかを考えて記録をすることです。
身体的な問題は何か、精神的な問題は何か、あるいは投薬上の問題は何か。そして、それを解決するためにはこういう検査をやってというように計画する方法が“Problem Oriented System”です。そして病歴を管理するのが病歴管理士“Medical Record Administrator”です。
このような記録を共有するシステムを構築することで、それまでの医師中心の医療から、チームで行う医療が行われるようになりました。患者さんの病歴を、チームのそれぞれが記入して、それぞれが同一の診療録を読む。これは看護師だけが見るもの、あるいは医師だけが見るもの、これは理学療法士、作業療法士だけ見るチャートやカルテというように別々のものにするのではなく、一つに全部が記入される診療録にするものです。この“Problem Oriented System”によって、医師中心の医療からチーム医療に、そして患者中心の医療を普及させるようにするということです。
(2013年3月18日)
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 一般財団法人ライフ・プランニング・センター 第40回財団設立記念講演会 |
| 【プログラム】 |
講演1「21世紀型の”よく生きる”とは―グローバル個人主義―」講師:鈴木典比古先生 演奏「音楽療法士による演奏とセッション」林谷嘉子氏 講演2 「創めることは 生きかたを変えること」 講師:日野原 重明先生 |
| 【講師】 |
鈴木典比古(すずき のりひこ)先生(公益財団法人大学基準協会専務理事,前国際基督教大学学長。経営学博士。研究分野は国際経営論) 日野原重明(ひのはら しげあき)先生(聖路加国際病院理事長・同名誉院長。(財)ライフ・プランニング・センター理事長) 林谷嘉子(ピースハウス病院音楽療法士) |
| 【日程】 | 2013年5月25日(土)13:00〜16:15 |
| 【定員】 | 800名 |
| 【会場】 |
笹川記念会館 国際会議場 *都営浅草線・泉岳寺駅より徒歩5分 *JR田町駅より徒歩10分 |
| 【参加費】 |
1,000円 *事前に往復ハガキでの申し込み(5/15消印有効、ただし満席になり次第締め切り)。 |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265−1907 FAX(03)3265−1909 〒102−0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 高齢者と薬について―訪問薬剤師として患者さんから学んだこと― |
| 【講師】 | 寺山泰郎(タカノ薬局鎌倉店,訪問薬剤師) |
| 【日程】 | 2013年4月16日(火)14:00〜16:00 |
| 【定員】 | 500名 |
| 【会場】 |
健康教育サービスセンター 地下鉄・永田町駅下車徒歩4分 |
| 【参加費】 |
500円 |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265−1907 FAX(03)3265−1909 〒102−0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
- この連載に関するお問い合わせ先
-
◆「新老人の会」に関するお問い合わせ先◆
財団法人ライフ・プランニング・センター「新老人の会」事業部
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館5F
TEL:03-3265-1907
FAX:03-3265-1909
ホームページ:http://www.lpc.or.jp/senior_soc/ -
◆日野原重明先生が顧問をつとめている「NPO法人医療教育情報センター」に関するお問い合わせ先◆
医療教育情報センター事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-16 ハイシティ代々木303
TEL:03-5333-0083
FAX:03-5333-0084
ホームページ:http://www.c-mei.jp/