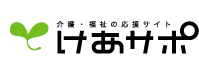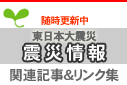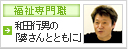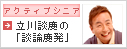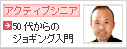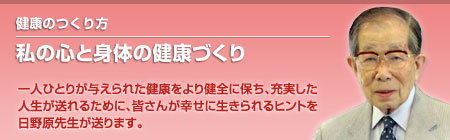
第92回 医術はしばしば和らげる
「患者」とか「病人」を英語では“Patient”といいますが、英語の辞書を引きますと、最初に出てくるのは「忍耐(辛抱・我慢)づよい」という言葉です。つまり、患者とか病人というのは、どんなに辛くても、また体や心が痛くても、じっと耐えている人をいいます。それをどうも私たち日本人は、「疾患をもっている人」という意味でのみ理解しているのではないでしょうか。
医療というのは、耐えている、あるいは辛抱したり我慢したりしている患者の気持ちをきちんと読み取って、できるだけそのような状態から解き放つようにすることです。
これまでの医療では、診断がつく前に痛みを抑える鎮痛剤を処方することはなかったのですが、これからは患者から痛みの訴えがあったらすぐにその痛みに対処し、痛みを軽減させる処置をしながら診断をつけていくようにしなければなりません。
そのことにいちばん最初に取り組まれたのが、英国の近代ホスピスの創始者といわれるシシリー・ソンダース女医です。1967年、ロンドン郊外のシデナムに、セント・クリストファーズ・ホスピスを設立し、ホスピスケアといわれる緩和医療ケアを提供したのです。米国のアポロが月飛行に成功した2年前のことでした。
当時、がん末期の患者には緩和ケアは行われておらず、患者は痛みや苦しみを訴える中で死を迎えなければならない状態でした。いわゆる「デス・エデュケーション」と呼ばれている教育は、欧米ばかりか日本の医学教育や看護教育においても手はつけられておらず、もちろん一般の人々も病気のことはすべて医療におまかせという状況でした。そして、医学は病気の診断とその治療にだけ意を注ぐという状態でした。また、治療に関しても医師(医学)と看護師(看護学)の考え方や働きはまったく別個なものであり、医師と看護師の連係もうまくとれているとはいえない状態だったのです。
私はかねてより、人間の生き方としてはいくら青年期や成人期の人生が充実したものであっても、人生の最後がよくなければ、それは決して幸せな人生とはいえないのではないかという疑問をもっていました。
そのためにソンダース医師のホスピスケアを日本でも普及させたいと考えました。そのためにはまず人材を育てるところから始めなければなりません。医師、看護師をはじめ、そのほかさまざまの専門職です。
まず、海外からの専門家を招聘してワークショップやセミナーを開催しました。1970年代当時、外国から人を招くというのはなかなか大変なことでしたが、米国や英国、オーストラリアなど緩和ケアの先進国から講師を招き、緩和ケアの考え方やその方法について教えてもらいました。
そのようにして、ホスピスが日本につくられたのです。まず、大阪の淀川キリスト教病院や浜松の聖隷浜松病院の緩和ケア病棟のように、総合病院の中に緩和ケア病棟がつくられました。私が理事長を務める財団法人ライフ・プランニング・センターが日本で初めての独立型ホスピス「ピースハウス」を設立したのは1993年のことでした。
現在、日本ホスピス緩和ケア協会に加盟している施設は225、ベッド数は4473床となっています(2011年現在)。そのほとんどが総合病院の中に設置された緩和ケア病棟となっています。緩和ケア病棟とは、患者が痛みや苦しみを緩和する医療を受けるために入院している病棟という意味で、英語では「palliative care unit(パリアティブ・ケア・ユニット)」といいます。
しかし現代の医学では、たとえばがんに対する化学療法はある程度成功したといえるかもしれませんが、次々と治らない新しい病気があらわれ、それに対する治療法を考えるという追いかけごっこのような状態がずっと続いていくのではないかと思います。
天災、事故、難病、そしてすべての人にくる死があります。避けられる死については医学が頑張らなくてはならないのですが、500年前にフランスの外科医、アンブロワーズ・パレ(1510〜1590)の言った言葉に耳を傾けることも必要です。それは「医師はときには治す(to cure sometime)ということです。
病気は病院に行ったからといって治るものではありません。風邪を治療することすらいまだにできていないのです。風邪を治す薬はありません。実は自然に治ってしまうのです。もちろん、解熱剤など苦しい症状を楽にする薬剤はあります。医術は「しばしば和らげる(to relief always)」ことはできるのです。
しかし、いつでも与えることができるのは慰め(to give comfort always)です。医療者はいつでも患者に慰めを与えることが求められていますし、またそれを与えることもできるのです。「末期のがんです。余命は3カ月です」というような冷たい言葉ではなく、どのように説明をするのかが問われています。患者の体と心の辛さや痛みに敏感にならなくてはなりません。
医療というのは、耐えている、あるいは辛抱したり我慢したりしている患者の気持ちをきちんと読み取って、できるだけそのような状態から解き放つようにすることです。
これまでの医療では、診断がつく前に痛みを抑える鎮痛剤を処方することはなかったのですが、これからは患者から痛みの訴えがあったらすぐにその痛みに対処し、痛みを軽減させる処置をしながら診断をつけていくようにしなければなりません。
そのことにいちばん最初に取り組まれたのが、英国の近代ホスピスの創始者といわれるシシリー・ソンダース女医です。1967年、ロンドン郊外のシデナムに、セント・クリストファーズ・ホスピスを設立し、ホスピスケアといわれる緩和医療ケアを提供したのです。米国のアポロが月飛行に成功した2年前のことでした。
当時、がん末期の患者には緩和ケアは行われておらず、患者は痛みや苦しみを訴える中で死を迎えなければならない状態でした。いわゆる「デス・エデュケーション」と呼ばれている教育は、欧米ばかりか日本の医学教育や看護教育においても手はつけられておらず、もちろん一般の人々も病気のことはすべて医療におまかせという状況でした。そして、医学は病気の診断とその治療にだけ意を注ぐという状態でした。また、治療に関しても医師(医学)と看護師(看護学)の考え方や働きはまったく別個なものであり、医師と看護師の連係もうまくとれているとはいえない状態だったのです。
私はかねてより、人間の生き方としてはいくら青年期や成人期の人生が充実したものであっても、人生の最後がよくなければ、それは決して幸せな人生とはいえないのではないかという疑問をもっていました。
そのためにソンダース医師のホスピスケアを日本でも普及させたいと考えました。そのためにはまず人材を育てるところから始めなければなりません。医師、看護師をはじめ、そのほかさまざまの専門職です。
まず、海外からの専門家を招聘してワークショップやセミナーを開催しました。1970年代当時、外国から人を招くというのはなかなか大変なことでしたが、米国や英国、オーストラリアなど緩和ケアの先進国から講師を招き、緩和ケアの考え方やその方法について教えてもらいました。
そのようにして、ホスピスが日本につくられたのです。まず、大阪の淀川キリスト教病院や浜松の聖隷浜松病院の緩和ケア病棟のように、総合病院の中に緩和ケア病棟がつくられました。私が理事長を務める財団法人ライフ・プランニング・センターが日本で初めての独立型ホスピス「ピースハウス」を設立したのは1993年のことでした。
現在、日本ホスピス緩和ケア協会に加盟している施設は225、ベッド数は4473床となっています(2011年現在)。そのほとんどが総合病院の中に設置された緩和ケア病棟となっています。緩和ケア病棟とは、患者が痛みや苦しみを緩和する医療を受けるために入院している病棟という意味で、英語では「palliative care unit(パリアティブ・ケア・ユニット)」といいます。
しかし現代の医学では、たとえばがんに対する化学療法はある程度成功したといえるかもしれませんが、次々と治らない新しい病気があらわれ、それに対する治療法を考えるという追いかけごっこのような状態がずっと続いていくのではないかと思います。
天災、事故、難病、そしてすべての人にくる死があります。避けられる死については医学が頑張らなくてはならないのですが、500年前にフランスの外科医、アンブロワーズ・パレ(1510〜1590)の言った言葉に耳を傾けることも必要です。それは「医師はときには治す(to cure sometime)ということです。
病気は病院に行ったからといって治るものではありません。風邪を治療することすらいまだにできていないのです。風邪を治す薬はありません。実は自然に治ってしまうのです。もちろん、解熱剤など苦しい症状を楽にする薬剤はあります。医術は「しばしば和らげる(to relief always)」ことはできるのです。
しかし、いつでも与えることができるのは慰め(to give comfort always)です。医療者はいつでも患者に慰めを与えることが求められていますし、またそれを与えることもできるのです。「末期のがんです。余命は3カ月です」というような冷たい言葉ではなく、どのように説明をするのかが問われています。患者の体と心の辛さや痛みに敏感にならなくてはなりません。
(2012年5月7日)
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | LPC国際フォーラム2012 がん医療 The Next Step――がん医療にサポーティブケアの導入を |
| 【プログラム】 |
(1)本プログラム:医療者のキャンサーサバイバーの連携―2011年国際フォーラムの報告/キャンサーサバイバーのニーズに応えるケアとは/がん治療外来での患者のQOLに関する問題点/など (2)オプションプログラム:サポーーティブケアからみる「がん患者の苦痛症状のコントロール」 |
| 【講師】 |
Sriram Yennu(テキサス大学M.D.アンダーソンがんセンター専任講師) 山内英子(聖路加国際病院ブレストセンター長) 宮下美香(広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授)ほか |
| 【対象】 |
(1)コース:医師・看護師・教職者・福祉職・コメディカル・医療福祉領域のボランティア *患者さんと家族の方は(2)のオプションプログラムのみ参加可 |
| 【日程】 |
(1)2012年7月14日(土)9:30〜16:30・2012年7月15日(日)9:00〜12:00 (2)2012年7月15日(日)13:00〜16:30 |
| 【定員】 |
(1)本プログラム:300名 (2)オプションプログラムのみの参加者:100名 (定員になり次第締めきり) |
| 【会場】 | 聖路加看護大学アリス・セント・ジョン・メモリアルホール(東京都中央区) |
| 【参加費】 |
(1)本編のみ参加12,000円(LPC会員8,000円) (1)+(2)本編とオプションプログラムの両方参加 14,000円(LPC会員8,000円) (2)オプションプログラムのみ参加 2,000円 |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265−1907 FAX(03)3265−1909 〒102−0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 基礎から学ぶフィジカルアセスメント2012――(3)基礎から学ぶ循環器 |
| 【講師】 | 高橋敦彦先生(日本大学医学部総合健診センター医長) |
| 【対象】 | 看護師、保健師、看護教員、介護支援専門員など |
| 【日程】 | 2012年7月20日(土)10:00〜16:00 |
| 【定員】 | 50名 |
| 【会場】 | 健康教育サービスセンター(地下鉄・永田町駅下車徒歩4分) |
| 【参加費】 | 7,000円(LPC会員5,000円) |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265-1907 FAX(03)3265-1909 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 基礎から学ぶフィジカルアセスメント2012――(2)呼吸器総論/胸部の打診・聴診 |
| 【講師】 | 馬島徹先生((財)化学療法研究会化研病院呼吸器センター長/国際医療福祉大学教授) |
| 【対象】 | 看護師、保健師、看護教員、介護支援専門員など |
| 【日程】 | 6月30日(土)10:00〜16:00 |
| 【会場】 | 剛堂会館(〒102-0094 千代田区紀尾井町3-27) |
| 【参加費】 | 7,000円(LPC会員5,000円) |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265-1907 FAX(03)3265-1909 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 認知行動療法の理解と実践 |
| 【講師】 | 丸屋真也(IFM家族・結婚研究所 代表・相談室長) |
| 【日程】 |
(1)2012年6月22日(金)13:30〜16:00 認知行動療法の理解 (2)2012年7月13日(金)13:30〜16:00 認知行動療法の実践1 (3)2012年9月14日(金)13:30〜16:00 認知行動療法の実践2 (4)2012年10月12日(金)13:30〜16:00 認知行動療法の実践3 |
| 【定員】 | 50名 |
| 【会場】 | 健康教育サービスセンター(地下鉄・永田町駅下車徒歩4分) |
| 【参加費】 |
全4回分12,000円(LPC会員8,500円) *参加費には資料「認知行動療法の理解と実践」(一般財団法人ライフ・プランニング・センター刊)の代金も含まれます。 |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265-1907 FAX(03)3265-1909 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 基礎から学ぶフィジカルアセスメント2012――(1)バイタルサインの異常からアセスメントできること |
| 【講師】 | 徳田安春先生(筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合診療科教授) |
| 【対象】 | 看護師、保健師、看護教員、介護支援専門員など |
| 【日程】 | 5月26日(土)10:00〜16:00 |
| 【会場】 | 健康教育サービスセンター(地下鉄・永田町駅下車徒歩4分) |
| 【参加費】 | 7,000円(LPC会員5,000円) |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265-1907 FAX(03)3265-1909 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 第39回財団設立記念講演会――「いのち」つなげる「いのち」つながる |
| 【講師】 |
講演1「より添いささえる」――震災から1年私の想い 菅野武先生 丸森町国民健康保険丸森病院内科医長・東北大学大学院医学系研究科博士課程。仙台市出身。東日本大震災時、同院において患者の治療・搬送に当たった。2011年4月には米国TIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれる。2011年12月に『寄り添い支える 公立志津川病院 若き内科医の3・11』を上梓した。 講演2「いのちつなげる いのちつながる」 日野原重明先生 聖路加国際病院理事長・同名誉院長。(財)ライフ・プランニング・センター理事長。東京都名誉都民、文化功労者、文化勲章を受章。2000年秋「新老人の会」を立ち上げ会長に。作年からは日本ユニセフ協会大使を務める。 |
| 【日程】 | 2012年5月19日(土)13:30〜16:30 |
| 【会場】 | 笹川記念会館 国際会議場(都営浅草線・泉岳寺駅より徒歩6分・JR田町駅より徒歩10分) |
| 【参加費】 | 1,000円。事前に往復ハガキでの申し込み(5/12消印有効、ただし満席になり次第締め切り)。 |
| 【定員】 | 800名 |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
| 【詳細】 | ファイルをダウンロード(PDF:887KB) |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265-1907 FAX(03)3265-1909 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
|
【参加要綱】 ひとり1枚の往復ハガキに、(1)郵便番号・住所、(2)氏名(ふりがな)、(3)電話番号、(4)会員の方は会員番号(LPC会員・新老人の会)を、会員で無い方は非会員と明記、返信用には住所・氏名を明記の上、下記までお送り下さい。 |
|
|
【申し込み先】(5/12消印有効、ただし満席になり次第締め切り) 〒102−0093 東京都千代田区平河町2−7−5 砂防会館5階 ライフ・プランニング・センター 「財団設立記念講演会」 係 |
|
■セミナーのお知らせ
| 【テーマ】 | 日野原重明先生の指導による東京都訪問介護員養成研修2級課程 |
| 【日程】 | 2012年4月24日(火)〜10月9日(火) |
| 【会場】 | 健康教育サービスセンター(地下鉄・永田町駅下車徒歩4分) |
| 【講師】 | 各領域の専門職 |
| 【関連URL】 | http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm |
| 【詳細】 | ファイルをダウンロード |
|
【主催・問い合わせ先(平日9:00〜17:30)】 (財)ライフ・プランニング・センター TEL(03)3265-1907 FAX(03)3265-1909 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館5階 HP:http://www.lpc.or.jp/health_edu/seminer.htm メールアドレス:lpc_seminar@lpc.or.jp |
|
- この連載に関するお問い合わせ先
-
◆「新老人の会」に関するお問い合わせ先◆
財団法人ライフ・プランニング・センター「新老人の会」事業部
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館5F
TEL:03-3265-1907
FAX:03-3265-1909
ホームページ:http://www.lpc.or.jp/senior_soc/ -
◆日野原重明先生が顧問をつとめている「NPO法人医療教育情報センター」に関するお問い合わせ先◆
医療教育情報センター事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-16 ハイシティ代々木303
TEL:03-5333-0083
FAX:03-5333-0084
ホームページ:http://www.c-mei.jp/